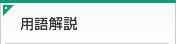原子力発電について
美浜発電所3号機事故について
 原子力安全検証委員会
原子力安全検証委員会
第22回 原子力安全検証委員会
第22回原子力安全検証委員会では「美浜発電所3号機事故の再発防止対策の取組状況」および「原子力発電の安全性向上に向けた自主的かつ継続的な取組みのさらなる充実(ロードマップ)※」について審議が行われましたので、その結果をお知らせいたします。
※2020年度下期の進捗状況については、2021年5月24日にお知らせ済み。
| 1.日 時 | 2021年6月2日(水)13時30分~16時40分 | |||
| 2.場 所 | 関西電力株式会社 本店(大阪市北区中之島) 関西電力株式会社 東京支社(千代田区内幸町) ※ビデオ会議システムにより開催 |
|||
| 3.出席者(敬称略) | ||||
| (委員長) | 【社 外】 |
|
(弁護士) | |
| (副委員長) | 【社 外】 |
|
(東京大学教授) | |
| (委 員) | 【社 外】 |
|
(関西大学教授) | |
| 【社 外】 |
|
(関西大学名誉教授) | ||
| 【社 外】 |
|
(元福井県中小企業団体中央会専務理事) | ||
| 【社 外】 |
|
(東京大学客員准教授) | ||
| 関西電力送配電 株式会社 取締役社長 |
|
|||
| 取締役 代表執行役 副社長 |
|
|||
| (幹 事) | 経営監査室長 |
|
||
- 4.冒頭挨拶
渡邉委員長挨拶骨子 -
- 〇我が国における新型コロナウィルスの感染は、今日なお終息の兆しを見せず、首都圏・関西圏だけでなく、その他の道府県においても、波状的に拡大が続いており、ワクチンの接種もようやく本格的に始まったばかりである。
- 〇このような平常とは異なる厳しい状況下においても、強い使命感を支えに日夜業務に取り組んでおられる医療関係者、電力、ガス、流通など社会インフラ事業に携わる方々に対し、改めて衷心から感謝の意を表したいと思う。
- 〇さて、本年3月、関西電力グループにおかれては、新たな経営理念を策定され、そこには、会社の「存在意義」として『「あたりまえ」を守り、創る』、「大切にする価値観」として「公正」「誠実」「共感」「挑戦」を掲げ、これらの前提として何よりも「安全を守り抜く」ことが明記されている。会社全体が、この理念に基づき、「安全を守り抜く」ことを大前提に、行動することを、決意も新たに宣言されたのである。
- 〇もとより、原子力発電所を運営する関西電力の安全性向上に資する取組みと、これを支える安全最優先の姿勢に対する理解と信頼の獲得、そしてこの理解と信頼を維持・伸長するための弛まぬ努力を重ねていくことこそが、その要諦である。
- 〇改めて申すまでもなく、当委員会の設置目的は、美浜発電所3号機事故を契機として
- ・社外の見識による独立的な立場から、事故の再発防止策を検証すること
- ・原子力安全文化醸成活動、そして福島第一原子力発電所事故を踏まえた原子力発電の自主的・継続的な安全への取組みについて助言を行い、これら継続的な改善に支えられた安全の確保をより確実なものとすること
- 〇原子力安全への取組みに後退や足踏みがあってはならず、「美浜発電所3号機事故を真摯に反省し、二度と起こさない」という決意を原点に、「関西電力における原子力発電の安全性向上の取組み」を、社外の眼で検証・確認するという当委員会の役割は、今後とも変わりなく求められていくものと思う。
- 〇本日は、検証テーマ「原子力発電の安全性向上に向けた取組状況」に基づき、
- ・原子力発電の安全性向上に向けた自主的かつ継続的な取組み(ロードマップ)の取組状況及び監査結果
- ・美浜発電所3号機事故の再発防止対策の取組み状況および監査結果
- ・2021年度検証計画
- 〇委員の皆様には、従前同様、ご専門分野の眼から、また社会一般の眼から、ご検証頂き、忌憚のないご意見、ご助言を賜るようお願いする。
- 5.議事概要
-
5-1.「原子力発電の安全性向上に向けた自主的かつ継続的な取組みのさらなる充実(ロードマップ)」の取組状況および監査結果
「原子力発電の安全性向上に向けた自主的かつ継続的な取組みのさらなる充実(ロードマップ)」の2020年度下期の取組状況について経営企画室から、また同監査結果について経営監査室から報告し、審議。- <報告内容等>
5-2.美浜発電所3号機事故の再発防止対策の取組状況および監査結果
美浜発電所3号機事故の再発防止対策の取組状況について原子力事業本部から、また同監査結果について経営監査室から報告し、審議。- <報告内容等>
- <意見>
-
[労働災害]
- 〇機電工事に重点が移り、機電工事関係の件数が増えているとのことだが、原子力発電所以外の職場での労働災害の発生頻度と比較をしてはどうか。また、工事別の件数の分析以外にも、その工事に関して従事している人数あたりで分析することも必要ではないか。土木工事や機電工事であっても、基本動作を無視する、忘れるということはあると思うので、人数あたりで分析すると、より深い分析になるのではないか。(小澤委員)
- 〇労働災害の撲滅のために、「基本動作不遵守」、「新規入構者」の2点に対して重点的に対策をされたということだが、対策の有効性を確認するためには、労働災害全体で見るのではなく、分析ポイントを絞り、例えば新規入構者による災害の割合が月別でどう変化しているかを見るといった分析を行う必要がある。(荒木委員)
- 〇労災発生件数が着実に減少したのは、対策の効果が示されているためだと思う。また、対策を整理して、効果が見られた取組みを恒常業務として定着させていくことは適切な対応である。
課題として「基本動作不遵守」、「新規入構者」への2つの組み合わせがクローズアップされたが、協力会社による新規入構者に対する導入教育の体系的な見直しが必要ではないか。
新規入構者への教育をしっかりやっていくことが、労働災害の発生を押さえ、維持できることにつながり、重要な役割を果すと思う。(山口副委員長) - 〇新規入構者に労働災害が発生しているが、その中には工事自体については相当の経験年数のある者も含まれているという。そうだとすると、災害が工事において一般的なことが原因で起こっているのか、原子力発電所の工事に特有なものか整理して、その内容に即した導入教育を行わないと力点がぼけるのではないか。このことを意識して対策に取り組むべきであると思う。(渡邉委員長)
- 〇一般的に6~8月は労働災害が増える時期であり、季節的な要因、注意点についても、導入教育等に入れる等、必要な対応に取り組んでいただきたい。(松本委員)
-
[安全文化評価]
- 〇関西電力は、安全最優先とコンプライアンスを含む社会的責任の全うということを、今回新たに策定された経営理念において、その上位概念として掲げられている。原子力発電における安全文化の向上に止まることなく、会社・グループ全体が、新たな経営理念を念頭に、そうあらねばならないという認識を持って、その大きな枠の中で、各部門に必要にして十分な安全文化を醸成し、その向上に努めていただきたい。(渡邊委員長)
- 〇安全文化について掘り下げており、良い取組みと感じた。国際原子力機関(IAEA)には基本安全原則があり、原則3では、安全に対するリーダーシップとマネジメントを定めている。安全文化には三つの要素があり、トップから現場まであらゆる層が安全に対してコミットメントすること、安全に対する説明責任を共有し認識すること、常に学ぶべき姿勢を持つこと、とある。今回の活動はあらゆる階層に対して安全文化を共有しており、IAEAで定める状態に向いて進んでいる。今後、この基本安全原則も参考にする等して、定着させることを進めればよい。(山口副委員長)
- 〇安全文化に対しては、全社的にどこでも同じマインドを持っていることが必要である。原子力をきっかけに全社的に水平展開することもよいと考える(小澤委員)
- 〇経営層が従業員の意見を吸い上げられるような聞く耳を持つことが必要。これには伝える側と聞く側が互いに信頼できる関係であることが重要。(小澤委員)
- ○原子力安全システム研究所(INSS)の小泉所長の講演にもあるように、安全文化の醸成には心理学的なアプローチと社会学的なアプローチが大切。14視点およびそこで抽出された課題について、心理学的な観点と社会学的な観点から整理すれば、新たな気づきが見えてくるのではないか。(荒木委員)
- ○トップのコミットメントと従業員個人の認識のギャップについては、様々な要因が絡んでおり、重要な問題である。安全文化に関する取組みについて、社外役員も含め取締役会で取り上げて、役員にレクチャーしてほしい。(松本委員)
- ○原子力発電の運営に関して、企業・組織の安全文化という観点から現状を評価、分析することは、大変意義のあることと思う。様々な視点から評価されているが、特にお願いしたい点は、原子力発電が危機的な状況を作り出す可能性を秘めていることを肝に銘じ、安全優先の理念、安全文化を強固に身につけた人材、安全文化を支える人材の確保、育成にしっかりと取り組んでいただきたい。(田中委員)
-
[ロードマップ]
- 〇取組状況の報告は、実施内容を中心に記載されており、よく読むとロードマップの取組みに新型コロナウィルスは影響を与えなかったということがわかるが、少し読み取りにくいように感じた。ロードマップの取組みに新型コロナウィルスの影響がなかったと明示的に記載しておく必要があるのではないか。(山口副委員長)
- ○ホームページに加え、X(旧Twitter)やFacebookといったSNSを通じて情報を発信するのは良い取組みだと思う。「事故リスクの最小化」と「事故が発生した際の対応」について一般の関心が高いが、きちんとフォローされており、よいと思う。今回はロードマップの公表に合わせての発信だったが、SNSは頻度高く発信することが大切。(松本委員)
-
[美浜発電所3号機事故の再発防止対策]
- 〇事故から17年経ち、原子力部門でも事故の経験を知らない人も増えてきていると思う。この事故は、技術的な面では解決されてきているが、事故の背景や内容をしっかり伝えていくことが大切だと思う。この点について今回、地域とのコミュニケーションや教育に重点をおかれたのは良いことだと思う。この2つがおろそかにならないように継続的に取り組んでほしい。(山口副委員長)
- ○若手に対し、美浜3号機事故を具体的にどのような説明をするかが大切。事故に至るプロセスを仮想環境の技術を使うなど工夫しながら、分かり易く伝えていくことが大事である。(小澤委員)
- ○原子力エネルギー協議会(ATENA)のガイドラインを2020年度に新たにセルフチェックで活用したということであるが、単に「適切な保全が実施されていることを確認した」という考察で終わるのではなく、この活動を実施したことにより、これまでの保守管理について新しい気づきがあったのか、それとも従来の取組みで十分であったのかといった考察を行って初めて学習する、つまりPDCAのサイクルを回すことができる。(荒木委員)
- ○原子力発電固有のリスクを新入社員や新任役職者に伝えているとのことで、美浜3号機事故を風化させることなく取り組まれていると理解した。原子力事業本部長との膝詰め対話は大変良い取組みだと思う。(松本委員)
- ○美浜3号機事故再発防止の取組みは、安全文化の出発点である。細かいところまでしっかりやっていることが確認でき、評価したい。毎年、被災者の慰霊を実施されており、風化させない、忘れないとの姿勢を示すなど、こうした取組みは安全文化の確立に重要な役割を担っており、今後とも継続していただきたい。(田中委員)
以 上
- 2025年12月4日
社外有識者による「第31回原子力安全検証委員会」審議概要を掲載しました(12月4日更新) - 2025年6月6日
社外有識者による「第30回原子力安全検証委員会」審議概要を掲載しました(6月6日更新) - 2024年12月6日
社外有識者による「第29回原子力安全検証委員会」審議概要を掲載しました(12月6日更新) - 2024年6月7日
社外有識者による「第28回原子力安全検証委員会」議事概要を掲載しました(6月7日更新) - 2024年2月7日
社外有識者による「第27回原子力安全検証委員会」議事概要を掲載しました(2月7日更新) - 2023年8月7日
社外有識者による「第26回原子力安全検証委員会」議事概要を掲載しました(8月7日更新) - 2023年2月20日
社外有識者による「第25回原子力安全検証委員会」議事概要を掲載しました(2月20日更新) - 2022年8月22日
社外有識者による「第24回原子力安全検証委員会」議事概要を掲載しました(8月22日更新) - 2022年2月4日
社外有識者による「第23回原子力安全検証委員会」議事概要を掲載しました(2月4日更新) - 2021年8月23日
社外有識者による「第22回原子力安全検証委員会」議事概要を掲載しました(8月23日更新) - 2021年2月4日
社外有識者による「第21回原子力安全検証委員会」議事概要を掲載しました(2月4日更新) - 2020年8月26日
社外有識者による「第20回原子力安全検証委員会」議事概要を掲載しました(8月26日更新) - 2020年2月6日
社外有識者による「第19回原子力安全検証委員会」議事概要を掲載しました(2月6日更新) - 2019年9月11日
社外有識者による「第18回原子力安全検証委員会」議事概要を掲載しました(9月11日更新) - 2019年1月29日
社外有識者による「第17回原子力安全検証委員会」議事概要を掲載しました(1月29日更新) - 2018年7月17日
社外有識者による「第16回原子力安全検証委員会」議事概要を掲載しました(7月17日更新) - 2018年1月19日
社外有識者による「第15回原子力安全検証委員会」議事概要を掲載しました(1月19日更新) - 2017年7月13日
社外有識者による「第14回原子力安全検証委員会」議事概要を掲載しました(7月13日更新) - 2017年4月7日
社外有識者による第13回原子力安全検証委員会における説明資料および開催結果を掲載しました(4月7日更新) - 2017年3月8日
社外有識者による「第12回原子力安全検証委員会」の説明資料を掲載しました(3月8日更新) - 2017年1月17日
社外有識者による「第11回原子力安全検証委員会」議事概要を掲載しました(1月17日更新) - 2016年7月21日
社外有識者による「第10回原子力安全検証委員会」の議事概要を掲載しました(7月21日更新) - 2016年1月27日
社外有識者による「第9回原子力安全検証委員会」議事概要を掲載しました(1月27日更新) - 2015年8月17日
社外有識者による「第8回原子力安全検証委員会」議事概要を掲載しました(8月17日更新) - 2015年1月8日
社外有識者による「第7回原子力安全検証委員会」議事概要を掲載しました(1月8日更新) - 2014年6月23日
社外有識者による「第6回原子力安全検証委員会」議事概要を掲載しました(6月23日更新) - 2014年2月19日
「第5回原子力安全検証委員会議事概要」を掲載しました - 2013年8月9日
美浜発電所3号機事故に係る再発防止対策の取組み状況等について(8月9日更新) - 2013年5月31日
「第4回原子力安全検証委員会議事概要」を掲載しました - 2013年2月26日
「第3回原子力安全検証委員会議事概要」を掲載しました - 2012年11月28日
「第2回原子力安全検証委員会議事概要」を掲載しました - 2012年8月16日
「第1回原子力安全検証委員会議事概要」を掲載しました - 2012年6月13日
「第18回原子力保全改革検証委員会」を掲載しました - 2011年11月30日
「第17回原子力保全改革検証委員会」を掲載しました - 2011年6月3日
「第16回原子力保全改革検証委員会」を掲載しました - 2010年12月7日
「第15回原子力保全改革検証委員会」を掲載しました - 2010年6月8日
「第14回原子力保全改革検証委員会」を掲載しました - 2009年11月25日
「第13回原子力保全改革検証委員会」を掲載しました - 2009年5月11日
「第12回原子力保全改革検証委員会」を掲載しました - 2008年11月26日
「第11回原子力保全改革検証委員会」を掲載しました - 2008年5月29日
「第10回原子力保全改革検証委員会」を掲載しました - 2007年11月1日
「第9回原子力保全改革検証委員会」を掲載しました - 2007年5月9日
「第8回原子力保全改革検証委員会」を掲載しました - 2007年1月29日
「第7回原子力保全改革検証委員会」を掲載しました - 2006年11月1日
「第6回原子力保全改革検証委員会」を掲載しました - 2006年8月3日
「第5回原子力保全改革検証委員会」を掲載しました - 2006年4月25日
「第4回原子力保全改革検証委員会」を掲載しました - 2006年1月31日
「第3回原子力保全改革検証委員会」を掲載しました - 2005年10月14日
「第2回原子力保全改革検証委員会」を掲載しました - 2005年6月24日
「第1回原子力保全改革検証委員会」を掲載しました
美浜発電所3号機事故に関する疑問にお答えしております。