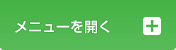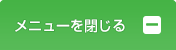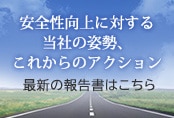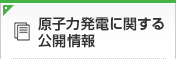2022~2024年度の主な取組項目
2022~2024年度の主な取組項目
1.安全最優先の理念の浸透および定着
安全最優先の理念の共有
経営層の安全最優先の理念に対する明確なコミットメントのもと、経営層が発電所等を訪問するコミュニケーションなどの機会を通じ、所員や協力会社とのコミュニケーション活動を行うとともに、様々な機会においてメッセージ発信を行うことで、安全最優先の理念の浸透に資する活動を行います。また、社達「原子力発電の安全性向上への決意」に係るeラーニングなどの実施など、日々の取組みへの実践につながる活動を継続していきます。
継続的な浸透活動の展開によって、安全最優先の理念に対する理解が深まっている。
![3ヵ年の取組みの図[安全最優先の理念の共有]](images/2024_firsthalf/torikumi_list01.png)
原子力安全に対する経営のガバナンス強化
全ての部門の役員等が委員となっている「原子力安全推進委員会」における多様な安全活動に係る審議に加え、委員会の下部組織である原子力リスクレビュー部会において、原子力以外の技術部門の技術的な観点からも審議を行うなど、経営全体として原子力安全の向上のための取組みを行っていきます。
社達「決意」のもと、原子力部門に対して「支援機能」と「牽制機能」を適切に発揮し、原子力安全を推進している。
![3ヵ年の取組みの図[原子力安全に対する経営企画のガバナンス強化]](images/2024_firsthalf/torikumi_list09.png)
安全文化の発展
組織の状態について安全文化評価を行い、抽出された課題への重点施策を立案、展開するなど、安全文化を高める取組みを行っていきます。
前年度の評価結果において抽出した課題の解決に取り組むとともに、安全文化の評価を行い、安全文化の向上が図られている。
![3ヵ年の取組みの図[安全文化の発展]](images/2024_firsthalf/torikumi_list10.png)
2.安全性向上に関する基盤整備
資源の充実(人財育成・体制整備)
【人財育成】安全・安定運転のために必要な技術要員の人財育成や確実な技術伝承に向けて、人財育成計画の確実な遂行や、力量管理の運用を進めていきます。また、原子力安全システムを俯瞰する人財の育成に向けて、育成キャリアパスの継続的な検討と配置を実施します。
【体制整備】7基稼動・4基廃止措置のプラントを安全・安定に運営するための持続可能な体制構築や社会全体のゼロカーボン化に貢献できる体制構築を進めていきます。
7基運転・4基廃止措置の体制下で自主的・継続的に安全性を高めつつ、社会全体のゼロカーボン化に貢献できる体制構築が進められている。
事故時に所⻑をサポートする参謀機能を担う原⼦⼒安全システムを俯瞰する人財が継続的に育成されている。
確実な技術伝承や、安全・安定運転のために必要な技術要員の人財育成計画の確実な遂行ができている。
![3ヵ年の取組みの図[資源の充実(人財育成・体制整備)]](images/2024_firsthalf/torikumi_list02.png)
3.安全性向上に関する活動の実施
稼動プラントの自主的安全性向上対策の推進
稼動プラントの安全・安定運転に万全を期すため、国内外の新たな知見を踏まえた原子力の安全性向上に関する活動に取り組んでいきます。
原子力の安全性向上に関する活動(自主的な取組み、基盤整備・運用等)に継続的に取り組み、稼動プラントの安全・安定運転に万全を期す。
![3ヵ年の取組みの図[新規制基準対応を含む安全性向上対策の推進]](images/2024_firsthalf/torikumi_list03.png)
事故時対応能力向上のための防災訓練の実施
「事故時対応能力向上のための防災訓練の実施」として、上記の対策に関わらず、原子力事故が発生した場合においても、迅速・的確な事故収束活動により進展・拡大を防ぐとともに、万一事故が進展した場合でも、住民のみなさまが安全に避難できるように、国や自治体、他の電力会社とも連携を図った総合防災訓練や個別の要素訓練を行うなど、事故時の対応能力の向上の取組みを行っていきます。
事故時対応能力を継続的に維持し、新たな知見を踏まえた更なる能力の向上に取り組んでいる。
各地域の緊急時対応(広域避難計画)に基づいた協力、支援を迅速かつ的確に実施できるよう継続的な改善に取り組んでいる。
![3ヵ年の取組みの図[事故時対応能力向上のための防災訓練の実施]](images/2024_firsthalf/torikumi_list04.png)
4.リスクマネジメントをはじめとするマネジメントシステムの確立・改善
リスクマネジメントシステムの継続的な改善
国内外のリスク情報を収集し、定期的に当社への影響について検討を行い、必要に応じて対策を講じる未然防止処置のプロセスを通じて、リスク顕在化を防止しています。また、クレーン倒壊事故対策を含め、労働災害防止に向けた取組みを着実に推進していきます。
リスクマネジメントシステムの継続的な改善に取り組み、また、リスク管理レベルを向上し、原子力の安全性向上に資している。
![3ヵ年の取組みの図[リスクマネジメントシステムの継続的な改善]](images/2024_firsthalf/torikumi_list05.png)
リスク管理・評価等のツールの整備・改善
最新のプラント情報や技術知見を反映したPRA手法の維持管理を実施するとともに、安全性向上評価※においてPRA・ストレステストを用いた評価を行い、評価結果をもとに設備・機器等の改良工事や発電所の運用等の見直しを行うなど、PRAを活用してよりリスク低減につなげる取組みを実践していきます。
※ 安全性向上評価:原子力事業者が、施設の安全性に届出、公表することが法令で定められているもの
各発電所において、リスク情報を活用した継続的な安全性向上活動が定着している。
![3ヵ年の取組みの図[リスク管理・評価等のツールの整備・改善]](images/2024_firsthalf/torikumi_list06.png)
その他マネジメントシステムの確立・改善
原子力事業本部による発電所の安全に関する取組みのパフォーマンスの定量的な評価(管理指標による評価)や現場観察による評価などのオーバーサイト活動により、業務の改善を図るなど、安全性向上の取組みを行っていきます。
発電所の安全に係る取組みのパフォーマンスを評価し、劣化傾向を特定するとともに、必要により発電所への是正を働きかける活動を通じて、継続的に安全性の向上が図られている。
![3ヵ年の取組みの図[その他マネジメントシステムの確立・改善]](images/2024_firsthalf/torikumi_list11.png)
客観的評価・外部知見等の活用
他電力等の知見を活用したオーバーサイト※活動により、安全性向上の取組みを進めていきます。また、デュークエナジー社(米国)やフランス電力会社などの海外電気事業者との経営層をはじめとした様々なレベルでの情報交換や、WANOやJANSIといった外部の原子力安全に係る専門組織などの知見を活用しつつ、継続的に安全性向上に取り組んでいきます。
※ オーバーサイト:発電所の安全に係る取組状況を観察・評価し、改善につなげる取組み
外部の知見を活用し、発電所の安全に係る取組みのパフォーマンスが評価され、発電所の弱みの改善等につながる提言等を得ることで、継続的に安全性の向上が図られる仕組みが整備・運用されている。
国内外の知見を活用し、原子力発電の安全性向上に継続的に取り組んでいる。
![3ヵ年の取組みの図[客観的評価・外部知見等の活用]](images/2024_firsthalf/torikumi_list07.png)
5.コミュニケーションの充実等
リスクコミュニケーションの推進
原子力発電の特性・リスクを十分認識し、立地地域、立地周辺地域、消費地域において、社会のみなさまの疑問・不安に向き合い、共に考えていく姿勢で引き続きコミュニケーションを展開し、頂戴したご意見を当社のリスクマネジメントに活用することで、更なるリスク低減に繋げていきます。
ステークホルダーとの「原子力リスク認識の共有」を図るとともに、ステークホルダーからのリスク情報をリスクマネジメントに反映する活動が継続的に行われている。
![3ヵ年の取組みの図[リスクコミュニケーションの推進]](images/2024_firsthalf/torikumi_list08.png)