エネルギー・環境教育
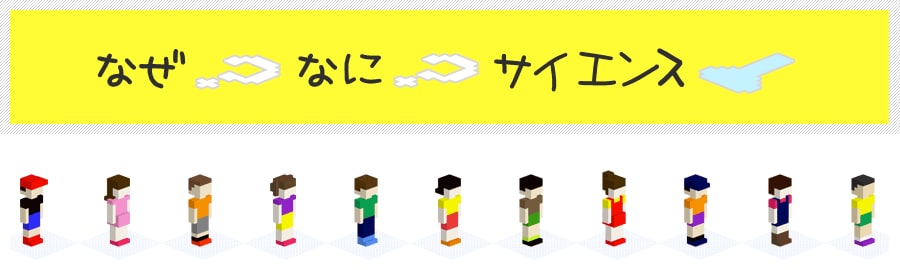

サーモカメラでなにがわかるの?
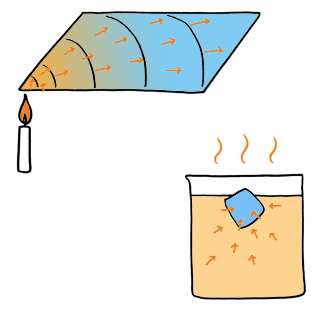 私たちの身の回りのものには、すべて温度があります。温かい物、冷たい物、さまざまあります。物を温めるには、火にあぶったり、熱いお湯につけたりとさまざまな方法があります。逆に、冷蔵庫に入れたり、冷たい水をかけたりすると、温度は下がります。
私たちの身の回りのものには、すべて温度があります。温かい物、冷たい物、さまざまあります。物を温めるには、火にあぶったり、熱いお湯につけたりとさまざまな方法があります。逆に、冷蔵庫に入れたり、冷たい水をかけたりすると、温度は下がります。
このように、温度が変化する原因になるものを「熱(ねつ)」といいます。
熱を加えれば(=加熱する)物の温度は上がるし、熱をうばえば(=冷却する)温度は下がります。
温度がちがう2つの物を合わせると、温度が高い物から低い物のほうに熱が伝わっていきます。そのとき、温度が高い物は温度が下がっていきます。そして、ついにどちらも同じ温度になると、熱の移動がやみます。
たとえばフライパンを火であぶると、中心からだんだん温度が上がっていきます。これは炎(温度が高い物)があたったところでフライパンの温度が上がり、そのとなりの部分にも熱が伝わり、だんだんまわりに熱が伝わっていくからです。これは上の図のように、炎から伝わった熱がまわりに広がっていく流れと考えることができます。
また、熱いコーヒーの中に氷を入れると、みるみるとけてしまいます。これは、コーヒーが持っている熱が、氷に伝わり、氷をとかしたと考えることができます。
このように、熱はつねに温度が高い方から低い方へ移っていきます。
まわりより温度が高い物からは、常に周囲に熱が移動しています。この熱の移動をキャッチして、温度が高い=赤、温度が低い=青というように色分けして表示するのが「サーモカメラ」(サーモグラフィ)です。
どうしてサーモカメラは熱がわかるの?
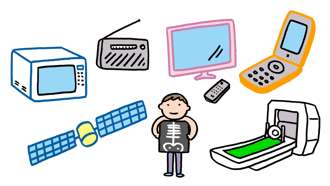 「電磁波(でんじは)」という言葉を聞いたことがありますか?
電磁波とは、その漢字を分解すると、電気の「電」、磁気の「磁」、波長の「波」からなっています。 電気の影響(えいきょう)がおよぶ範囲を電界(でんかい)、磁気の影響がおよぶ範囲を磁界(じかい)といいますが、その電界と磁界がお互いに影響しあってつくられる波が電磁波なのです。
電磁波にはいろいろな種類があり、短波(たんぱ)・長波(ちょうは)などと呼ばれる電波もその一種。そのほか、赤外線(せきがいせん)、可視光線(かしこうせん。目に見える光のこと)、紫外線(しがいせん)、X線(えっくすせん)、γ線(ガンマせん)なども電磁波です。
電磁波のうち、「電波」と呼ばれる種類は、ラジオ、テレビ、携帯電話、衛星通信などに利用されています。
電子レンジで食べ物を温めるのにも、電磁波が使われています(衛星放送と同じ種類の電磁波です)。
日焼けの原因となる紫外線は、殺菌(さっきん)などに利用されています。
X線やγ線は、レントゲンやがん治療(ちりょう)などに利用されています。
「電磁波(でんじは)」という言葉を聞いたことがありますか?
電磁波とは、その漢字を分解すると、電気の「電」、磁気の「磁」、波長の「波」からなっています。 電気の影響(えいきょう)がおよぶ範囲を電界(でんかい)、磁気の影響がおよぶ範囲を磁界(じかい)といいますが、その電界と磁界がお互いに影響しあってつくられる波が電磁波なのです。
電磁波にはいろいろな種類があり、短波(たんぱ)・長波(ちょうは)などと呼ばれる電波もその一種。そのほか、赤外線(せきがいせん)、可視光線(かしこうせん。目に見える光のこと)、紫外線(しがいせん)、X線(えっくすせん)、γ線(ガンマせん)なども電磁波です。
電磁波のうち、「電波」と呼ばれる種類は、ラジオ、テレビ、携帯電話、衛星通信などに利用されています。
電子レンジで食べ物を温めるのにも、電磁波が使われています(衛星放送と同じ種類の電磁波です)。
日焼けの原因となる紫外線は、殺菌(さっきん)などに利用されています。
X線やγ線は、レントゲンやがん治療(ちりょう)などに利用されています。<ここ>では、「サーモカメラは熱がわかる」と説明しましたが、サーモカメラが本当に見分けているものは正確には、物体から放たれている赤外線のエネルギー量ということができます。 赤外線は目に見えない電磁波で、温度が高い物体ほど赤外線を強く出して(放射して)います。 サーモカメラは特殊なレンズでこの赤外線を見分け、赤外線が多い(=温度が高い)=赤、赤外線が少ない(=温度が低い)=青のように色分けして表示します。 赤外線は、明るさ/暗さに関係なく伝わるので、サーモカメラを使うと、やみ夜の森の中などでも、動物などを見つけることができます。