事業所・関連施設
 原子力事業本部
原子力事業本部
越前若狭探訪
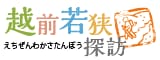
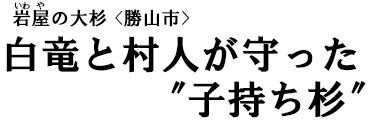


▲主幹から5本の幹が分かれて伸びる巨大な岩屋の大杉。
根元には祠と石仏が祀られている。
勝山市北郷町(きたごうちょう)の山間(やまあい)にある岩屋(いわや)観音堂の傍(かたわ)らにそびえる「岩屋の大杉」(市指定天然記念物)は、かなり古くに主幹(しゅみき)の大半を失った後も命を保ち続けた。数m残った主幹から伸び出た5本の幹が、今ではいずれも大木に育ち、親が子をたくましく支えているような姿から〝子持ち杉〞とも呼ばれる。うち1本は下向きに湾曲した後、天に向かい、まるで巨大な象の鼻のようだ。
福井県自然保護センターのホームページ「ふくいの巨木」では、この大杉について、幹回り17m、樹高33m、樹齢約500年と推定。伝承では樹齢1200年ともいわれ、見る者を圧倒する力強い樹形から、「日本有数の大迫力」と評価する巨木ファンも多い。
言い伝えによると、「岩屋の大杉は昔、12本に分かれていた。あるとき盗人がこの杉を切ろうとしたが、途中で白竜が現れて、残った幹を命がけで守り、以来、白竜は大杉の根元に棲(す)み着いた」。多くの人は、これをおとぎ話の類(たぐい)と思っていたが、1967年(昭和42)、観音堂を修復した際に白蛇が出現。白竜伝説は信憑(しんぴょう)性を帯び、人々は改めて信仰を深めたという。
▼岩屋観音堂(右奥)と拝殿。大杉はその向こう側。周辺一帯は、奈良時代に白山を開いた泰澄大師ゆかりの寺跡とされる。


▲岩屋の大杉から遊歩道を登った山腹に、直立してそびえる「飯盛杉(いいもりすぎ)」(幹回り7m、樹高35m)。

▲修験者が胎内くぐりの行をした岩窟。大木が岩の上にそそり立っている。
周辺一帯は、奈良時代に白山を開いた泰澄(たいちょう)大師ゆかりの寺跡とされる。岩屋は、豊原寺(とよはらじ)(現坂井市)と平泉寺(へいせんじ)(現勝山市)を結ぶ道筋にあたり、修験者(しゅげんじゃ)が山伝いに行き来した。山腹には巨岩が連なり、「胎内(たいない)くぐり」の行場(ぎょうば)になった岩窟(がんくつ)もある。
大杉を神木として守り続けてきた岩屋には、明治・大正期に250人を超える多くの人が暮らしたが、三八(さんぱち)豪雪(1963年〔昭和38〕)で離村が進み、その2年後の秋の風水害で、冬を待たずに無住の集落となった。以後は、元住民によって組織された岩屋観音奉賛会が信仰を守り継いでいる。
大杉を神木として守り続けてきた岩屋には、明治・大正期に250人を超える多くの人が暮らしたが、三八(さんぱち)豪雪(1963年〔昭和38〕)で離村が進み、その2年後の秋の風水害で、冬を待たずに無住の集落となった。以後は、元住民によって組織された岩屋観音奉賛会が信仰を守り継いでいる。

【参考】『図説勝山市史』(勝山市・1997 年発行)、『神木探偵』(本田不二雄著・2020年発行)