事業所・関連施設
 原子力事業本部
原子力事業本部
越前若狭探訪
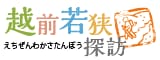
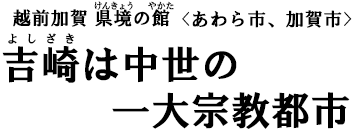


▲上空からドローンで撮影した吉崎御坊跡(御山)と福井・石川の両県にまたがる吉崎の町並み

▲越前加賀県境の館の玄関ホールに展示されているジオラマ。赤い線は県境で、左側が福井県。吉崎の町を県境が縦断している。
福井県北端のあわら市吉崎(よしざき)と、石川県加賀市吉崎町(よしざきまち)は、県境で隣り合っている。その境目は複雑に入り組んでいて、狭い路地やブロック塀の向こうが隣の県だったり、中には庭や建物が県境をまたいでいる家さえある。
北潟湖畔(きたがたこはん)にある「越前加賀県境(けんきょう)の館(やかた)」は、2015年(平成27)4月、あわら市と加賀市が共同で県境に整備。玄関から建物内、屋外まで敷石などで県境を色分けしている。

▲日本海方向
歴史上、平安期の823年(弘仁(こうにん)14)、越前国を分国して新たに加賀国が置かれてから、吉崎は国境(くにざかい)となった。
戦国時代の初頭、吉崎が歴史の表舞台に登場する。浄土真宗中興(ちゅうこう)の祖、蓮如(れんにょ)上人が延暦寺(えんりゃくじ)から迫害を受け、1471年(文明3)、越前吉崎の御山(おやま)(標高33m)に吉崎御坊(ごぼう)(本堂、僧堂、庫裏(くり)、書院、鐘楼など)を建立、北陸における布教(ふきょう)の拠点とした。ここに吉崎参りの門徒らが大挙押し寄せた。

▲県境の館から望む「鹿島の森」。全体が神域とされ、暖帯性照葉樹の原生林となっている。

▲建物内外の県境を敷石等で色分け(左側が福井県)。コロナ禍前は例年秋に館の前で、両県民が“領地”をかけて綱引き大会を開催。

▲現在の国道305号線の県境付近。江戸期には、福井藩と大聖寺藩がそれぞれ番所を置き、人や荷の往来を取り締まった。
当時の吉崎御坊は3方向を湖に囲まれた天然の要害で、吉崎は海陸交通の要衝だった。蓮如上人の吉崎滞在は、わずか4年余りだったが、御山の上には御坊を守護する約50の寺院が坊舎(寺院多屋(たや))を建て、麓にも約200の民宿多屋が軒を連ね、商人や職人、水運・陸運に携わる人々が集まって寺内(じない)町を形成。平安期に定められた国境を越えて、一大宗教都市へと発展した。
寺内町は、門前町と異なり、町全体が寺の境内にあって防御機能を持つ。吉崎は、わが国初の代表的な寺内町だ。
しかし、御坊の建立から35年後、朝倉氏によって破却され、以後は廃坊となった。
蓮如上人や吉崎御坊について解説展示している県境の館から対面に、国の天然記念物「鹿島(かしま)の森(もり)」がある。江戸中期頃までは離れ島だったが、大聖寺(だいしょうじ)川が運ぶ土砂が堆積、大聖寺藩は新田(しんでん)開発を進めるとともに鹿島新道(しんみち)を造り、加賀吉崎と陸続きになった。その領地は越前か加賀か、長く帰属が定まらず、1884年(明治17)に、時の内務卿(ないむきょう)山縣(やまがた)有朋(ありとも)の裁定で加賀(石川県)とされた。町の中に正式な県境が引かれたのもこの時。越前吉崎と加賀吉崎は町筋も小路も排水路も入り交じっていたから、その線引きは複雑なものとなり、現在に至っている。

▲鴫谷山(しぎたにやま)の切通し
かつて道が険しく吉崎参りの難所だった蓮如道(吉崎古道)の鴫谷山。1887年(明治20)に人力で掘り下げた場所で、道の両側には山壁が切り立っている。
越前加賀 県境の館 あわら市吉崎2丁目1004-2  0776-75-1705
0776-75-1705
入館無料。休館は火曜(祝日の場合は翌平日)。
開館9時から17時(入館は15分前まで)
【参考】『金津町吉崎の郷土誌』(金津町教育委員会・1999年発行)
越前加賀県境の館の末富攻館長からご教示・ご案内をいただきました。
