事業所・関連施設
 大飯発電所
大飯発電所
おおい町の語り部たち
山おろし (町指定無形民俗文化財) |
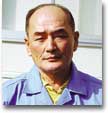 |
| |||
|
勇壮な太鼓は、山おろしの華 |
|
鹿野の「山おろし」は、火勢行事の一環として行われます。大飯町には、いくつかの区で今も火勢が残っていますが、山おろしがあるのは、この鹿野だけ。8月15日の夜、全員が白装束(鉢巻、ワイシャツ、トレパン、運動靴か地下足袋、草履)で、隣接する小車田との境の竹の越地籍の火勢山に登り、火勢を上げます。ここで少し景気づけにお酒を飲み、そこから「山おろし」の行事となります。 「山おろしは太鼓を先頭に降りますが、山の上での太鼓とはリズムが違って独特のものです。山裾で初めて太鼓を地上に降ろし、大太鼓と中太鼓の2つの太鼓の競演をします。そして集落に入り、出迎えに集まった人たちの前を通って仏燈寺へ向かうわけですが、ここから練り込み太鼓で、目的地が近づくにつれてだんだんテンポが速くなるんですね。そして仏燈寺の境内で太鼓を2つ並べて叩きます。集落に入ってからと仏燈寺では誰が叩いてもよく、バチの取り合いになります」。 長年、山おろしの太鼓を打ち続けてきた竹内正輝さんがその様子を詳しく語ります。 山に上がるとき、山の上、山おろしのとき、裾野、練り込み、境内・・・・・・と場面ごとに6種類の叩き方があり、これを覚えるのが難しいそうです。 | |
 火勢山での火勢が終わった 後で、山おろしが始まります。 松明の明かりの中で、太鼓を 先頭に、鉦や笛が続きます。 |
仏燈寺の境内では、櫓が組んであり、火勢に参加した者だけで鹿野独特の「山おろしの踊り」を踊ります。2番目に「かごや踊り」、最後に「ばんば踊り」でしめて火勢行事が終わります。 「太鼓、鉦(かね)、笛、提灯、松明の組み合わせが、小さい頃は異様に感じました。もう少し大きくなれば勇壮な感じに変わり、山を登ると大人の仲間入りができたような気がしたものです。同時に太鼓を打つことに憧れました。」尾谷和孝さんの子供時代の印象です。「山に登るときから、山の上、山おろしまでずっと一人で叩くので、体力的にも大変。でも何と言っても、太鼓は山おろしの華なんですよ。今は尾谷くんに引き継ぐことができて、私もすっかり安心です」と嬉しそうに語る竹内さんでした。 |
 仏燈寺の境内では、 誰が叩いてもいいから、 バチの取り合いに。 |
 |
| |||
 |
太鼓を打つのは、 小さい頃から好きで、 遊びのひとつでした。 |
先輩の竹内さんに4年ほど前から太鼓を教わっています。子供時代から竹で組んだ籠をかついで、真似して叩いて遊んだものです。田舎では、山おろしが一番の行事。お盆に帰省する人たちも、一緒に参加するのを楽しみにしています。子供から大人まで、男だけで登ります。この勇壮な行事をずっと守っていきたいですね。 | |
|
尾谷 和孝 さん | |||
|
|
| ||