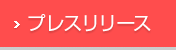プレスリリース
 2008
2008
2008年10月15日
関西電力株式会社
原子力発電所の運営状況について
当社の原子力発電所における運営状況について、以下のとおりお知らせします。
| 1.運転状況について(平成20年10月14日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.トラブル等情報について
| (1) 法令に基づき国に報告する事象(安全協定の異常時報告事象にも該当する事象) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発電所名 | 高浜発電所4号機 | 発 生 日 | 第18回定期検査中 (平成20年9月22日) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 件 名 | 蒸気発生器伝熱管の渦流探傷検査における有意な信号指示の確認結果の原因と対策について (添付図2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事象概要 および 対 策 等 |
第18回定期検査中に、3台ある蒸気発生器(SG)の伝熱管全数※1について渦流探傷検査(ECT)※2を実施した結果、C−SGの伝熱管1本の高温側管板※3部に、有意な信号指示が認められました。なお、A,B−SGの伝熱管については、有意な信号指示は認められませんでした。
本事象による環境への放射能の影響はありません。
[平成20年9月22日、10月3日 お知らせ済み]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発電所名 | 高浜発電所4号機 | 発 生 日 | 第18回定期検査中 (平成20年10月3日) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 件 名 | A、B、C−蒸気発生器入口管台溶接部での傷の原因と対策について (添付図3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事象概要 および 対 策 等 |
第18回定期検査中に、国内外で発生した600系ニッケル基合金溶接部での応力腐食割れ事象を踏まえ、3台ある蒸気発生器(SG)の1次冷却材出入口管台溶接部(計6箇所)について予防保全工事※1を実施する計画でした。
この工事のため、事前に入口管台溶接部内面について渦流探傷試験(ECT)※2を行ったところ、A−SG入口管台溶接部で7箇所、B−SG入口管台溶接部で8箇所、C−SG入口管台溶接部で21箇所の有意な信号指示(最大長さ A−SG:約14mm、B−SG:約30mm、C−SG:約33mm)を確認しました。 SG入口管台溶接部においてECTによる有意な信号指示が認められた36箇所について、傷の深さを確認するため超音波探傷試験(UT)※3を実施した結果、A−SGで最大深さ約12mm、B−SGで最大深さ約13mm、C−SGで最大深さ約16mmの傷と評価しました。 この結果、AからCの各SGで、当該部の板厚が電気事業法に基づく工事計画書に記載の板厚※4を下回ること※5が分かりました。 本事象による環境への放射能の影響はありません。 傷が発生した原因調査のため、AからC−SGの入口管台溶接部内表面の外観目視観察および型取観察等を行った結果は、以下のとおりです。
[平成20年10月3日、10日 お知らせ済み]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)安全協定の異常時報告事象
なし
(3)保全品質情報等
なし
以 上