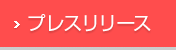プレスリリース
 2008
2008
2008年10月31日
関西電力株式会社
大飯発電所3号機の原子炉起動および調整運転の開始について
大飯発電所3号機 第13回定期検査の概要
| 1. | 主要な工事等について |
| (1)600系ニッケル基合金溶接部の応力腐食割れに係る点検・予防保全工事 | |
| (図−1参照) | |
|
国内外PWRプラントにおける600系ニッケル基合金溶接部の応力腐食割れ事象を踏まえ、原子炉容器のAからDループ出入口管台溶接部と炉内計装筒の内面および溶接部については外観目視点検や渦流探傷試験を、D蒸気発生器の出入口管台と加圧器安全弁の溶接部については外観目視点検や超音波探傷検査を実施しました。
その結果、原子炉容器のAループ出口管台溶接部において、渦流探傷試験で応力腐食割れによる傷が認められたことから、研削により傷を除去しました。また、その他の部位については、異常のないことが確認されました。 予防保全対策として、溶接部の残留応力を低減させるため、原子炉容器のAからDループ出入口管台の溶接部と炉内計装筒の内面および溶接部にウォータージェットピーニング工事※1を施工しました。 (6(3)を参照)
|
|||||||
|
|||||||
| (2)1次系強加工曲げ配管取替工事 | (図−2参照) |
| 海外BWRプラントにおいて、芯金を使用して冷間加工したことにより曲げ管の内面で応力腐食割れが発生した事象を踏まえ、予防保全として、1次冷却材系統につながる口径が約10cm以下の曲げ管を、芯金を使用しないで曲げ加工した配管に取り替えました。 |
| (3)亜鉛注入装置設置工事 | (図−3参照) |
| 作業員の被ばく低減を図るため、1次冷却材中に含まれるコバルト60等の放射性物質が、機器や配管内表面への付着を抑制する効果がある亜鉛を1次冷却材中に注入する装置を、化学体積制御系統に設置しました。 | |||
|
| (4)耐震裕度向上工事 | (図−4参照) |
| 設備の耐震性を一層向上させるための耐震裕度向上工事について、工事実施箇所の検討が終了した原子炉冷却系統、安全注入系統、余熱除去系統、主蒸気系統の配管の支持構造物29箇所の強化工事を追加で実施しました。 |
| 2. | 保全対策について |
| (1)高サイクル疲労割れに係る対策工事 | (図−5参照) |
| 国内PWRプラントにおける高サイクル熱疲労割れ事象(温度ゆらぎによる疲労)を踏まえ、AおよびB余熱除去冷却器バイパスライン合流部の2箇所について、応力集中が小さい溶接形状のものに取り替えました。 |
| (2)2次系配管の点検等 | (図−6参照) |
|
当社の定めた「2次系配管肉厚の管理指針」に基づき、2次系配管1,960箇所について超音波検査(肉厚測定)等を行った結果、必要最小厚さを下回る箇所および次回定期検査までに必要最小厚さを下回ると評価された箇所はありませんでした。 (超音波検査1,937※2箇所、内面目視点検23箇所) |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 今定期検査開始時には119箇所の配管取替を計画していましたが、減肉傾向が見られた箇所2箇所を追加し、合計121箇所の配管を取り替えました。 | |||||||||||||||||||
| 3. | 蒸気発生器伝熱管の渦流探傷検査結果 |
| 蒸気発生器4台のうち、BおよびD−蒸気発生器伝熱管全数(3,382本×2台、計6,764本)について、渦流探傷検査を実施し、異常のないことを確認しました。 |
| 4. | 燃料集合体の取替え |
|
燃料集合体全数193体のうち、81体(うち56体は、55,000MWd/t高燃焼度燃料の新燃料集合体。)を取り替えました。
また、燃料集合体の外観検査(99体)を実施した結果、異常は認められませんでした。 |
| 5. | 次回定期検査の予定 |
| 平成21年秋頃 |
| 6. | 定期検査中に発生した安全協定に基づく異常事象 |
| (1)中性子源領域検出器の電源断による一時的な停止について | (図−7参照) |
| 平成20年2月7日、2台ある中性子源領域検出器※3の電源が約40秒間切れ、その間の記録が欠測しました。事象発生時、原子炉内に燃料が装荷された状態であり、この状態では保安規定で定める運転上の制限として1台以上の中性子源領域検出器で原子炉の状態を監視することが要求されています。このことから、記録が欠測した間、運転上の制限を満足していないと判断しました。
調査の結果、原子炉保護系制御装置の点検作業において、当該検出器の切替えスイッチを誤って操作した結果、電源が切れたものと確認されました。また、切替え操作は、プラントの運転操作を行っている発電室から点検担当課に操作移管されていましたが、確実な操作確認が実施されていませんでした。 対策として、保安規定の運転上の制限に係わる操作については、発電室から点検担当課に操作移管を行わず、発電室が直接操作を行うこととしました。 |
|||
[2月15日お知らせ済み]
|
| (2)所内電源喪失に伴う非常用ディーゼル発電機の自動起動について | (図−8参照) |
| 平成20年3月18日、発電機窒素ガス封入装置※4の電磁弁の動作確認試験を行っていたところ、送電線から所内電源を供給するために投入されていた主変しゃ断器が開放し、所内電源が喪失するとともにB—非常用ディーゼル発電機が自動起動しました。
調査の結果、当該試験では、テストスイッチを使用する必要がありましたが、作業員の誤認識、作業要領書の誤記載および作業実施にあたってのチェック機能不足によって、正常な作業がなされていませんでした。 対策として、作業要領書の修正、作業着手前の要領書再確認の徹底を行うこととしました。 |
|||
|
| (3)原子炉容器Aループ出口管台溶接部の傷の原因と対策 | (図−9参照) |
| 国内外で発生した600系ニッケル基合金溶接部での応力腐食割れ事象を踏まえ、原子炉容器の1次冷却材出口および入口管台の溶接部(計8箇所)内面について、予防保全としてウォータージェットピーニング工事を実施する計画としていました。この工事に先立ち、溶接部内面の渦流探傷試験※5を実施したところ、Aループ出口管台部で有意な信号指示が1箇所認められ、水中カメラによる目視点検で長さ約3mmの傷が認められました。なお、当該箇所以外では有意な信号指示は認められませんでした。
目視点検で認められた傷について、超音波探傷試験※6を実施した結果、傷の深さは特定できませんでした。傷の深さを特定するため、工事計画認可申請書※7の記載板厚を変更し、傷を中心に円弧状に深さ約20.3mmまで削った結果、目視点検で傷が認められず、渦流探傷試験でも有意な信号指示が確認されなくなりました。その後、さらに約0.7mm削り、目視点検および渦流探傷試験で傷がないことを確認しました。 以上の結果、傷があった部分の板厚は約53.6mmとなりました。 調査の結果、溶接部の金属境界に沿って深さ方向に進展している割れが認められ、引張り残留応力が生じる切削加工跡が確認されたことから、当該部で応力腐食割れが発生・進展したものと推定されました。 対策として、傷を全て削り取った形状にて、ウォータージェットピーニング工事を施工しました。なお、次回定期検査で耐食性に優れた690系ニッケル基合金による補修溶接等を実施する予定です。 |
|||||||
|
以 上