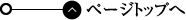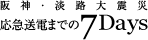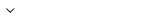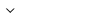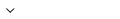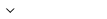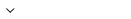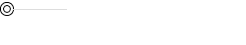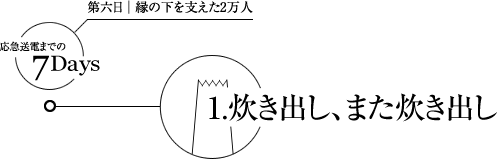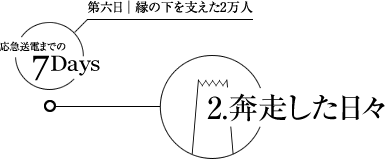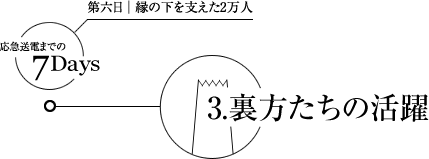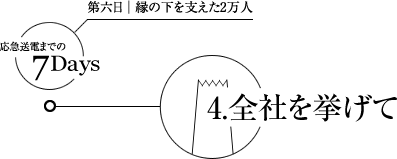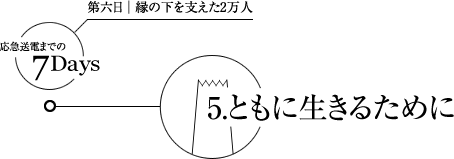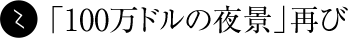三宮営業所庶務課の寺内敦能は、震災当日から「炊き出し」を担当した。他の営業所や電力会社からの応援部隊の分を含め、1回に用意する食事は2500人分だった。
当初は水の確保が一番の難問だった。社屋は損壊し、水道も使えない。17日には水の購入に神戸市内を走り回った。購入した水は飲料以外にも使用するため、ペットボトルから18リットルの石油容器に移し変えた。これにも思わぬ時間と手間がかかった。電気ももちろんだが、蛇口を捻るだけで水が出るのは有り難いことだ。作業を続けながら、改めてそう思った。
食事時は、まさに眼の回るような忙しさだった。ガレージの仮設営業所に入りきれず、路上で食事をとる作業員も多い。そんななかを何度も行き来し、弁当を配ったり、カップラーメン用のお湯やお茶をサービスしたり……。昼食時は時間もバラバラなので少しは交代で息もつけたが、作業員が次々に戻ってくる夕食時は、15人の炊き出し班が総出で走り回った。
あっと言う間に一日が過ぎ、誰もが疲れ果てた。けれども寝具の整った宿泊所は現場作業員を優先。裏方の寺内たちは車の中で仮眠をとり、早朝4時には起き出すと、また朝食のための湯沸かしを始めた。それでもみんな不平一つ口にせず、必死で作業員たちを支え続けた。
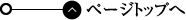

炊き出し班も奮闘
兵庫営業所の京谷健も、同様の日々を送っていた。
17日に出社し、所員の安否確認などを行った後は、作業員への炊き出しが京谷の主な仕事になった。ところが営業所自体の損傷がひどく、食堂もグチャグチャ。冷蔵庫は倒れ、都市ガスは止まり、使える鍋釜もほとんどない。ふだん食堂の賄いをお願いしている業者も、もちろん出勤していなかった。
とりあえず緊急用に備えてあった2口のプロパンガスと米を探し出し、どうにか使えそうな鍋で米を炊いた。炊き上がったご飯は、所員5人でおにぎりにした。そしてまたその鍋で米を炊く繰り返し……。朝、昼、夕食に加え、夜遅く戻ってくる作業員のための夜食と、1日4食。あとで振り返っても、京谷にとって震災当初は「おにぎりを握り続けた日々」という印象が何よりも強かった。
2日目には早くも食材が底をついた。市内では食料が手に入らず、自宅のある小野市まで買い出しに行った。営業所を朝7時に出発して、戻ってきたのは夕方だった。小野市のスーパーでも食料を買い求める人々が長蛇の列をなしていた。
炊き出し以外に、作業員用宿泊場所の手配も手伝った。営業所内の廊下に布団を敷いたり、湊川変電所にテントを設営したりした。100人収容のテント設営は、夜半から早朝までの作業になった。
ガソリンの確保にも苦労した。震災当初は近隣のガソリンスタンドが閉店していたため、周辺に範囲を広げて片っ端から連絡を入れた。ようやく何軒か確保しても、やはりガソリン確保に奔走していた警察署・消防署に譲ったこともあった。中国電力の応援部隊がガソリンを持参してくれた時には「助かった!」と思った。
輸送ルートが整い、本店から弁当が届くようになってからは、一部を近くの避難所へ差し入れた。「ずっとパンやおにぎりだったから、おかずのある弁当は本当に嬉しい」。避難所の人々に感謝され、京谷も嬉しくなった。
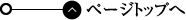

支援物資
日曜日を迎えても、一時も休むことなく続いた復旧作業。その現場を陰で支えた「縁の下」たちにとっても、毎日が闘いの日々だった。
兵庫営業所では非常災害対策本部の総務班を、食料班、物資調達班、環境班、記録班に分けた。食料班は炊き出しや弁当の搬入・配分に奔走した。
物資調達班は連日本部に待機し、所内のニーズをまとめ支店・本店などとの連絡調整を行った。「配電工具から梅干し、マスク、線香、清め塩まで、まさに百貨店仕入れ責任者のような活躍を見せてくれた」と、のちに土山裕司所長は振り返った。
環境班は寝具の調達や宿泊場所の確保、簡易トイレの設置や処理手配、風呂場の男女入浴制限管理など、あらゆる生活ニーズの処理班となった。応援部隊も増え、環境維持が重要となるなか、地味ながら欠かせない存在だった。
記録班はその名のとおり、復旧に関わるすべての活動を記録するのが役割だった。毎日の復旧作業状況はもちろん、激励や慰問に訪れたお客さまや救援物資のリストまで……。将来の参考にするべく、あらゆる動きを克明に書き記し続けた。
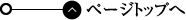

地下食堂で仮眠をとり復旧作業にあたる
本店各部門も、総力を結集して現場を支援した。
総務部門ではまず、物資の輸送ルート確保に全力を挙げた。海・陸両ルートの輸送体制を整えた後は、現地のあらゆるニーズに応え、食料ほか生活物資を送り続けた。現場での通信連絡に携帯電話が重宝されるようになると、全国各地から380台をレンタル調達し、各営業所に送り込んだ。
資材部門でも当初は、輸送手段や車両の確保に追われた。交通渋滞の凄まじさから、一時は空輸も検討したが、積載重量や飛行ルートに制約があることなどから、陸上輸送を主にした。幸い大阪府茨木市の資材センターに大きな被害はなく、1日約30便のトラックも確保できた。
日がたつにつれ資材部門には、復旧資機材以外にも様々な調達依頼が殺到した。「フロアに寝ている作業員が多い。畳を調達できないか」「断水で手が洗えない。ウェットティッシュが欲しい」「降雨対策用にビニールシートと土嚢袋を手配してほしい」。すでに関西地区では在庫が底をついていた物品も多かったが、資材部門は万難を排して、現場の要望に応え続けた。
被災地の状況が徐々に確認されるなか、秋山喜久社長は「前例にこだわらず、関係部門が全力を挙げて被災した社員の救済に取り組む」よう指示した。これを受けて労務部門では19日、「被災従業員支援センター」を設置。住居の提供や生活物資の配布、医療支援などを行った。
このほか阪神地区以外の支店・営業所でも、多くの社員が被災地に出向き、現場の復旧作業や後方支援活動を助けた。関西電力はまさに全社──2万6000人が一丸となって復旧をめざしたのだ。
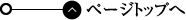

ふれあいキッチン号での炊き出し
同時に関西電力では、地域に根ざした公益事業として、被災地の支援活動にも力を注いだ。
特に応急送電体制が整った後は、避難所などに街路灯を設置する「ライトアップ作戦」を展開したほか、シャワー用電気温水器や電気焼却式トイレの設置、電気調理器を積み込んだ「ふれあいキッチン号」での炊き出しも行った。
「限られた範囲での支援だったので、どれだけお役に立てたのかという反省も残ったが、当社自身も被災し、電力復旧という使命を抱えたなかでは精一杯の活動だった。とにかく我々にできることはと考えたら、電気の明るさや温かさ、清潔さをお届けすることこそ何よりの支援と思った」。地域共生本部統括グループ課長の戸神良章は、のちにそう語った。
個人で、あるいは事業所内で有志を募り、ボランティア活動に参加した社員も多かった。そうした社員の活動をサポートするため、関西電力も10日間の特別休暇を認定した。この制度を活用し、被災地への物資配布や給水活動などに携わった社員は延べ656人。社員一人一人もまた地域に生きる一員として、被災地の復興に微力を尽くそうとしていた。
22日午後1時半現在、停電軒数は1万5000軒となった。