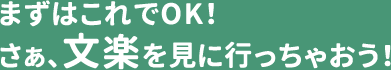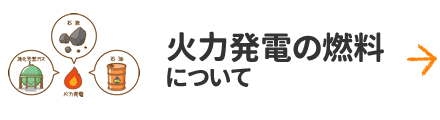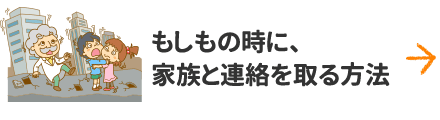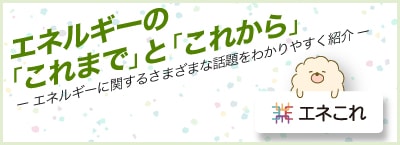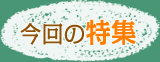
実際に行ってみよう!
1. いきなり見に行ってもわかるかな?
なるほど!はココをクリックここまでにも見てきたように、文楽では現代にも通じる人々の心の動きが表現されているし、3人の人にあやつられる人形の動きを見たり、太夫の声と三味線の音を耳にするだけでも楽しめるはずだよ。
ただ、文楽は江戸時代につくられた作品が多いので、場合によっては少しわかりづらい部分もあるんだ。だから、実際に見に行くときには、あらかじめ話の流れを調べておくといいよ。
2. こどもが観に行ってもいいの?
なるほど!はココをクリックもちろんだいじょうぶ。夏休みなどにはこども向けのお話を演じている劇場(げきじょう)もあるから、ぜひ調べてみよう。また国立文楽劇場や文化センターなどでは、こども向けに文楽の楽しみ方を教えてくれる教室なども開かれているので、こうしたものに参加すればますます文楽が身近に感じられるよ。
■国立文楽劇場
所在地:〒542-0073 大阪府大阪市中央区日本橋1-12-10
最寄り駅:[地下鉄]堺筋線・千日前線 日本橋駅 7番出口より徒歩1分
・文楽の鑑賞入門やイベントについては、人形浄瑠璃文楽座のホームページをチェックしよう。
3. 太夫さんの言葉が分からなくても平気?
なるほど!はココをクリック太夫が話す言葉は江戸時代の大阪弁なので、初めての人にはすんなりと理解するには、むずしいかも…。だけどだいじょうぶ。多くの劇場では太夫が話す言葉を解説するイヤホンガイドを貸し出してくれるから、初めての人でも、どんな意味の言葉を話しているか理解することができるよ。
4. 浄瑠璃と文楽ってどう違うの?
なるほど!はココをクリック文楽について調べてみると、浄瑠璃という言葉がたくさん出てくるよね。初めのページでも紹介(しょうかい)したけど、浄瑠璃というのは音楽とセリフでつくられたもので、オペラに近いような劇(げき)なんだ。それが人形劇と組み合わさり、はじめのうちは「人形浄瑠璃」と言われていたんだけど、人形浄瑠璃の1つの流派(りゅうは)である文楽座(ぶんらくざ)が大きな人気を博したことから、次第に人形浄瑠璃といえば文楽と言われるようになったんだ。
5. 人形つかいになりたい!
なるほど!はココをクリック文楽を見ていると「自分でも人形を動かしたい!」と思う人もいるんじゃないかな。実は文楽は、学校のような研修制度を設けていて、そこに合格すれば人形つかいや太夫になることができるんだ。その研修は国立文楽劇場が行っているもので、人形の動かし方や太夫の話し方、三味線のひき方など、多くのことを勉強していくんだよ。
研修を受けられるのは中学校を卒業していて23才までの男性だから、興味がある人は「文楽の技芸員」で調べてみよう。
(2018年3月時点の内容です)