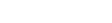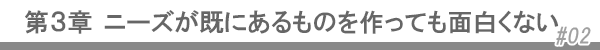>「第1章 出口の見えない“モヤモヤ期」はこちら
>「第2章 熱量があれば、実現する道はいくつもある」はこちら
メンタリングで事業プランをブラッシュアップ
数年ぶりに参加した起業チャレンジは、当時森脇が参加した頃よりも、大きくアップデートされていた。
これまで参加者は、アイデアに基づいた事業計画(ビジネスモデル、収支計画等)を独力で作り込み、審査を通過できるレベルまで整えなければならなかったため、ハードルが高く感じられており、応募数も伸び悩んでいた。
その課題を解消すべく起業に必要なスキルを付与し、事業計画策定を支援する仕組みを会社が整えていたのだ。
「かんでん起業チャレンジ制度」の現在の仕組みはこうだ。
これまで通り、自分で事業プランを立案して応募する方法に加え、「アイデア創出チャレンジ」という、プランではなくアイデアの状態で応募することができる場をつくった。そこで優秀なアイデアと認められると、次のステージ「一次審査」に進むことができる。
「アイデア創出チャレンジ」通過者、および起業チャレンジの参加者は、一次審査に向けてアイデアのブラッシュアップの時期が設けられ、「アクセラレーションプログラム」として、外部メンターによる事業アドバイスやメンタリングを受けることができる。
そして「一次審査」を通ると、事業FS(フィジビリティスタディ)として半年間の期間が設けられ、一定額の予算を使って事業化の検証を行うことができる。
その検証期間を経て「最終審査」を通過すると合格。提案者も出資し、グループ会社として法人化するという仕組みである。
2018年夏。
森脇が「アイデア創出チャレンジ」で提案した時のものは、まだまだアイデアレベルだった。「TRAPOL」という名前すら決まっていなかった。しかし、コンセプトへの共感によるものか、見事通過。森脇の他にも複数のアイデアが通過している。
そして「アイデア創出チャレンジ」通過後は、一次審査に向けて、「k-hack」を中心とする仲間と一緒に事業内容を詰めていった。
「アクセラレーションプログラム」のメンタリングも活用した。
メンターは19歳で起業し、現在はイノベーションコンサルタントとして数々の事業創出のメンタリングに関わっている山口高弘氏。
森脇は仲間と考えた「TRAPOL」の構想を話した。
山口氏は「面白い!」と話を聞いてくれつつも、どの市場で戦うのか? キャッシュポイントをどこにするのか? など、かなり具体的なアドバイスやヒントをくれた。
山口氏は今まで数々の事業を立ち上げてきた経験者。
経験者が語る言葉には説得力があり、森脇は山口氏が話すすべての内容に、真剣に耳を傾けた。こうして月数回程度のメンタリングを受け、事業プランをブラッシュアップしていった。
再び挑んだ起業チャレンジ
山口氏のアドバイスや仲間の協力もあり、なんとか事業計画ができあがった。
サービス名は、トランスポート(届ける)×トラベル(旅)で、「TRAPOL(トラポル)」に決めた。
2018年12月、「アイデア創出チャレンジ」から数ヶ月経ったある冬の日。
一次審査は会議室で行われた。
ひとり3分ほどのプレゼンテーションで、森脇の他にも20人程度の発表者がいた。
「なぜそれをやりたいのか?」など、審査員は、熱量やコアな価値の部分、そして事業化への本気度を見ていたように感じた。熱量に関しては、森脇は自信があった。
森脇が事業創出において一番大事にしている部分だからだ。
また「アイデアが面白い」という評価も多かった。
事業計画に動画を添えてプレゼンしたことで、リアリティも感じてもらえたのだろう。
その時の動画がこちら。
動画には、現地で森脇らが実際に経験したことをふんだんに盛り込んだ。
あえて、現地の様子をそのまま動画にした。
リアリティを大事にしたかったからだ。
一方、審査員から「本当にニーズはあるのか?」という質問もあがった。
それも当然、比較できるようなサービスはまだ世の中には存在しない。
そのためニーズが見えてこない。
森脇は答える。
「ニーズが既にあるものを作っても面白くない。世の中にない新しい価値を出していきたい。ニーズが見えているなら、すでに遅いと思っている」
そのメッセージを強く伝えた。
この時森脇は、仮に一次審査に受からなくても、他の手段を使って実現しよう、と事業化への強い意志を持って臨んでいた。
きっとその情熱も伝わったのだろう。
見事に一次審査を通過した。
残ったのは、森脇を含めて3人だった。
皆、「k-hack」でつながりのある仲間だった。

森脇の想いに共感し、サポートしてくれた仲間との1枚。
一番左が森脇
すべてが手探りのモニター検証
一次審査を通過したのち、事業FSフェーズに入った。
所属部署となった経営企画室のイノベーション推進グループより一定額の予算がつき、その予算を使って、半年間、事業化の検証を行う。その予算の使い道も自分の裁量で決められる。
検証においては「TRAPOL」に共感した仲間が、「ぜひ一緒に、世の中に出したい!」と言って手伝ってくれた。
森脇はまずは「TRAPOL」のコンセプトやサービスを伝えるためのオフィシャルサイトを作った。ロゴもできた。
同時に、モニター検証も進めていった。
この半年間のうちにできるだけ多くの体験を提供し、生の声を拾うこと。
顧客となり得る世代とのつながりや関連機関との関係構築を行い、事業化の目処を立てることに注力した。
「TRAPOL」のメインターゲットは、主に20代のミレニアル世代。
旅が好きで異文化交流に関心がある層を想定した。
そういう層の人たちがどういうところに集まっているか? それを考えたときに、シェアハウスなどで暮らしている人たちが思い浮かんだ。森脇はさっそくそういうコミュニティに顔を出し、友達を作り、興味がありそうな子を紹介してもらうなど、ネットワークを広げていった。
森脇の読みは当たっていた。
声をかけた多くの人が興味を持ち、モニターをしたいと手を挙げてくれた。
また「TRAPOL」の仲間のひとりが、ベトナムの旅行代理店とつながりがあったため、旅行業者との提携もスムーズに進めることができた。
また現地のサプライヤー、つまり旅行者と交流してくれるベトナムの人たちも、現地の国際交流団体等との連携により得ることが出来た。
ベトナムに積極的に出向き、結果、400名程度のサプライヤーを確保する。
旅行者、旅行代理店、そしてサプライヤーの獲得、全てが同時進行ではあったが、それらが揃ったことで、モニター検証ができる状況が整った。
モニター旅行者とサプライヤーのマッチングに関しては、まずはサプライヤーに欲しいお土産を登録してもらい、モニターはその中から選んで届けるという方法を取った。
性格診断なども取り入れながら、どういうマッチングが良いのか、手探りで試す。
また、ローカルな体験に関しても、どういうアクティビティが喜ばれるか? どういう場所がいいのか? 家庭料理を食べさせてくれるなどの方が嬉しいのか? など、こちらもモニターからアンケートを取るなど、検証を進めた。
その結果、モニターからは思わぬ反響があった……。
最終章へ続く