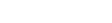>「第1章 出口の見えない“モヤモヤ期」はこちら
「k-hack」から生まれたプロジェクト
「k-hack」は、運営を始めて間もなくすると、徐々に内部でチームができ、それぞれが自走するようになっていった。
「○○をやりたい!」という人に賛同した仲間が集まってチームになったり、数人でアイデアを創出するようなグループが生まれたり、ケースは様々。
本業ではないため、割ける時間は限られているものの、「eチャレンジ制度(※2)」のうちの一つである「デュアルワークチャレンジ(※3)」を活用するなどして、熱意を持った人々が動き出すようになった。
まさに森脇が求めていたような状態になってきていた。
例えば2018年秋に実施された「黒部峡谷鉄道の謎解きゲーム」の企画。
これは黒部峡谷のトロッコ列車を盛り上げるために、経営層が若手の意見を聞いてみたらと橋渡しをしたことをきっかけに、「k-hack」のメンバーらが企画したもの。1年がかりで取り組んだ結果、関連部門から予算を獲得し、実施に至った。
(※運用されている特設サイトはこちら)
とはいえ、全員が全員、仲間を見つけられるわけではない。
森脇は、「こんなことをしたい」という社員のビジョンを聞き、合いそうな人をつなげたりもした。また財津が週1でメルマガを書いて、動いているプロジェクトの紹介をしたり、外部との交流の場を設けて参加を促進するなど、熱量はあるものの、やりたいことが明確になっていないメンバー等に向け、きっかけを提供するなども積極的に行われた。
(※2)個々の自律的なキャリア形成を支援し、多様なキャリアフィールドにチャレンジできる社内公募型の仕組み
(※3)多様な業務経験による個人のさらなる成長を目的として、本来の従事業務に加え、就業時間の一部(20%程度を目安)を用いて他業務(特定のプロジェクト業務等)にも従事する仕組み
実現する手段はいくつもある
「k-hack」を作ったことで、森脇の中でも大きな変化があった。
それは、自分の中で“言い訳”をしなくなったことだ。
正直、起業チャレンジを利用した時は「(制度の)環境が整っていない、制度が不十分」など、できない自分に言い訳を作っていた。しかし「k-hack」を通じて、森脇自身も仲間と一緒に新規事業の企画をしたり、様々なトライアルを試みる中で、わかったことがある。
それは、何よりも大事なのは環境でも制度でもなく、本人の“熱量”だということ。
自分を信じて「何としても実現したい!」という熱量こそが、仲間を呼び、環境を変え、実現性を高めていくということを知った。
実現するための手段は何でもいい。
起業チャレンジを利用するのもひとつだが、別の部門の予算で実現するとか、外部との連動で予算を獲得するなど、手段はいろいろあることもわかった。
熱量があれば、諦めない限り、実現する道はいくつも用意されている。
そこには、できないという言い訳は通用しない。
ベトナムで生まれた「TRAPOL」の原点
「TRAPOL」の構想は、「k-hack」を立ち上げてすぐの頃から始まっていた。
「k-hack」のメンバーである、ベトナム国籍のクアンさんの想いからだった。
「ベトナムを絡めたビジネスをやりたい!」
彼の熱意もあり、森脇は「じゃあ、一緒に考えよう」と、まずは「k-hack」のメンバーらと一緒に、ベトナムに行ってみることにした。
現地では想像以上の歓迎が森脇たちを待っていた。
迎えてくれたベトナムの人々は、日本人が好き、日本の文化も製品も大好きという、親日の人ばかり。森脇が日本で購入した、どこにでもあるありふれた物でさえも、お土産に渡したらすごく喜んでくれた。
そんな森脇たちを、現地の人たちは、地元の人が遊びに行くような場所に連れて行ってくれた。
それは、初めて目にするローカルな場所。
今までにない体験ばかりだった。
森脇はそれらのディープな体験によって、(現地の方々とは)その日会ったばかりにもかかわらず、深い関係が築けたような気がした。
そして、「また絶対に会いに来る」直感的にそう思った。
その土地にしかない価値に触れ、それを現地の方々と共に体験をする。
そういった国や文化を超えたつながりに森脇は心震えた。
「この経験をもっと多くの人に提供できないか……」
この経験をきっかけに、森脇は事業化を検討し始めることになる。
便利さによって失われたものを取り戻す
その後も定期的にベトナムを訪れては、現地の人々と交流を行った森脇。
その際、日本のお土産は欠かさなかった。
彼らがとても喜んでくれるからだ。
現地にお土産を届けに行く、そして相手の喜ぶ顔を見る。
森脇は、その“わざわざ会いに行く”というところに、大きな価値を感じていた。
今の時代、SNS やAIの技術により、オンラインでいつでもどこでもつながることができる。これからの時代は、家から出なくても人々が交流し合い、見たい風景を楽しめる時代になるかもしれない。しかしそれら便利さによって失われたものもある。
それは肌と肌の触れ合いだったり、自分の足を使って探求する喜びだったり、そういった本来人間が持っている喜び。
———大学生の頃、モリ突きに夢中だった森脇。
モリ一本だけを持ち、無人島で生活をしたこともある。
そこで感じたのは、人間の本能や、文明社会に支配されない感情。
文明の発達で便利にはなったが、それゆえ、見えなくなっている価値がいっぱいあることに気づいた。
「人間が本来の姿に回帰できる価値を世の中に出したい」
森脇は今回のベトナムでの体験を通じて、そこに自分の想いがあることを、改めて知ることになる。

ベトナムで現地の人々とディープな経験をする森脇。
中央左から2番目が森脇
「誰に売るのか」よりも「自分が何を作りたいか」
「このベトナムでの体験をどうしたら事業化できるか」
森脇は「k-hack」のメンバーらと考えるようになった。
そして「次の起業チャレンジに出してみたいね」と盛り上がる。
「TRAPOL」を事業化するにあたり、森脇が大事にしたのは、
「まだ誰も感じたことがない新しい価値をつくる、新しい体験をつくる」
ということだった。
ビジネスの視点で発想すると、どうしても「自分が何を作りたいか」よりも、「誰に売るのか」「どう稼ぐか」から考えてしまう。
収支予測はしやすいが、それでは、どこかに転がっているサービスになってしまう。
自分がやる意義も情熱も生まれない。
それよりも、「何をつくりたいか? どういう価値を世の中に出したいのか?」
そこに時間をかけて、自分の中のコアを具現化していくことが重要だと考えた。
———そして2018年。
起業チャレンジに応募することになる。
第3章へ続く