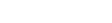「自分がやらねば……! あの頃は無我夢中だった」
そう語るのは、今回の主人公、株式会社気象工学研究所 代表取締役社長 小久保鉄也(こくぼてつや)。
小久保は1984年に関西電力に入社。
本社の土木建築部門を経て、32歳の時に北陸支社の副長となり、黒部ダムの管理業務を行う。その4年後の1995年、小久保が36歳、本店副長の時、黒部川で記録的な大水害を経験。
その水害を機に、翌年には黒部川降雨予測研究会を立ち上げた。
その後、ここでの研究成果を事業化すべく、「かんでん起業チャレンジ制度(※1)」を活用して起業を目指す。そして2004年9月に、株式会社気象工学研究所を設立。
社員4名、家賃10万円の老朽ビルの一室からスタートした気象工学研究所は、現在では社員45名、売上は6億7千万円(うち70%が関電グループ外)、そして業界第4位にまで拡大成長している。
創業して今年で15年。
小久保が走り続けてきた背景には、ある想いがあった……。
「関西電力の一社員がいかにして起業したのか?」
情熱溢れるストーリーをお楽しみください。
(※1)「グループの事業領域の拡大」「競争時代にふさわしい人材の育成と風土づくり」をねらいに、平成10年に創設した社内ベンチャー制度。現在は、年1回から年2回に機会を増やし、その可能性を広げている。
黒部ダムで経験した1度目の危機感
———1995年7月。
停滞した梅雨前線により、北陸は記録的な豪雨に見舞われていた。
富山県東部を流れる黒部川上流域では氾濫が起こり、黒部川の発電所群は停止。
黒部峡谷鉄道も土砂災害により大きな被害が出ていた。
その頃、発電所を保守運用していた作業員らも、川筋から脱出する術がなく、取り残されてしまっていた。自衛隊と県警のヘリによって、作業員は無事に救助されたものの、黒部ダムが完成して以来の大災害に、皆が固唾を飲んで見守った。
死傷者ゼロを安堵するとともに、この時、本店でダム管理の副長をしていた、当時36歳だった小久保鉄也は、ひとり大きな危機感を感じていた。
「気象情報を把握していて、しかも長年黒部川で従事してきた作業員達だったにも関わらず、救助を要することになるとは、これでいいのか……」
現状の知り得る気象情報や、作業員の経験則を以ってしても事前に防げなかったこと、今後同じような気象が訪れた時にどうすれば未然に防ぐことができるのか、それが見えないことに大きな不安を感じた。
「何とかしなければ……」
そう考えた小久保は、翌年、大学の研究者や外部の有識者を集め、黒部川降雨予測研究会を立ち上げた。この研究会こそが、株式会社気象工学研究所の起点になっている。
人と同じでは面白くない
小久保が、黒部ダムに出会ったのは17歳の頃。
その迫力に感銘を受けた。
その時の感動は今でも覚えている。
その影響もあって、高校卒業後は大学の土木工学科に入学。
「自分も(黒部ダムを建設するような)大きな仕事がしたい」そう思った。
その後、関西電力に入社した。
小久保は、学生時代はリーダーシップをとるようなタイプではなかった。
クラスのリーダーやクラブのキャプテンすら経験がない。
引っ張っていくというよりも、「人と同じようなことをやっていては全然面白くない」と、どこか、人とは違うところを見ていた。
小久保の幼少期や学生時代は、ちょうど高度経済成長期。
大量生産・大量消費で、皆が一斉に同じ方向に向かっていくことが求められた、今から見ればまさに「非ダイバーシティ」の時代。
そんな社会構造に、漠然と「面白くない」と感じていた。
「戦前や戦後のドサクサの時代の方が面白かっただろうな」と想いをめぐらすこともあった。
皆が自由な発想で事業を興していた戦前や戦後復興の時代にどこか憧れていた。
とはいえ、真摯でまっすぐな小久保は、関西電力入社後は、黙々と仕事に邁進した。
そして原子力の建設現場、本店での業務を経て、32歳の時に北陸支社の土木建築課の副長に就任。10代の頃に出会った黒部ダムに直接携わるようになり、小久保は感慨深い想いで向き合った。
1963年に完成した黒部ダムはちょうど30年を迎える節目でもあり、小久保は「黒部ダム30年史」の編纂プロジェクトを立ち上げるなど、より黒部ダムへの愛が深まっていた。
そして36歳の時。
あの大水害を経験することになる。
事前に得られる気象情報に限界があり、未然に防げなかったことに危機感を覚えた小久保は翌年、自ら黒部川降雨予測研究会を立ち上げた。
社内はもちろん、京都大学始め外部の専門家に自ら声をかけて回り、数名のメンバーで研究会を発足した。ここでの活動が、気象工学研究所の技術研究のはじまりであり、この時のメンバーが、後に気象工学研究所のコアメンバーとなる。
関西電力で「大きな仕事がしたい」と夢を持って入社した小久保は、36歳の水害を経験するまで、順風満帆な人生だった。仕事に邁進し、着々とポジションを上げた。パリ事務所駐在時代には視野を広げることもできた。「このまま社内で上を目指したい」、そう思いながら会社員生活を送っていた。
しかし、もともと「皆と同じでは面白くない」という感覚を持っていた小久保。
「36歳で身を以って体験した危機感によって、何かが目覚めたのかもしれない」
そう振り返る。

パリ事務所駐在時代の1枚(右側が小久保)
俺たちの役目はこれで終わるのか……
ほぼ同じくして、小久保が所属している土木建築部門でも大きな危機感が生まれていた。
それは、「もう大きな発電所はいらないのでは?そうなったら土木建築部門はいらなくなる?」という危機感だった。
もともと土木建築部門は日本最大規模の黒部ダムを始め、数々のダムを何も知見がないところから造り上げたプロ集団。しかしそれまで続いていた建設ラッシュもひと段落し、ひとつの時代が終わろうとしていた。
「俺たちの役目はこれで終わるのか……」
多くの先輩社員が他部門や社外へと去っていった。
強い危機感を感じていた。
今まで培ったノウハウを活用して海外に新規事業を展開するか、それとも何か異なる事業を考えるか……という状況に迫られていた。
結果、海外へ目を向けることにした。
この時、北陸支社の土木建築課長になっていた小久保だったが、その2年後には本店に戻り、新規事業として海外水力事業を行うことになる。
最近運開したインドネシアのラジャマンダラ水力の発掘にも、「これはチャンス、絶対やらねば」との強い使命感から、小久保は全力を尽くした。
小久保には、このまま海外事業を推進していくリーダーになる、という選択肢もあった。
しかし同年開かれた「フロンティアチャレンジ研修(※2)」で、黒部川の水害以来、研究を重ねていた気象予測の研究を「何とか事業化したい!」と、気象予測の事業化を推進していく道を選ぶ。気候変動により豪雨災害はますます社会の脅威となるだろう。これを経験した関西電力は先駆的に貢献すべきではないか。黒部ダムが日本のダム技術をけん引し、電力の安定供給に貢献したように……との想いがあった。
(※2)…各部門から推薦された部長クラスを対象にした、新規事業プランを検討する社内研修。
本気でやるつもりなの?
小久保は43歳になっていた。
「フロンティアチャレンジ研修」は、4つの新規事業案をベースに、意見を深めたりフィジビリティを探るなどを、新規事業を創出し経営するスキルを高めることを目的とした、半年に渡る研修会である。小久保含め、20名ほどが参加した。
小久保は気象ビジネスを起案し、熱弁をふるった。
しかし他の参加者にとってこれはあくまで研修。「小久保さん、本気でやるつもりなの?」と言われてしまう。
小久保は本気だった。
もちろん、今まで携わってきた海外水力の新規事業も気がかりではある。
しかし、海外水力の事業は、仮に自分がやらなくても誰かが推進してくれる。
では気象ビジネスはどうか?世の中の需要やビジネスチャンスが見えているにも関わらず、自分がやらない限り、誰も実行する状況ではなかった。
この時小久保は、以前上司が言っていたある言葉を思い出していた。
「やるべき仕事があって、まわりを見て誰もやりそうにないなら、それは自分の仕事」
今はまさにその状況。
「だったら自分がやるしかない……」
ここでも使命感に駆り立てられていた。
この想いは、のちに小久保が後輩の起業家らに伝えるようになった、「私がやらねば、誰がやる」の精神につながっている。
その熱意が通じたのか、ある役員の配慮により、小久保はグループ経営推進本部への異動が決まった。気象工学の事業化に向けて本格的に検討が進められることになったのだ。
———しかし。
いざ事業化となると、新規事業領域であり、且つ、リスク面などの考慮もあってか、社内では全然進まなかった。小久保がどんなに推進しても組織は動かなかった。
誰も意思決定できない状態にあった。
「社内でこのままグダグダしていては機会損失になる、勿体ない。誰かが責任を負わないと、何も動かない……」
そこで小久保は、「かんでん起業チャレンジ制度」を活用して、起業する決意をした。
目の前に自分にやるべきことがあって、それができる好条件の機会がある、気象工学はまさにその環境にある。
「だったらやるしかない」
小久保は一切ブレなかった。
第2章へ続く