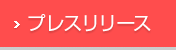大飯発電所において、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、1,2号機および3,4号機の復水処理装置再生排水処理設備※1(以下「ETA排水処理設備」という)からの排出ガスと排水の試料採取(1回/年の頻度)を行いました。
その結果、11月29日、分析会社より、3,4号機ETA排水処理設備からの排出ガス中に基準値(5ng-TEQ/m3)を上回るダイオキシンが検出(8.9ng-TEQ/m3)されたとの報告(速報)を受け、即時、ETA排水処理設備の運転を停止するとともに、同設備周辺をロープで区画し、立ち入り制限を行いました。
また、同設備の運転状況等を確認のうえ、11月30日、関係機関に報告しました。
3,4号機ETA排水処理設備に関しては、当面の使用を停止し、原因を究明後、必要に応じて設備の改善等を実施することとしました。また、1,2号機の同設備についてダイオキシン濃度を測定するとともに、放水口付近の海域や敷地境界付近の大気、および敷地内の土壌におけるダイオキシン濃度の測定も行い、基準値を十分下回ることを確認しました。
| |
※1 |
: |
復水処理装置再生排水処理設備(ETA排水処理設備):
プラント運転中に、2次系統水中の不純物を除去する復水処理装置の、樹脂を再生する際に発生した廃液を焼却処理する設備。 |
[平成17年12月1日、平成18年1月19日 お知らせ済]
ダイオキシン発生の原因を調査するため、当該のETA排水処理設備の分解・点検や系統における樹脂の混入状況等の調査を実施しました。
その結果、廃液噴霧ノズルが腐食、破損していること、また、ETA排水処理設備の系統に樹脂が混入していることが分かりました。これらのことから、ダイオキシンの発生メカニズムは、以下のとおりと推定されました。
<ダイオキシンの発生メカニズム>
| ・ |
廃液噴霧ノズル※2が腐食し、ノズル噴霧穴が拡大・変形した。 |
| ・ |
ノズル噴霧角度が変わり、燃焼炉内の耐火材と接触することなどにより廃液が液状に滴下する状態になった。 |
| ・ |
廃液の噴霧状態が不良になったことから混入した樹脂が不完全燃焼し、ダイオキシンが発生した。 |
| |
※2 |
: |
廃液噴霧ノズル
廃液と空気をまじり合わせ、燃焼炉内に送り出す先端部分。
廃液に空気を注入させる「ミキシングコア」、廃液と空気をまじり合わせる空間をつくる「ミキシングノズル」、燃焼炉内に噴霧する先端部の「コーンチップ」から構成されている。
|
このため、以下のとおり対策を実施します。
<対 策>
 |
廃液噴霧ノズルを新品に取り替える。
(腐食によって穴が拡大したミキシングコアについては、材質をジルコニウムから耐酸腐食に優れたタンタル(Ta)に変更する。)
|
 |
廃液噴霧ノズルは、定期点検毎に分解点検を行うこととし、廃液噴霧ノズル先端部のコーンチップは毎回取り替える。 |
 |
廃液噴霧ノズルの取り付け位置を焼却炉内側へ移動し、ノズル噴霧角度が変わっても耐火材と接触しないよう、寸法余裕を確保する。 |
 |
ETA排水処理設備への樹脂の混入を防止するため、復水処理装置出口ラインにストレーナを設置する。 |
 |
燃焼状態の監視機能を強化するため、廃液噴霧空気圧力計、および流量計を設置する。 |
なお、上記    の対策工事については、本年6月下旬目途で完了する予定です。 の対策工事については、本年6月下旬目途で完了する予定です。
また、同種設備である大飯1,2号機および高浜3,4号機(上記   については既に実施済み)についても同様の対策を実施します。 については既に実施済み)についても同様の対策を実施します。
以上の内容については、3月31日に関係機関に報告しました。
|
 2006
2006