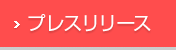プレスリリース
 2000
2000
2000年2月21日
世界初の超低損失12.3kV-SiCダイオードを開発
- ○アクティブフィルタ
- 電力変換器等から発生する高周波電流に対し、逆位相の高周波電流を能動的に発生させ系統に注入することで、これを抑制するフィルター。
- ○インバータ装置
- 直流電力を交流電力に変換する電力変換器。
- ○SiCウェーハ
- 一般に、ウェハーとは薄板のことを言い、SiCウェハーとはSiCの薄板のことを示す。SiC基板と同義。半導体素子や集積回路を作り込む基板として用いられる。
- ○SVG(Static Var Generator)
- SVGの中に組み込まれたインバータの出力電圧を高速に制御して系統電圧の変動を改善する装置。以下のような適用効果が考えられる。
- 電鉄や圧延機などの変動負荷によって発生する電圧変動の抑制に効果がある。
- 長距離交流送電線では、SVGを送電線の途中に設置することで送電電力を増加させることができる。
- ○エピタキシャル膜
- 単結晶半導体基板上に単結晶の薄膜を成長させる技術をエピタキシャル成長と言い、この技術で成長させた薄膜をエピタキシャル膜と呼ぶ。例えば、n型半導体の単結晶基板上にp型半導体の単結晶薄膜を成長させるとpn接合を作ることができる。エピタキシャル成長させる方法には、材料ガスを流した反応炉内で成長させる気相成長法などがある。
- ○オン電圧
- 電圧を印加することでオンし電流が流れる半導体素子において、素子がオンして、ある電流値が得られるために必要な電圧。
この値が小さいほど、電流が流れるときのロスが小さい。 - ○系統安定化装置
- 電力系統を安定化する方法にはいくつかあるが、近年パワーエレクトロニクス技術の発展により、半導体を用いた系統安定化装置が用いられるようになった。以下のような種類がある。
 SVC(SVGを含む):(上記説明)
SVC(SVGを含む):(上記説明)
 TCSC:
TCSC:コンデンサにサイリスタと呼ばれる半導体素子で作ったサイリスタスイッチを取り付けて、送電線の送電能力を調整するもの。
 UPFC:
UPFC:自励式インバータ(SVGの中に組み込まれているものと同じもの)を2台組み合わせて、電力を自由に制御できるもの。
 可変速揚水発電:
可変速揚水発電:一日の電気の使われ方は昼と夜とでは大きな差がある。供給(発電)と需要(負荷)が同時に行われる電力は 両者のバランスが大事である。需要が供給を上回ると周波数が低下し、逆に供給が需要を上回ると周波数が上昇する。このため周波数を一定に保つように発電力を調整する。この調整を自動周波数制御(AFC)といい、AFC運転が可能な揚水発電所のこと。 - ○系統間連系装置
- 2つ以上の電力系統を直流で連系する装置。電力系統の間が離れていれば、直流送電となり、隣接していればBTBとなる。日本国内で用いられている連系装置はすべてサイリスタと呼ばれる半導体素子が用いられているが、近年自励式半導体素子と呼ばれる新しいタイプの半導体素子を用いた装置の開発も進んでいる。
- ○限流器
- 短絡時に回路に流れる故障電流を抑制する機器。通常は低抵抗であるが、故障電流を検出すると、これを抑制するために高抵抗に切り替わる。
- ○サイリスタ
- ゲートと呼ばれる制御端子からの制御信号によってオフ状態からオン状態へ切り換えができるスイッチング半導体素子。トランジスタに比べて高電圧、大電流の領域で優れた特性を示し、大容量の素子は電力変換装置などに用いられている。
- ○シリコンカーバイド(SiC)
- シリコンに比べ高電圧、高周波、高温エレクトロニクスへの応用にとって非常に優れた性質を持つ次世代の半導体材料。従来のシリコンを用いたパワートランジスタやサイリスタ、整流器がより有利なシリコンカーバイドを用いた半導体素子に置き換えられる可能性がある。
- ○スイッチング損失
- スイッチング素子を高周波で使用する場合に、定常損失以外に考慮する必要が出てくるスイッチング時の損失。スイッチング時(ターンオン時、ターンオフ時)に変化する電流と電圧の積で表す。
- ○接合終端技術
- 電力用の半導体素子は高い電圧をかけても壊れずに動作することが求められる。通常、素子に高い電圧をかけるとpn接合の端部に高電界が発生する。この電界を緩和する技術のことを接合終端技術という。
- ○ダイオード
- 半導体にはプラスの電荷を持った正孔により電気を運ぶようにしたp型半導体と、マイナスの電荷を持った電子により電気を運ぶようにしたn型半導体がある。ダイオードは、p型半導体とn型半導体を接合させたもので、順方向(順方向:電圧のかけ方はp型に+側、n型に-側とする)には電気が流れるが、逆方向には流れない整流作用がある。また、金属と半導体を接合させたダイオードもあり、同じように整流作用を持つ。ダイオードは交流を直流に変換する整流装置などに用いられる。
- ○デバイス
- 素子のこと。独自の機能を持つ最小単位であって、単なる部品ではないもの。例えば、半導体デバイスは半導体素子の意味。
- ○トランジスタ
- 半導体で作られた電気信号を増幅する素子で、スイッチング素子としても利用でき、集積回路の基本構成要素として用いられる。その応用はコンピュータをはじめとする情報産業、通信機器、音響機器、家庭電化製品、産業用制御機器などにおよび、電子産業を支える重要な素子である。
- ○パワー半導体
- パソコン用の半導体に比べると大容量(使用する電圧、電流が大きい)の半導体であり、約12V以上の電圧または0.1A以上の電流で動作するものを総称してパワー半導体と呼んでいる。ダイオード、パワートランジスタ、サイリスタなど多数の種類があり、電力分野や鉄道、自動車、家電製品等に広く使用されている。
- ○BTB(back-to-back)
- 半導体を用いた変換器を2つ背中合わせに接続した設備で、交流をいったん直流に変換してまた交流に戻す。電力系統が巨大で莫大な容量になれば、故障時の電流は容量の増加とともに増大するので、短絡故障時の故障電流を遮断する機器が莫大なものとなる。そこで電力系統を分割して独立させ、短絡電流を減少する方法を検討する必要がある。
BTBを電力設備に適用すると、短絡容量を増大させずに、有効電力だけの融通が簡単にできる。BTBには2種類の方式があり、1つは系統間連系であり、もう一つは周波数変換である。系統間連系は同一周波数の交流系統を連系するもので、日本では中部電力と北陸電力の間に設置された南福光変換所が相当する。周波数変換は異なる周波数を持つ交流系統を連系するもので、日本では中部電力と東京電力の間に設置されている佐久間変換所や新信濃変電所がある。 - ○リアクトル
- 交流回路に対して、抵抗を与えることを目的とした機器。通常の抵抗と異なる点は、交流回路においては電流が流れても電力を消費しない。
- ○リカバリー時間
- 整流器やスイッチング素子において、電源電圧をオン方向またはオフ方向に急峻なステップ状に変化させた時、出力電流が規定値に戻るまでの時間。
この値が小さいほど、素子の高速化、高周波化が可能になる。
以 上