事業所・関連施設
 原子力事業本部
原子力事業本部
越前若狭探訪
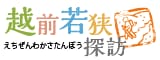



▼若狭の夏を代表する大イベント「スーパー大火勢」

「炎の太鼓」演奏
松明行列

▲花火と音のページェント(音楽連動型の花火)
平成7年(1995)に始まり、毎年6万人以上の観客を迎え若狭の夏を代表する大イベントとなった「若狭おおいのスーパー大火勢」。今年は8月4日(土)に、うみんぴあ大飯で開催される。
その見どころは、燃え盛る巨大松明(たいまつ)(仏像の光背のような形に組まれたもので高さ約20m、重さ約1t)を、総勢60人の若衆が火の粉を浴びながら回転させるシーン。炎の輪が渦巻き、大量の火の粉をまき散らす。このスーパー大火勢のルーツは、同町の佐分利(さぶり)地区で今も続く伝統行事の大火勢にある。
福井県無形民俗文化財に指定されている福谷(ふくたに)の大火勢は、火勢山(かせやま)の山頂で行われる火祭り。以前は8月23・24日に行われていたが、若者の減少で、現在は旧盆の帰省に合わせて8月14・15日の2晩、福谷区と大火勢保存会によって実施されている。高さ約15mの柱に5本の横木をつけ、端に茅(かや)などを縛った大火勢。これを男衆が回転させては倒し、また引き起こして回す。回転とともに火は燃え盛り、倒したときに巻き上がる火の粉はすさまじい。
福谷の大火勢は、愛宕(あたご)信仰に基づく火祭りで、江戸時代に始まり300年以上続くという。戦時中も嵐に見舞われた年も、火災鎮護と五穀豊穣を祈って欠かさず行われてきた。区の各家が寄り合う愛宕講で毎年、代参(だいさん)者3人をくじ引きにより選び、京都市嵯峨(さが)の愛宕山山頂に鎮座する愛宕神社に詣(もう)で、お祓(はら)いを受けたマッチを持ち帰る。その火を提灯(ちょうちん)や大火勢の火種にしている。
愛宕信仰は、愛宕神社を発祥とする火伏せを主とした信仰で、近世には愛宕山伏(やまぶし)によって全国に広められた。日本全国で「愛宕」を社名につける神社は、約800にのぼるという。各地で愛宕講がつくられ、愛宕山へ代参者を送って火伏せの札などを受けてくるほか、火祭りをする所も多い。
こうした歴史をベースに、町民参加型のイベントとして平成の時代に誕生した「若狭おおいのスーパー大火勢」。今年で第24回を迎え、一歩ずつ着実に"新しい伝統"を積み重ねている。


若狭おおいのスーパー大火勢
2018年は8月4日(土)
うみんぴあ大飯で開催
詳しくはコチラ
【写真提供】おおい町
【参考文献】大飯町誌(大飯町・平成元年発行)、ふるさと百話集上巻(山口利夫編著・平成9年発行)、福井県無形民俗文化財保護協議会20周年記念誌(平成9年発行)