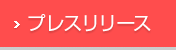事 象
および
対 策 等 |
第19回定期検査中の平成22年4月16日、化学体積制御系統*1の体積制御タンク*2から充てん/高圧注入ポンプ*3までの配管に水を張ったのち、水張りした配管の最上部にある弁を開き、配管内の空気を換気ダクトおよび体積制御タンクの気相部に抜く作業(以下「空気抜き操作」という)を行ったところ、15時44分に「4−1次系建屋漏水」警報*4が発信しました。
警報が発信した場所を確認したところ、体積制御タンク室内での漏えいであることが確認されたことから、直ちに現場確認を行った結果、床面に水溜り(約100cm×約10cm×深さ約0.5cm)があり、漏水検知器が設置されている排水口の目皿に水が流入した形跡があることを確認しました。また、水溜りの上方にある、配管から排出された空気を換気ダクトに導く空気抜き配管の先端が濡れていることが確認されました。
漏えい水量は、水溜まり(約0.5リットル)と目皿へ流入した水量(約2リットル)の合計約2.5リットルであり、放射能量は約8.3×104Bqと評価しました(法令に基づく国への報告基準は3.7×106Bq以上)。
水張り操作は、水源である燃料取替用水タンクの連絡弁を開き、タンクの水位差による圧力で系統に水を張ったのち、連絡弁を閉じます。この時、配管内の空気は水圧により圧縮された状態となります。その後、水張りした配管の最上部にある弁を開けて、配管内の空気を換気ダクトと体積制御タンクの気相部に抜く作業を行います。これら一連の操作は、今回と過去の定期検査時とでは同じでしたが、詳細に調査した結果、今回は、水張りに使用した燃料取替用水タンクの水位が高かったため、水張り後の配管内の水圧が高くなり、配管内の空気の圧力も高かったことがわかりました。また、空気の圧力が高い状態で空気抜き操作を行うと、配管内の空気が膨張し、配管内の水を空気抜き配管の先端まで押し上げる可能性があることがわかりました。
水漏れの原因は、水張り時に水源である燃料取替用水タンクの水位が高かったことにより、配管内に溜まっていた空気の圧力が高かったため、空気抜き操作を行った際、膨張した空気が系統内の水を押し上げ、空気抜き配管の先端から漏れたものと推定しました。
対策として、今後は、空気抜き操作の際は、空気抜き配管の弁を閉止し、体積制御タンクへ、空気を逃がすように、操作手順を変更します。
また、操作手順書作成の際の検討不足が今回の事象の背景にあると考えていることから、漏えい防止や労働災害防止の観点で、系統状態(系統内の圧力等)の変化を伴うような操作の影響について再評価を行い、必要に応じて操作手順を見直すこととしました。
本事象による環境への放射能の影響はありません。
- *1 化学体積制御系統:原子炉冷却系統から1次冷却材の一部を抽出し浄化したのち、保有水量やほう素濃度等を調整して、原子炉冷却系統に1次冷却材を充てんする系統。
- *2 体積制御タンク:原子炉容器や配管内の1次冷却材の量を調整するためのタンク。運転中は、気相部を水素に置換している。
- *3 充てん/高圧注入ポンプ: 原子炉の1次冷却材系統から1次冷却材を抽出し、浄化やホウ素濃度の調整等を行ったのち、再び1次冷却材系統に戻すためのポンプ。
- *4 「4−1次系建屋漏水」警報:管理区域内(格納容器内を除く)の各室内で、漏水を検知した際に、中央制御室に警報を発信する。どの漏えい検知器からの発信かは中央制御室内にある1次系補機室内の1次系補機操作盤で確認できる。
|
 2010
2010