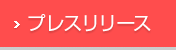プレスリリース
 2004
2004
2004年9月18日
美浜発電所3号機2次系配管破損事故に係る第2グループ(美浜発電所1号機、高浜発電所1号機、大飯発電所2号機)および定期検査中プラント(高浜発電所4号機、大飯発電所3号機)の点検結果等について
1.件 名
美浜発電所3号機 2次系配管破損事故について
2.現 況
(1)事故に関する評価
 原子炉に対する影響
原子炉に対する影響- 美浜発電所原子炉設置変更許可申請書(平成6年3月9日許可)において、給水系配管に破断が生じ、2次冷却材が喪失し、原子炉の冷却能力が低下する事故として「主給水管破断」を想定している。
「主給水管破断」事故では、主給水管の逆止弁とSGの間の配管破断による破断口を通じてのSG器内水の放出、外部電源の喪失による1次冷却材ポンプの停止等を仮定しているのに対して、今回の事故においては、主給水管の逆止弁より更に上流側の復水管の脱気器入口での破損であったことからSG器内水の放出はなく、1次冷却材ポンプも停止しなかったこと等から、安全解析の評価結果の範囲内であり、原子炉の冷却は正常に行われ、原子炉への影響はなかった。なお、念のため、プラント挙動シミュレーションにより、実際のプラント挙動との比較を実施する。  復水流量の変動及び流出量
復水流量の変動及び流出量
- 通常A・Bの2系統で脱気器へ流れる復水流量は、15時23分から破口が認められたA系が増加、B系が急激に低下している。その後、B系流量は15時24分以降「0ton/h」となっており、脱気器水位が15時25分頃から急激に低下している。
復水配管からの流出量は、2次系純水タンクからの補給水(約565ton)及び系統保有水減少分(約320ton)から、合計で約885tonの復水がA系の破口部から流出したと評価される。
(2)原因調査
 配管破損メカニズムに関する調査
配管破損メカニズムに関する調査- 今回の事故については、第4回事故調査委員会にて原子力安全・保安院から報告された資料等に基づけば、現在までに判明した事実は以下のとおりである。
a.現場調査
(a)外観観察
A系配管(破損配管)は頂上部近傍で軸方向及び周方向に大きく、破口している。破口幅は、軸方向に約515mm、周方向に約930mmであった。
下流側に向かって、右方向に進展したき裂は、上流側、下流側ともに溶接部直近で停止し、左方向に進展したき裂は、管底部近傍で停止している。
(b)肉厚測定
A系配管(破損配管)及びB系配管について超音波肉厚測定器による肉厚測定を実施した結果、いずれもオリフィス下流側においては、ほぼ全周にわたり減肉傾向が認められ、オリフィス上流側においては有意な減肉傾向は認められなかった。
A系配管のオリフィス端面から697mm(約1・1/4直径)付近の破口部先端部において最も薄い0.4mmの箇所が認められた。B系配管ではオリフィス端面から734mm(約1・1/4直径)付近において最も薄い1.8mmの箇所が認められた。
軸方向の減肉量は、A系配管、B系配管いずれもオリフィス下流1直径~1.5直径付近で最大となり、下流側に向かって徐々に減少している。
なお、A系配管の底部(180°位置)の肉厚はオリフィス下流1.5直径から下流に向かってほとんど減肉しておらず他の位置と様相が異なっている。
周方向の減肉量については、B系配管は比較的均一に減肉しておりA系配管は頂部に偏って減肉している。 - (c)配管内面観察
A系配管(破損配管)のオリフィス下流側について、破口部からデジタルマイクロスコープにて配管内面の観察を行った結果、残留水によって表面が腐食し表面状態が変化したと推定される180°位置(配管底部)を除くすべての内面に、約1mm幅の鱗片状模様が一様に認められた。オリフィス近傍では、鱗片状模様は約3~5mm幅とやや大きいものであった。
なお、当該部はキャビテーションの発生しない温度、圧力条件となっており、内面観察からもキャビテーションの痕跡は認められなかった。
当該配管の材料は炭素鋼(SB42:板曲げ管)、寸法は外径558.8mm、公称肉厚10.0mm、でありJIS規格に基づく材料を使用している。また、当該復水系統は最高使用圧力1.27MPa,最高使用温度195℃である。 - b.給復水の水質履歴
2次系の水質管理履歴を調査した結果、給水、復水のpH、溶存酸素など給水処理に係わる水質データはいずれも水質管理値内に維持されていた。また、2次系給水処理は運転開始当初からAVT(*)、最近ではETA(**)処理等が計画的に行われているなど、各種対策により経年的に給水鉄濃度も低減してきていることから、運転開始以降当該部の水質環境について特異な点は認められない。
*:全揮発性薬品処理 **:エタノールアミン - c.破損メカニズムの推定
破損配管の肉厚測定結果によると、オリフィス下流部位に減肉が認められている。また、破損部位の内面観察結果では概ね全面にわたってエロージョン・コロージョン発生時に認められる光沢のある鱗片状模様が認められている。
以上のことから、当該部はオリフィス下流部位での流れの乱れによりエロージョン・コロージョンが発生したことにより減肉が進行し、肉厚が薄くなった部位が内圧により破口したものと推定される。
 配管肉厚管理に関する調査
配管肉厚管理に関する調査- a.PWRにおける2次系配管の肉厚管理
当社は、昭和50年代前半より2次系炭素鋼配管の減肉現象に着目し、配管の肉厚調査を進めていたが、昭和58年高浜発電所2号機において発生したエロージョン・コロージョンによる減肉トラブルを経験したことを契機に体系的な肉厚調査を開始した。
当該肉厚調査により得られたデータならびにそれまでの諸外国における運転経験等も含めた当時の技術知見を集大成して、平成2年5月に「原子力設備2次系配管肉厚の管理指針(PWR)」(以下「PWR管理指針」という。)を策定し、その後、現在に至るまでこのPWR管理指針に基づき2次系配管の肉厚管理を実施している。
b.当該破損部位の肉厚管理状況の調査
当該破損部位の肉厚管理状況について調査した結果、PWR管理指針では点検を実施すべき箇所に該当するものの、点検対象とはなっておらず(肉厚管理システムの管理票に登録されていない)、美浜3号機が運転を開始して以来、一度も点検を実施していなかったことが判明した。
当該部位は、美浜3号機ではじめて管理指針が適用された第11回定検(平成3年1~6月)から、登録漏れであった。その後、平成8年に当該業務をプラントメーカから協力会社に移管したが、移管にあたり、プラントメーカから検査用図面や点検リストの引渡しを受けた際も登録漏れに気づかなかった。
平成15年4月に協力会社が当該部位の登録漏れに気づいたものの、機械システムに登録しただけで当社へは連絡せず、同年11月に次回の点検計画を提案した際も、登録漏れであったことを当社への通知がなかったため、次回定検での点検が予定されるにとどまった。
c.他プラント等の状況
(a)肉厚管理の状況
美浜3号機を含む全ユニットの2次系配管の肉厚管理状況について、記録類をもとに調査した結果、肉厚管理未実施の部位が6箇所(美浜3号機の当該部位及びB系の同等部位含む)、同一仕様プラントの測定結果から健全性は確認できるものの、肉厚管理が未実施であった部位が11箇所あることを確認した。また、過去の点検記録の確認過程で「発電用火力設備の技術基準の解釈について」の「ただし書」を特例的に適用し、健全性評価を行うという不適切な事例があることが判明した。
(b)肉厚管理未実施部位等の点検状況
運転中のユニットを計画的に順次停止し、全てのユニットについて、上記の肉厚管理未実施部位、美浜3号機の破損部位と同等部位、その他の給水・復水系統のオリフィス下流部位等について、超音波肉厚測定器による肉厚測定を実施し、健全性を確認しているところである。
(3)当面とるべき対策について
これまでの調査結果から、現時点でとるべき対策について取りまとめ、実施することとする。これらの検討に当たっては、原子力事業本部長に社長が就き先頭に立って行うこととする。
なお、今後の調査結果とその分析から抽出される必要な対策については、適宜追加することとする。
 労働安全の確保
労働安全の確保
a.事故後直ちに実施した対策
事故後直ちに、運転中のプラントへの立ち入り制限を実施した。
やむを得ず作業が必要な場合には、防火服の着用等万全の措置を実施する。
また、2次系配管の健全性が確認されるまで、定期検査前準備作業を実施しないこととした。
b.被災者救出活動の確実な実施
緊急時において、被ばく又は放射性物質汚染の発生の有無等、被災者情報に重点をおいた事故内容の医療機関等への伝達方法について検討する。具体的には管理区域外での災害においても、医療機関等に確実に状況を把握して頂くため、被ばく又は汚染がないという情報を的確に伝達できるように所則類へ追加する。
救急通報の徹底、救出活動にあたる者に対する安全上の注意事項の明確化、消防・救急との連携強化、現場での作業人員の的確な把握の方策を行い、被災者救出活動をより迅速かつ確実に実施できる運用とすべく、所則類への反映を検討する。
また、発電所が要請した救急車等の緊急車両が地元を通過する場合の地元への連絡方法について検討し、確実な連絡を実施する。
 組織改正等
組織改正等
社長が先頭に立って事故原因究明、再発防止対策に取り組むため、原子力事業本部長を社長とする。
また、福井県に技術系役員が常駐し、技術的事項の的確な対応を行う。
 2次系配管肉厚管理の厳正化
2次系配管肉厚管理の厳正化
適正な保守管理を行うためには、点検対象範囲の特定、点検の頻度、時期、方法等を明確化することが必要であるので、以下を確実に実施する。
a.管理票の整備
スケルトン図(配管立体図)とPWR管理指針を照合し、肉厚管理が必要な箇所の管理票への反映状況を確認し、管理票を整備した。
b.管理業務の見直し
2次系配管肉厚管理業務については、点検計画の策定や点検結果の評価において協力会社への依存度が高かったため、当社が直接管理指針に照らし確実に管理を行う。
c.管理票の変更管理
2次系の設備改造工事を確実に2次系配管肉厚管理票に反映させるよう変更管理の仕組みを見直した上でルール化するとともに、当社社員が点検箇所に抜けがないかについて定期的なレビューを行う。
d.技術基準適用の厳正化
当社が行ってきた肉厚管理において、一部、技術基準解釈の「ただし書」の不適切な適用があった。今後は、技術基準の適用を厳正に行い、技術基準の解釈に明記されている規定値を用いて運用することとする。
e.肉厚管理が必要な配管への表示札取り付け
弁、ポンプ等は機器番号により容易に識別できるが、配管の減肉管理が必要な箇所については識別困難である。このため、自分の担当設備であるとの意識を醸成するとともに、管理状況を容易に確認できるようにするため、主要点検系統の肉厚管理対象部位に点検状況等を記載した表示札を取り付けることを検討する。
f.NIPSの改善
NIPSにあるスケルトン図と管理票とのリンク付け等により、点検箇所の追加等を容易に判断できるように、以下の改善を行う。
・ NIPSの位置づけ、所在、管理、運用方法(当社の関与)を明確にする。 ・ NIPSの高度化としては、活用目的を明確にさせて、設備改善に伴う変更や今後実施される配管指針の見直しによる部位の追加に対応した変更管理及びその際の運用方法を明確にする等が考えられる。
 当社と協力会社との情報共有化
当社と協力会社との情報共有化
品質保証体制導入等、管理業務を厳格に行う政省令改正の導入時期にあたることや改造工事の減少により、机上業務量が増加し、担当者の現場巡視機会が減少してきている。これにより、当社担当者と協力会社第一線作業者との交流機会が減少し、緊密な関係に基づいた情報交換が弱くなってくるおそれがある。
このため当社保修担当者の立ち会いを点検・検査結果の確認に限らず、各種作業ステップにおいても、協力会社担当者との交流を深め、双方向の情報受け渡しを行い、情報交換の維持・向上を図る。また、協力会社が行う朝礼、TBM等に至るまで積極的に共有することで協力会社との一体感醸成に努める。 地元との対話活動の充実
地元との対話活動の充実
今までも発電所のコミュニケーショングループを中心に、さまざまな機会を捉えて地元の方々との対話活動等を進めてきたが、発電所の技術者が直接地元の方々のご心配を汲み取り、発電所業務を運営することが重要である。こうした観点から、発電所においては技術系社員が地元の方々へ直接ご説明することとする。
さらに社長以下、本店・支社幹部が地元の方々と直接対話し、経営に活かしていくことが重要である。したがって、今後、当社幹部が直接地元の方々の意見を聞かせていただく、あるいは当社の状況等を定期的にご説明することとする。
- (4)今後の課題
-
 原因究明のための課題
原因究明のための課題 - a.破損メカニズム解明のための解析、試験
オリフィス下流での減肉事象の発生、進展の状況を確認するとともに当該破損配管の減肉の特徴を検証するために以下の解析、試験を行う。
(a)流動解析
A系配管(破損配管)及びB系配管等の配管構成を模擬して、計算機による流動解析を行い、オリフィス下流の流況、流れの乱れ分布を確認する。
(b)流況可視化試験
A系配管(破損配管)及びB系配管等の配管構成を模擬して、オリフィス下流を可視化した状態で流況、圧力変動を確認する。
(c)材料分析
A系配管(破損配管)とヒートナンバーが同じB系配管の残材を成分分析することによりCr等の影響を確認する。
b.2次系プラント挙動シミュレーション
復水配管破損後に脱気器水位が低下し、給水流量が低下し原子炉自動停止に至った2次系のプラントシステム挙動を解析し、実際のプラント挙動との比較検討等を実施し、炉心の冷却状態等の直接計測できないデータ及び復水管破損箇所からの流出流量等のデータを推定する。
c.破損事故の影響範囲に関する調査
復水配管の破損により多量の復水が流出した際の、破口部の衝撃力やその影響範囲を解析により確認する。また、その復水が蒸気及び水となり電気設備に侵入したことにより接地が発生したものと推定されるため、タービン建屋の機械、電気設備等に対する影響を調査し、健全性評価の上、必要な対応を検討する。
 品質保証、保守管理上の問題点の調査
品質保証、保守管理上の問題点の調査
2次系配管肉厚管理調査工事における工事計画や結果の評価段階等での当社の関与が不足していたことから、調達管理方法などについて課題を整理し、品質保証及び保守管理について以下の対策を実施する。
a.補修工事における外注管理の厳正化
2次系配管肉厚管理調査工事を含む補修工事全般に関して、以下の事項について調達管理を定めた社内標準に反映する。
・ 要求事項、管理方法、責任分担、外注先の的確性等を明確にした工事仕様書を作成する。 ・ 調達業務において調達先で不適合が発生した場合に当社へその情報を連絡する仕組みを整備する。 ・ 調達業務が適切に実施されていることを当社として確認するための仕組みを整備する。
- なお、2次系配管の点検リストに不備があったことに鑑み、他の点検工事についても、原子力保全機能強化検討委員会にて検討を行う。
b.保全体制の再構築
今回の事故に鑑み、現行の保全体制の課題を整理し、メーカ等を含む体制の再構築等を検討し、確実に保全業務の運用を目指すために、社内関係者(原子力以外を含む)及び社外有識者で構成する「原子力保全機能強化検討委員会」を設置し、検討を開始した。
今後、社外有識者として、品質管理、法律、原子力の専門家に委員としてご就任いただく予定であり、第三者の目からもご意見をいただく予定である。
 2次系配管肉厚管理の更なる充実
2次系配管肉厚管理の更なる充実
今回の減肉管理調査の過程で配管肉厚管理方法の点でも改善すべき事項が顕在化していることから管理指針の高度化を図る。
これまでの実機計測データの集約による見直しや設備実態に応じた運用マニュアルになっているかという観点での見直しを実施し、以下の点を改善する。
・当社における過去の減肉データ実績の分析、取替え実績の整理を実施し、どういった部位がどのような減肉率であるかを整理する。また、その他の系統に関して、減肉傾向を持つ箇所もあるため、範囲や具体的運用方法等について見直す。
・各電力よりデータを集約するとともに最新の海外情報により、管理指針の見直しを学協会等で実施する動きがあり、当社としても積極的にこれに参加する。
(5)おわりに
平成16年8月9日に発生した美浜発電所3号機の事故につきまして、亡くなられた方々とそのご遺族の皆さまに対しまして衷心より深くお詫び申し上げますとともに、亡くなられた方々のご冥福を心からお祈り申し上げます。また、負傷された皆様におかれましては一日も早くご回復なさいますことを心からお祈り申し上げます。加えて、地元の方々をはじめ多くの皆様に大変なご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
当社は今後二度と同様の事故を起こさないために、本報告書においてこれまでに判明した事故原因と当面の対策について中間的な内容をご報告いたしました。当面の対策を速やかに実施するとともに、今後原因究明を進めることに全力を尽くして取り組みます。
さらに、再発防止を徹底するとともに、原子力発電所の安全の確保と当社に対する信頼回復に努めてまいります。
以 上