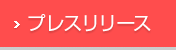プレスリリース
 2003
2003
2003年10月27日
海外の原子力発電所ベンチマーキング調査について~「広く海外に学ぶ」~
当社は、従来から原子力発電所の故障・トラブルの低減に努めるなど、原子力発電に関わる品質の向上に取り組んでおります。その結果、平成14年度実績では原子力設備利用率90.5%と、過去最高水準を実現しておりますが、さらにこれからも、継続的に原子力発電所の安全・安定運転を続けるため、諸外国において優秀な運転成績を達成している発電所や立地地域住民とのコミュニケーションを積極的に行っている発電所の事例を調査し、当社事業に取り入れていくこととしました。
まず、その最初の取り組みとして、今年8月から9月にかけて、米国の原子力発電所に調査員を派遣し、ベンチマーキング調査を実施しましたので、その概要をご紹介します。
| (1)調査目的 | |||
| 海外の原子力発電所の中で、設備利用率などにおいて優秀な運転成績を達成している発電所や、地域とのコミュニケーションにおいて積極的な活動を行っている発電所の好事例を学び、必要ある場合はそれを取り入れることで、当社の原子力発電所運営のさらなる向上を目指すもの。 | |||
| (2)調査概要 | |||
| ○目 的 | 発電所長によるマネジメント活動のベンチマーキング | ||
| ○調査体制 | 美浜発電所長以下 計4名 | ||
| ○調査対象 | ロビンソン発電所(サウス・キャロライナ州、プログレス・エナジー社) カトーバ発電所(サウス・キャロライナ州、デューク・パワー社) |
||
| ○調査期間 | 平成15年8月28日~9月7日[11日間] | ||
| ○調査内容 | 所長のリーダーシップ、品質保証活動など | ||
| ○目 的 | 発電所立地地域とのコミュニケーション活動のベンチマーキング | ||
| ○調査体制 | 原子力事業本部 原子力企画部長以下 計4名 | ||
| ○ 調査対象 | セント・ルーシー発電所(フロリダ州、FP&L社) ミルストン発電所(コネチカット州、ドミニオン社) |
||
| ○調査期間 | 平成15年9月4日~12日[9日間] | ||
| ○調査内容 | 地域への情報公開、理解活動など | ||
| (3)今後の予定 | |||
| <マネジメント活動調査> | |||
| ・平成15年11月 高浜発電所長他 米国 | |||
| ・平成16年1~2月 大飯発電所長他 米国 | |||
| <コミュニケーション活動調査> | |||
| ・平成16年2~3月 欧州 | |||
| 次年度以降も、海外の原子力発電所とのベンチマーキング調査を継続実施予定。 | |||
| 【 特徴的な取り組み 】 | |||
| <発電所のマネジメントに関して> | |||
| ◇所長のリーダーシップについて | |||
| 所長の強力なリーダーシップの下、所長が発電所としての目標値(設備利用率、発電コスト、自動停止回数等)を設定。その目標値の達成度合いは、毎月、分かりやすく提示し、全所員で発電所運営に関する問題意識を共有し、所員一丸となって、目標達成に取り組んでいる。
目標値に対する達成度合いを色で表示し、所内の掲示板に表示したり、ミーティングの中で配付するなどして、その達成度合いを共有化している。 |
|||
| (ロビンソン、カトーバ) | |||
| ◇品質保証活動について | |||
| 所員全員が常に発電所の状況を監視し、不具合情報を抽出・是正するシステム「是正措置プログラム」が設備利用率の向上に寄与している。 ― 是正措置プログラム(Corrective Action Program)― 発電所の不具合情報の抽出や改善提案を行うシステムで、プラントに関わる大きなトラブルは当然のこと、所内の職場環境を改善するなど日々の業務に関する改善提案をも、所員がコンピュータに入力し、担当箇所が処理する。 システムに入力されたデータは全所員にオープンにすることで共有化が図られており、発電所の品質保証活動に役立てられている。 |
|||
| (ロビンソン、カトーバ) | |||
| <コミュニケーション活動に関して> | |||
| ◇ 地域情報連絡会議(Community Advisory Panel)の設置 | |||
| 電力会社と地域住民との間のクッション的な第三者組織として設置されている。
安全問題や信頼の失墜に起因して、中立的な組織として設置された「州政府主導型」(ミルストン)、情報提供の場であるとともに、発電所のコミュニケーション活動に関する地域ニーズを把握するために設置された「電力会社主導型」(セント・ルーシー)の2種類がある。 これらの連絡会議により、事業者や規制当局から発信される情報の透明性が確保されている。 |
|||
| ◇発電所地域対応チーム(Community Outreach Team)の活動 | |||
| 発電所が立地されている地域住民とのコミュニケーション活動を担うチームで、自発的に志願した発電所の技術系社員で構成されている。 発電所立地地域の、環境保護団体等のNGO、ウーマンズクラブ等の市民グループ、教育関係団体などに直接出向き、対話を重視した双方向のコミュニケーション活動を実施している。 地域の人々の興味・関心は何かを引き出すために質疑応答に時間を費やし、その内容を全てデータベース化している。このデータベースの活用により、チーム全員で情報を共有化し、住民理解の促進に役立てている。 |
|||
| (セント・ルーシー) | |||
| ◇次世代教育プログラム | |||
| ボーイスカウトのカリキュラムを活用した原子力に関する次世代層教育の取り組み。 発電所の専任スタッフが講師として原子力に関する高度な知識を教えることにより、原子力発電への理解促進を図っている。このカリキュラムを修了するには、原子力に関する専門用語の解説など、非常に高度な知識が求められており、カリキュラム修了者にはそれを証明するバッジ「アトミック・メリット・バッジ」が与えられ、カリキュラムが難しいことからボーイスカウト内の昇級時に高く評価されている。 |
|||
| (セント・ルーシー) | |||
以 上
<参考資料>