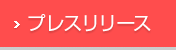プレスリリース
 2003
2003
2003年7月13日
訃 報
1.関西電力社長として
昭和34年11月、関西電力の社長に就任、火力発電における重油専焼技術をはじめエネルギー流体革命に対応した発電方式の確立や、黒四建設におけるアーチ式ダム開発、9社初の原子力発電の導入、超高圧送電網の建設、2万ボルト配電など、発電から配電に至る広範な革新技術の開発導入を進めるとともに、設備運用や経営管理面におけるコンピュータリゼーションの推進による経営全般の近代化、効率化に努めた。
この結果、昭和29年の電気料金改定以来、上昇する電力コストを吸収し、19年間にわたって、電気料金を値上げしなかった。
また革新技術の導入のなかでも、とりわけ原子力発電については、社長就任以前の昭和30年ごろからこれが将来の発電の主流になることを予見し、調査研究に努めるとともに、技術者の養成をはかってきた。昭和30年代後半に至り、わが国エネルギー問題の解決には原子力の開発が不可欠であるとこを確信し、昭和41年美浜発電所1号機の建設に着手した。昭和45年8月8日、折から開かれていた大阪万博に同発電所の試運転電力が送られ、関西電力のみならずわが国電気事業に原子力時代を開いた。
2.関西電力会長として
昭和45年11月、会長に就任したが、折から環境問題への関心の高まりから電源立地が困難となり、また昭和45年ごろを境に石油需給が逼迫に転じ、二度にわたる石油ショックが起こった。そのため、徹底した経営効率化を進めるとともに、電気料金の正常化にも取り組み、また電源立地難に対しては、直接その解決に尽力する一方、中央政財界に立地問題への理解と支援を働きかけ、政府の電源立地促進政策の強化を支援するとともに、原子力開発については国民的コンセンサスの確立に努めた。
3.関経連会長として
昭和41年11月、関経連会長に就任以来、東京への一極集中が日本全体の衰退を招くという危機意識のもと、それまでの「関西モンロー主義」の転換をはかり、中央政財界、行政界との意思疎通を強化して、関西における国家的施策の推進に努めた。
また、関西の国際化、近代化のため、資本貿易の自由化促進へ経済界を指導するとともに、関西経済連合会友好訪中団団長としての訪中など、中国の友好の絆を固めたのをはじめ、国際交流活動を活発化し、また画期的な道州制の提言にみられるような産学共同研究を行った。
とりわけ特筆すべきは、昭和45年の関西最大の国家的大事業である日本万国博覧会の開催である。万国博協会副会長として、その準備、運営の重責を担い、最も困難な課題であった会場内外の施設整備に尽力し、同博覧会の画期的な成功に主導的役割を果たした。
また、関西国際空港の建設についても、昭和45年関西経済界の支援組織として、在阪神経済8団体による関西新国際空港推進協議会を結成してその会長に就任するなど、計画実現に向けて尽力したところであったが、関経連会長退任後も、昭和54年に運輸省航空局長の相談機関のメンバーとして、空港建設工法の検討を行い、空港建設、運営の事業主のあり方についての建議するなど、関西国際空港の建設実現に貢献した。このため、昭和59年、請われて関西新国際空港株式会社設立委員長に就任、関西新国際空港株式会社設立後も相談役に就任して、新空港の建設を指導した。
なお、電気事業者として、あるいは広くこうした経済界での活動によって、昭和53年11月、勲一等旭日大綬章を受章している。
以 上