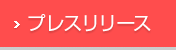事故報告漏れの再発防止のため、以下を基本に、設備の実態に応じた効果的な対策を講じるものとする。なお、既に対策が確立している部門については、その内容の遵守等について再徹底することとする。
(1) 電気事故の発生連絡漏れ防止措置の構築
| |
a.「報告要否判定フロー」を作成し、判定のバラツキを防止 |
| |
|
「報告要否判定フロー」を作成し、判定のバラツキを防止電気事故報告の種類、内容、報告対象範囲等については、電気関係報告規則第3条で規定されているが、今回の報告漏れに鑑み、制御所等事故発生箇所および支店(社)等設備所管箇所においても判断に迷うことなく判定出来るよう「報告要否判定フロー」を作成し報告漏れの防止を図るとともに、その活用について関係社内標準に規定する。 |
| |
|
(対策実施予定:平成14年11月末)
|
| |
b.運転・保全要員への教育 |
| |
|
「電気関係報告規則(事故報告)」について、運転・保全要員などの関係者全員に教育を行い、実施状況を管理する。 |
| |
|
(対策実施予定:平成14年11月末)
|
(2) 電気事故報告の要否判定箇所の明確化
| |
a.電気事故報告の要否判定箇所を支店(社)等に一元化 |
| |
|
電気事故報告の要否判定箇所を支店(社)等に一元化し、その判定は主任技術者が行うことに変更する。なお、この内容については、主任技術者業務要綱等に追加し責任の所在を明確化する。 |
| |
|
(対策実施予定:平成14年11月末)
|
| |
b.電気事故報告要否判定のチェック機能の強化 |
| |
|
電気事故報告書提出箇所は、報告のあった事故内容の確認を行い、報告の要否について必要に応じサイドチェックを行う。 |
| |
|
(対策実施予定:平成14年11月末)
|
| |
c.協力会社に迅速な事故報告について指導 |
| |
|
平成12年11月に、配電関連の協力会社3社に対し、事故報告の遅延に対する指導(危機管理体制の確立と、危機管理教育の実施)を実施したが、今回、再度関係協力会社に周知徹底し再発防止を図る。 |
| |
|
(対策実施予定:平成14年11月末)
|
(3) 災害発生時の電気事故報告箇所への報告ルール明確化
| |
事務系部門も含め全部門に適用する共通社内標準「業務上災害等事務取扱通達」に、感電災害等電気工作物に関連する災害が発生した場合は、現行の安全担当箇所への報 告に加え、支店(社)の電気主任技術者にも報告し、所轄経済産業局への報告を依頼する旨規定する。 |
| |
|
(対策実施予定:平成14年11月末)
|
(4) 電気事故報告状況について自主点検実施
| |
今回の電気事故報告漏れに鑑み、対策の定着が確認されるまでの間、年1回の頻度で電気事故報告状況について自主点検を行い、電気事故報告業務が適正に実施されているか確認する。また、同時に今回の対策が適正に機能しているか確認を行い、必要があれば改善を行う。 |
| |
|
(対策実施予定:平成15年下期〔1年後〕)
|
(5) 再発防止対策の全関係社員への周知徹底
| |
今回の対策について、主任技術者会議等で周知徹底するとともに、各主管グループは、その内容の関係者全員への周知状況について報告させ確認を行うものとする。 |
| |
|
(対策実施予定:平成14年11月上旬)
|
| |
なお、今回の報告漏れに鑑み、コンプライアンス(法令遵守)について関係箇所に、今回の調査責任者である、関係本部・事業本部・室の副本部長・副事業本部長・室長名文書で周知徹底する。 |
| |
|
(対策実施予定:平成14年10月末)
|
|
 2002
2002