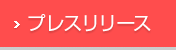プレスリリース
 2000
2000
2000年5月8日
関西電力株式会社
多方向不規則波を用いた構造物の耐波特性に関する研究
実際の海の波は、1波ごとに波の高さや周期が不規則に変化しています。
さらに、少し沖合の海面を観察するとよく分かるように、波の峰が切れ切れで向きもばらばらになっています。
これは、いろいろな方向に進む波が重なり合って生じる状態であり、波の進行方向が一定で波の峰が長く連なった状態の単一方向波に対して、多方向不規則波といわれています。
土木構造物の実設計において、海の波、風、地震などの性質を明らかにし、自然の外力を精度高く評価することは、構造物の安全性の面だけでなく、構造物をできる限りスリムに設計して建設コスト低減へとつなげる面からもたいへん重要といえます。
現在、規則波や単一方向不規則波の実験結果を用いることが多い海岸構造物(人工島、防波堤など)の耐波設計(越波、波力、安定性などの検討)においても、今後、多方向不規則波を用いた水理模型実験結果によって波浪現象を評価し、実設計に反映させることが期待されています。
多方向不規則波に関する研究は、多方向不規則波造波装置を有するいくつかの研究機関で実施されています。
当社においても、数年先の実設計への反映を目指し、1987年に総合技術研究所に設置した多方向不規則波造波装置を用いて研究に取り組んでいます。
構造物周辺の波の挙動は非常に複雑であり、基礎的な特性すら十分に解明されていない現象も見られます。
本研究は、構造物周辺海域、および構造物沿いにステム波(Mach-stem)が形成される場合の波浪場特性(波高分布、海浜流)を把握するとともに、そこでの入射波の多方向性の影響(多方向不規則波と単一方向不規則波の違い)を明らかにしようとしたものです。
多方向不規則波の研究は、多くの研究機関によって、次第に複雑な波浪現象を対象とした研究が実施されつつあります。
当社も、ステム波の発達にともなう砕波現象や構造物の越波、安定性を対象として、多方向不規則波の特性についての研究に取り組む予定です。

多方向不規則波造波装置(幅18m)

構造物全面のステム波の発達