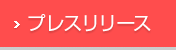プレスリリース
 2000
2000
2000年6月14日
BNFL製MOX燃料問題に関する調査結果について
- 1. 経緯
- 英国BNFLのMDFで製作され、高浜発電所に輸送された4号機用MOX燃料8体に関し、昨年11月、当社はペレット外径の品質管理データに不正はないものとして最終報告書を公表したが、同年12月16日に新たに不正が発覚し、MOX燃料の高浜4号機への装荷を断念した。
これにより、重要な原子力政策であるプルサーマル計画がスタートでつまずく結果となり、関係各方面に多大なご迷惑をお掛けするとともに、社会の信頼を大きく失うこととなった。
本件の重要性に鑑み、全社的にこの問題に取り組むため、平成12年1月11日に品質監査担当の副社長を委員長とするBNFL製MOX燃料問題調査検討委員会を設置し調査を開始した。本報告書は、調査検討委員会および三菱重工業による調査結果およびBNFLと英国原子力施設検査局(NII)の報告内容を踏まえて、不正発生の原因究明、再発防止対策等について総合的にとりまとめたものである。また、品質管理および原子力安全分野の社外専門家にも報告書のレビューをしていただき、その結果を本報告書に反映した。 - 2. 調査の目的
- 今回のデータ不正の実態を解明するとともに、品質保証・品質管理上の問題点を抽出し、さらにそれらの背景を明らかにすることによって、有効な再発防止対策を導き出すことを目的としている。
- 3. 調査の結果と問題点
(1) MDF検査データの分析調査
a. ペレット外径データ - 不正の手口をBNFL及びNIIの解析およびその他の手法を用いて検討した結果、31ロットが特異なデータを含むロットとして抽出された。これらの中には、当社が昨年9月に不正と判断した22ロットと、同12月に新たに不正が明らかとなった1ロットが含まれる。
その他の8ロットについては、データ一致数、および検査員からのインタビューからは直ちに不正と断定できないが、昨年11月から今日までに判明した次の事実を総合的に勘案して不正と見なさざるを得ないと判断した。
- 検査員のパートナーに、コンピュータ操作に明るい運転員がいるという証言が明らかになったこと。
- 不正に関与したと思われる人数が当初より拡大したこと。
- 抜き取り外径検査における品質管理の不具合やコンピュータ・データ管理の甘さにより、不正の入り込む余地があること。
- 規制当局であるNIIの報告書で、BNFLの多くの不具合が指摘されていること。
- b. ペレット外径以外のデータ
- ペレット外径以外の検査項目については不正の可能性は低く、今回の調査でも不正があったことを示す事実は見いだせなかった。
- (2) 品質保証・品質管理の問題点
a. MDFにおける問題点 -
- 管理者、作業者とも、品質保証・品質管理の重要性の認識が弱く、要領書を遵守して作業を行わなかったことがあった。
- 業務の的確かつ効果的な実施に対する、組織的な確認が弱かった。
- 工程性能の向上、自動化が行われておらず、長時間の単調な抜き取り外径検査が改善されなかった。
- 品質管理データが手入力でデータの不正が容易であった。また、データへのアクセスを制限する措置が取られていなかった。
- 検査員が品質管理部門ではなく運転部門に所属し、役割分担が不明確であった。
- 検査員、運転員および管理者に対する教育が不十分であった。
- b. 三菱重工業における問題点
-
- 資格審査において、MDFの設備上の問題を認識し、BNFLに対する是正指導・監督を行っているが、元請け会社として組織をあげた指導・監督には至らなかった。
- 資格審査で把握した問題点を踏まえた、製造中の品質管理が十分ではなかった。
- 監査は、海外で最初のMOX燃料加工であるということを認識し、書類審査のみではなく、製造段階において作業現場の実態把握や作業員の要領書遵守状況まで把握すべきであった。
- 立会検査において、検査データのバラツキ評価による製造能力の確認を行っていなかった。
- c. 当社における問題点
-
- 当社は、三菱重工業の資格審査で十分と考え、BNFLに対する監査を実施しなかった。
- 当社自ら監査等により現場実態を確認すべきであった。
- 当社の立会検査は、MDFのペレット製造に関する作業実態の確認という観点では十分とはいえない状況であった。
- (3) 本件発生後の当社および三菱重工業の対応における問題点
- BNFLからの情報に基づき、直ちに現地に社員を派遣する等対応しているが、初期調査段階で知り得た単純なデータ不正の手口および当時得られた検査員の証言に基づいて調査の方向性を絞り込み、不正の全体像を見失ってしまった。
- 不正の発見に目を奪われ、後日明らかとなったMDFの劣悪な品質管理状況までは確認できなかった。
- NIIが抱いていた疑義について、もっと技術的解明をするとともに、担当箇所のみで判断するのではなく、全社的な検討を行うべきであった。
さらに、この情報が通産省の判断に影響を及ぼす可能性のあることも思量し、通産省をはじめ関係箇所に適切に連絡すべきであった。
- (4) 燃料棒異物混入問題の調査
- 平成11年9月7日、MDFにおいて製造中の高浜3号機向けMOX燃料の通常のX線による検査中に、燃料棒2本に異物が確認され不合格とされた。
本件については、約3週間後に、MOXデータ問題調査団に、三菱重工業を通じ、異物混入により燃料棒2本を不合格とした旨、口頭で連絡を受けた。しかし、当該燃料棒がBNFLの通常検査で不合格となり、当社が調査を開始する前に、工程から既に排除されていたこと、また、当時はMOX燃料の検査データに不正はないかを中心に調査を進めていたことから、特に重要性を認識せず追及は行なわなかった。
当社と三菱重工業は、燃料棒に異物が確認されたという情報を現地で聞いた際に、その発見時期、異物の性状、混入時期、混入場所等について正確に確認すべきであった。
一方、BNFLは当時から燃料棒中の異物が故意に入れられた可能性も考えられるとし、本件を一つのきっかけとして社長指揮の外部専門調査員による特別調査を開始した。しかしBNFLは機密保持を理由に、異物の性状、および故意の可能性について平成12年2月7日まで当社に報告しなかった。
このような重要な情報が正式に連絡されなかったことは、結果として、当社の初期調査の方向を誤らせることとなった。
- a. 調査結果
- 当社は、本件の重要性に鑑み本年3月~4月に追加調査を行った。
- (a)異物の特定と混入経路
-
- 異物は、MDF内で使用されていた全長9ミリ、頭部径約5.5ミリのステンレス製ネジと、MDF内の床材であるコンクリート片である。
- 異物は当該燃料棒が仮置きされていた約8時間の間に混入されたものと推定。
- (b)不正を行った者と動機
- 第三者の外部専門調査機関による調査の結果、誰も混入を認めたものはおらず、また目撃証言や物的証拠もないため断定はできないが、得られた状況証拠に基づきBNFLは以下のとおり推定している。
- MDFでは全ての燃料棒について全長X線検査が行なわれるため、たとえ異物を混入させても必ず発見されることは、MDF内では周知の事実であったことから、動機は破壊工作ではなく、異物が発見されることによる何らかのメリットを狙ったものである。
- 異物が確認された9月7日の数日前に、BNFLのペレット外径データの不正に関する調査で他の作業員の一人がデータ不正を認め、会社による追求がさらに進捗しようとしていた。このため、データ不正に関与した人物が、会社の追求が自分に及ぶことを恐れ、異物混入事件を引き起こすことにより追求の矛先をデータ不正の件からそらそうとした。
- 不正を行った者については、異物が混入された時間帯に現場にアクセスできた人物をMDF立入記録で調査したところ、2名が洗い出された。そのうち1名はデータ不正を行った人物であり、既に解雇されており、特に疑いが濃い。もう1名については、異物混入に関与している可能性はほとんどないが、MOX関連業務に従事させないこととしている。
- b. 異物混入防止対策
故意による異物混入に対して、以下の再発防止対策を実施する。 - (a) 海外MOX燃料メーカー
- 燃料被覆管を、自由にアクセスできる状態で長時間仮置きしないこと。
- 従業員に対して本件およびその重大性について周知徹底するとともに、従業員の品質意識の向上に取り組むこと。
- 品質に影響する異常事象が発生した場合、速やかに元請けおよび当社に連絡するよう通報連絡方法、体制を明文化すること。
- (b) 元請けメーカー
- 上記の海外加工メーカーの再発防止対策が実施されていることを、加工前の資格審査にて確認するとともに、加工中も適宜監査を行なうことにより確認すること。
- 海外加工メーカーから異常事象に関する情報提供を受けた場合、常に詳細を調査し、文書による正式な報告を要求する姿勢を持つこと。
- (c) 当社の再発防止対策
-
異常事象について報告を受けた場合、常に詳細を調査する姿勢を持つよう社内教育を徹底する。
- 4. 不正に関与した従業員等に対する措置について
- 不正に関与した従業員、その可能性のある従業員、および不正に気づいていたが対応しなかった従業員ならびに監督が不行き届きであった管理職について、BNFLはこれまでに19人の処分を以下のとおり行った。これにより、不正および異物混入等に関与した人物はすべて解雇されたか配置転換された。
- 検査員、運転員: 4名を解雇、9名を配置転換
(当初5名が解雇されたが、1名が再審議により復職された。) - 管理職: 2名は辞職、4名を配置転換
- 検査員、運転員: 4名を解雇、9名を配置転換
- 5. 再発防止対策
(1) 再発防止対策の基本的考え方 - MOX燃料の品質は、高い品質意識の下に、当社、元請け会社、海外MOX燃料メーカーが一体となって保証すべきものである。
そのために、当社は主体性を持って今後のMOX燃料の品質確保に当たることとし、当社、元請け会社および海外MOX燃料メーカーが実施すべき品質保証活動を明確にするとともに、各組織が一体となった品質保証体制を構築する必要がある。 - (2) 海外MOX燃料メーカーへの品質保証・品質管理の要求
- 海外MOX燃料メーカーとの契約に当たり、当社および元請け会社は以下の事項について要求、確認する。
- 適切な品質保証・品質管理の仕組みの確立と実施。
- 製造プロセスの適切な確認。
- 品質管理データの厳格なセキュリティ確保。
- 組織の責任と権限の明確化。
- 異常時の適切な措置。
- (3) 元請け会社への品質保証・品質管理の要求
- 元請け会社は十分な品質保証体制を確立し、製造プロセスを現場実態にまで立ち入って確認し、問題がある時は指導、監督する必要がある。当社は元請け会社に対し次の事項を要求、確認する。
- 海外MOX燃料メーカーに対する組織的な指導・監督が行なえるような品質保証体制。
- 現場の状況確認まで踏み込んだ資格審査。
- 製造段階における的確な監査。
- 製造開始時期の綿密な立会検査および長期滞在等による品質の確認。
- 異常時の適切な措置。
- (4) 当社の品質保証・品質管理の改善
- 当社は、緊急の課題としてMOX燃料加工における品質管理活動の改善を図るとともに、経営にとって重要な品質・安全面をチェックできる体制を整備することが必要である。
- a. 海外MOX燃料加工における品質保証・品質管理活動の強化
- 資格審査段階における元請け会社、海外MOX燃料メーカーに対する監査の実施。
- 製造段階における専門家の長期派遣等による立会検査体制、内容の充実。
- 異常時の適切な措置。
- b. 社内体制の強化
- 今回のデータ不正に関する当社の対応および品質保証・品質管理への取り組みの問題点に対する反省を踏まえて、今後、このような問題が発生しても経営として全社的に的確、かつ迅速に対処するため、社外の専門家を交えた品質・安全委員会の設置等により全社体制を強化するとともに、原子燃料部門の体制を強化する。
- (a)全社体制の強化
- ・品質・安全委員会の設置。
- 品質・安全委員会を設置し、品質・安全に関する経営的諸問題を幅広く共有・審議するとともに、社外の見識や情報を取り入れてより良い品質・安全の確保にあたる。(平成12年4月1日)
- ・品質管理・安全管理拠点の構築。
- 部門や事業所を離れた立場から、それぞれの品質保証・品質管理活動をチェックする拠点として、企画室 品質監査グループを品質・安全監査室として独立させ、機能を強化する。
- (b)原子燃料部門の組織の強化
- 原子燃料部門に品質・安全チームを設置(平成12年3月1日)し、専門的な観点および独立した立場から品質保証・品質管理の仕組みが適切かつ効果的に機能していることを確認する。また、元請け会社および海外燃料メーカーの品質保証・品質管理の指導を強化する。
- a. 海外MOX燃料加工における品質保証・品質管理活動の強化
- 6. 結言
- 調査検討委員会は、今回の問題の当事者である当社原子燃料部門以外の各部門から選定した委員およびワーキンググループ構成員が中心となって調査・検討することにより、第三者的な立場から客観的調査を行った。さらには、品質管理および原子力安全分野の社外専門家に報告書のレビューをお願いし、貴重なご意見をいただき本報告書に反映した。 調査検討委員会はBNFL・MDF工場において発生したデータ不正に関して、データ不正の全容を調査し、不正発生の誘因となったMDFの品質管理の実態を確認するとともに、当社および元請け会社の品質保証・品質管理に問題がなかったのかについて調査・検討した。また、不正発覚後の当社および三菱重工業の対応状況についても調査した。これらの調査結果を踏まえ、MOX燃料の品質保証・品質管理を確立することによって、不正発生を防止するための再発防止対策を策定した。今後のMOX燃料の海外発注にあたっては、この再発防止対策を実効あるものとし、MOX燃料の品質を確保していくことが重要である。 さらに、本報告書に記載した原因究明、再発防止対策のほかに、補償問題についても検討した。補償問題については、当事者間の懸案事項として継続協議していく。また、高浜4号機で使用中止としたMOX燃料集合体8体の返送については、既にBNFLに返送要求しているところであり、今後実現に向けて関係箇所と協議していく。 今回のデータ不正問題における当社の対応が十分でなく、これまで培ってきた当社の原子力発電に対する信頼を大きく損ったことを反省し、この教訓を今後の業務に活かすとともに、社会的な信頼の回復と理解を得るよう今後とも努力していきたい。
以 上