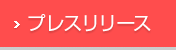プレスリリース
 1999
1999
1999年5月25日
関西電力株式会社
美浜発電所2号機の点検結果について(余剰抽出水系統配管からの漏えいの原因と対策)
美浜発電所2号機(加圧水型軽水炉定格出力50万キロワット)は、復水器内に海水の微少な漏れ込みがあるものと推定されたことから点検・補修のため、平成11年4月29日14時00分から出力降下を開始し、同日15時45分に電気出力を約65%として運転していましたが、4月29日の格納容器サンプ水位の上昇率において通常値に比べ、有意な増加が認められました。
このため、関連する計測値の監視強化を行うとともに、各部の点検を行った結果、Bループの余剰抽出水系統取出配管部付近からわずかな水漏れが認められたことから、より詳細な点検、調査を行うため、4月30日に発電を停止しました。
なお、今回の事象による周辺環境への放射能の影響はありません。
その後、水漏れが認められた箇所の外観点検を実施した結果、Bループ1次冷却材ポンプ入口配管の余剰抽出水系統取出配管曲げ部の背側中心部近傍に直線状の割れ(外表面長さ約7mm)が確認されました。
[平成11年4月30日、5月7日記者発表済]
- 1.詳細調査結果
- (1)当該損傷部を切り出し、試験施設にて詳細な外観観察を実施した結果、割れは外面で長さ約7mm、内面で長さ約24mmであり、貫通していることが確認されました。
その他に、管内面の当該部の近傍には貫通に至っていませんが、長さ約14.5mmの割れと微小な割れが認められました。
割れは、管内面の背側中心部近傍から発生しており、割れの破面には、疲労によると思われる特徴が観察されました。
また、当該曲げ部の管内面においては、付着物の厚さの違いにより、上部は黒色、下部は茶色、その間の曲げ部には茶褐色部の模様が認められ、茶褐色部において温度の境界面(下流側が弁により仕切られ、通常運転中に流れがない配管においては低温の水が滞留しており、ここに1次冷却材配管から高温の1次冷却水が入り込んで温度の境界面が生じる)が生成していたと推定されました。 - (2)工場において実機の配管形状を模擬した流動試験を実施した結果、1次冷却材配管の曲がりによって1次冷却水の流れに変動が生じ、その影響で、従来の知見に比べ温度の境界面の生成位置が浅くなることが確認されました。
また、当該配管と同様に配管曲げ部に温度の境界面を生成させる試験を実施した結果、境界面が周期的に上下に変動することが確認されました。 - (3)当該の配管曲げ部については、製作時の曲げ加工によって管の背側内表面に比較的高い応力が残留することが、模擬試験により確認されました。
- (1)当該損傷部を切り出し、試験施設にて詳細な外観観察を実施した結果、割れは外面で長さ約7mm、内面で長さ約24mmであり、貫通していることが確認されました。
- 2.原因
当該配管においては、1次冷却材配管から高温の1次冷却水が入り込んで低温水との間に温度の境界面が生じるが、その境界面が従来知見より浅い配管曲げ部に位置したことから、温度の境界面の変動による熱応力が繰り返し作用し、製作時の配管曲げ加工による残留応力と相まって熱疲労による割れが内面に発生し、徐々に進展して貫通漏えいしたものと推定されました。
また、温度の境界面が想定位置より浅い部分に生成された原因は、当該余剰抽出水系統配管が、曲がった形状のBループ1次冷却材ポンプ入口配管からの分岐管であるため、1次冷却水の流れの変動等の影響により、高温の1次冷却水の侵入深さが浅かったためと推定されました。 - 3.対策
当該配管については、高温の1次冷却水が入り込んで生じる温度の境界面が配管曲げ部に影響しないように、Bループ1次冷却材ポンプ入口配管から曲げ部までの長さを変更するとともに、残留応力の小さい曲げ管に取替えます。
また、今回の知見を配管の設計基準に反映します。
なお、念のため、プラント起動時に当該曲げ部付近の温度測定を行い、温度の境界面の発生状況を把握し、対策の妥当性を確認します。
対策実施後、6月中旬頃に運転を再開する予定です。
以 上
| 基準1 | 基準2 | 基準3 | 評価レベル |
| - | - | 0- | 0- |
<参考資料>