事業所・関連施設
 原子力事業本部
原子力事業本部
越前若狭探訪
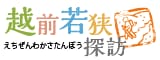



▲特産「福井梅」発祥の地、伊良積の高台から望む三方湖(手前は梅林)
若狭町の三方湖畔に、風情のある茅葺(かやぶ)きの舟小屋(ふなごや)が立ち並ぶ。早春の梅の開花期はとりわけ美しく、景勝地三方五湖エリアでも指折りの撮影スポットとして、多くのカメラマンが訪れる。
この西田(にした)地区北庄(きたじょう)に並んで立つ6棟と隣の伊良積(いらづみ)にある4棟の舟小屋は、一見したところ湖で漁をする舟を格納するためのものと思われがちだが、二つの集落はともに農業が主で、漁業権を持たない。在所に近い耕地には限りがあり、対岸の長尾島(ながおじま)などの梅畑や水田まで行き来をしたり、特産の梅を運ぶために、かつて舟を利用した。
三方湖畔に立ち並ぶ舟小屋(北庄)▼


▲梅の花が春の訪れを告げる三方湖畔(伊良積)
時を江戸後期に巻き戻すと、伊良積は特産「福井梅」発祥の地で、天保(てんぽう)年間(1830〜44)に伊良積で初めて売り梅として梅の木を植えたのが福井梅(当時は西田梅)の始まりとされる。その後、明治20年代から品種改良が進められ、現在の主力である紅映(べにさし)や剣先(けんさき)が誕生し、優良多産の梅として栽培面積を広げた。
明治・大正の頃までの西田地区は交通の便が悪く、湖を渡る舟が主な移動・運搬の手段だった。早朝、青梅を舟に乗せ、主に女性が櫓(ろ)を漕ぎながら「梅運び唄(梅売り唄)」を歌い、三方湖から水月湖、浦見川を経て久々子湖畔に上陸。そこからは背に担いだり、荷車を引いて歩き、美浜や敦賀の市場に卸したり民家などに呼び売りをした。
1921年(大正10)、小浜線が若狭路を舞鶴に向けて延伸(翌1922年に全線開通、昨年百周年)したのに伴い、三方駅から貨車で出荷できるようになって、急速に梅の販路が拡大した。
道路整備が進み、車が普及した昭和30年代までは、伊良積と北庄の多くの農家が舟と舟小屋を所有。同50年代以降、三方湖と水月湖畔にコンクリート護岸と農道が整備されるとともに軽トラックが普及し、舟を使う機会は減ったが、舟小屋は昔ながらの景観を伝える観光資源として保存された。
三方湖畔全体で、北庄と伊良積に合わせて10棟の舟小屋が残る。近年、北庄の6棟の舟小屋の近くに駐車場や広場などを備えたポケットパークが整備された。2020年(令和2)には、地元有志によって舟小屋の茅葺き屋根修復に取り組むプロジェクトがスタートしている。
明治・大正の頃までの西田地区は交通の便が悪く、湖を渡る舟が主な移動・運搬の手段だった。早朝、青梅を舟に乗せ、主に女性が櫓(ろ)を漕ぎながら「梅運び唄(梅売り唄)」を歌い、三方湖から水月湖、浦見川を経て久々子湖畔に上陸。そこからは背に担いだり、荷車を引いて歩き、美浜や敦賀の市場に卸したり民家などに呼び売りをした。
1921年(大正10)、小浜線が若狭路を舞鶴に向けて延伸(翌1922年に全線開通、昨年百周年)したのに伴い、三方駅から貨車で出荷できるようになって、急速に梅の販路が拡大した。
道路整備が進み、車が普及した昭和30年代までは、伊良積と北庄の多くの農家が舟と舟小屋を所有。同50年代以降、三方湖と水月湖畔にコンクリート護岸と農道が整備されるとともに軽トラックが普及し、舟を使う機会は減ったが、舟小屋は昔ながらの景観を伝える観光資源として保存された。
三方湖畔全体で、北庄と伊良積に合わせて10棟の舟小屋が残る。近年、北庄の6棟の舟小屋の近くに駐車場や広場などを備えたポケットパークが整備された。2020年(令和2)には、地元有志によって舟小屋の茅葺き屋根修復に取り組むプロジェクトがスタートしている。
2023年4月12日
美浜町レイクセンターがオープン

4月12日に新装オープンの美浜町レイクセンター(美浜町早瀬 0770-47-5960、遊覧船発着場、カフェ、テラス、レンタサイクルあり)と、新規就航の電池推進遊覧船。《休/水曜》
0770-47-5960、遊覧船発着場、カフェ、テラス、レンタサイクルあり)と、新規就航の電池推進遊覧船。《休/水曜》


「梅の里会館」(若狭町成出 0770-46-1501)では、製造直売の梅加工品などが盛りだくさんに並ぶ。
0770-46-1501)では、製造直売の梅加工品などが盛りだくさんに並ぶ。


【参考】『若狭町ふるさと歴史発見』(若狭町歴史文化課・2015年発行)、『三方町史』(三方町・1990年発行)