事業所・関連施設
 原子力事業本部
原子力事業本部
越前若狭探訪
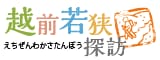



▲ 巨大な門柱が並んでいるように見える門ヶ崎

▲ 左側の遠景は越前海岸、右端は高速増殖原型炉もんじゅ(門ヶ崎展望所から)


▲ 敦賀半島先端近くを横断する敦賀半島トンネル
2020年3月、原子力災害制圧道路として敦賀半島先端近くを横断する県道竹波立石縄間(たけなみたていしのうま)線の敦賀市白木(しらき)― 浦底(うらそこ)間4.9kmが開通した。同区間にある全長3,863mの「敦賀半島トンネル」は、道路トンネルとしては福井県内最長(2番目は北陸自動車道の敦賀トンネル上り線の3,225m)。この新ルート開通で、敦賀半島を周遊する交通の利便性が大幅に向上した。これまで車では、半島西側の美浜町丹生からしか行けなかった敦賀市白木へ、東側の浦底から通行が可能になり、観光面でも期待が寄せられている。
白木の門ヶ崎(もんがさき)は見応えのある風景が広がる。漁港の西側に位置する高さ20~40mの断崖で、方状の節理(せつり)(岩の規則的な割れ目)が見られ、四角い岩塊や鋭く尖った岩峰が幾層にも重なる。約6300万年前にマグマが地下深くで冷えて固まり、地殻変動で地表に現れた黒雲母花崗岩(くろうんもかこうがん)で、波浪や風雨による浸食、崩落がかなり進んでいる。

▲ 門ヶ崎観音(門ヶ崎展望所付近から)
門ヶ崎へは、白木漁港から遊歩道が設けられており、先端の断崖の上にある展望所からは、広く若狭湾と越前海岸が見渡せる。その断崖の中に、門ヶ崎観音と呼ばれる岩塊があり、冠をかぶり錫杖(しゃくじょう)を携えた観音様の姿に見える。永い年月をかけて自然が創り出したものだ。観音様は、白木沖で漁をする人々を見守ってきた。
豊かな海の幸に恵まれながらも、厳しい自然環境のもとで、白木の人たちは共に助け合って暮らしてきた。郷土誌『白木の里』には、その暮らしが克明に綴られている。
昔からの語り伝えとして、夜の漁に男たちが出ている時、突然、南風が山鳴りとともに吹き下ろすと、女たちは急ぎ門ヶ崎付近に集まって焚(た)き火を始め、燃え上がる炎で沖の舟に知らせたという。強風による転覆や、沖に流されて遭難する恐れがあったからだ。

▲ 門ヶ崎の断崖(白木漁港から門ヶ崎展望所に続く遊歩道の先端近くから)
明治から昭和初期にかけて、白木では「磯さし網」が盛んに行われた。男たちが夜中にとってきた魚を敦賀の市場まで運ぶのは女たちの仕事で、重い荷を背負い、未明に白木を出て、敦賀の朝の市場に間に合わせた。
1960年(昭和35)に白木と美浜町丹生を結ぶ林道が開通するまで、白木は〝陸の孤島〞だった。それまで白木の人たちは、丹生への白木峠越えの山道を歩いて行き来した。
当時の一番の心配は、病気になった時。重病人が出ると、海が穏やかなら医者のいる敦賀の町まで舟で運べるが、荒れれば『たんか』に乗せて白木峠を越えたという。大雪の時は各家から人が出て、カンジキで雪踏みをして丹生までの道を確保した。
この区間も、1985年(昭和60)には、高速増殖原型炉もんじゅの建設に伴い、白木トンネル(737m)が開通。峠の下を短時間で走り抜けることができるようになった。白木の人々の暮らしは、道路整備の進展とともに大きな変貌を遂げてきている。

▲ 白木集落と漁港、白砂の海水浴場(門ヶ崎遊歩道から)

▲ 白木の集落内(白城(しらき)神社の鳥居前)

【参考】「白木の里 上・下巻」(橋本昭三著・1978年発行、「日本民俗誌集成 第12巻」〔1997年発行〕にも収載)、
「敦賀市史 通史編 上・下巻」(敦賀市・1985、1988年発行)