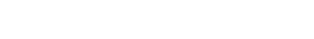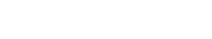

敗戦からの復興にわく日本が、電化元年を謳歌した1953年。その年の12月8日に、アメリカのアイゼンハワー大統領が第8回国連総会で世にも名高い演説を行った。「Atoms for Peace」。原子力の平和利用を訴え、原子力国際プール案(※1)を打ち出したこの演説は、国際原子力機関誕生の出発点となる。 日本では、政府が、原子力発電所開発体制の確立を目指し、さまざまな動きを展開。
産業界とも一体となった取組みは進み、それまでは「次世代の夢」だった原子力発電は電力会社にとって現実的で先進的な「1つの電源」となった。 “くろよん”竣工から3年後の1966年夏、「電力の安全・安定供給」という変わらぬ使命を長期的に果たし続けるための第1歩として、1970年に大阪で開催される「万国博に原子の灯りを」を合言葉に美浜発電所1号機の建設が始まった。

原子力の平和利用を人類の課題として浮上させた、アイゼンハワー大統領による1953年12月8日の演説「Atoms for Peace」。これを契機に、アメリカ、イギリス、ソ連(当時)など先進各国は、原子力発電への第一歩を踏み出していく。
日本でも1954年度政府予算に原子力予算を計上。政府と産業界が互いに呼応しつつ、原子力に関する調査や研究などその利用に向けての準備が進められた。1955年1月にはアメリカ政府が日本政府に対し、実用原子炉建造に向けた技術援助を提案。日本はこれを受け入れ、翌1956年1月には原子力行政の最高審議機関となる原子力委員会を発足させる。産業界も、各種のサポート体制を整え1956年3月に財団法人日本原子力産業会議(通称、原産)を設立。参加企業はその後1年間で600社を超えた。
1957年11月には、電力各社が出資する日本原子力発電株式会社が設立され、原子力委員会の決定に基づく発電用原子炉の導入を推進。1960年1月から茨城県東海村で建設工事が開始され、1965年5月に1号炉が初臨界(※2)に達した。
時は高度経済成長期。子どもたちが読む漫画本の中では、原子の力で動く科学の子、鉄腕アトムが活躍していたこともこの時代を象徴している。

関西電力は、官民一体となった原子力発電開発体制の整備推進の一翼を積極的に担う一方、自社内でも原子力発電に関する取組みを進め、1957年9月には日本の電力業界の先陣を切って社内に「原子力部」を設置。原子力発電所の設計や建設技術を本格的に調査研究する体制を整えた。
早速見えてきた最重要課題の一つは原子炉の炉型の選択だった。先行した日本原子力発電の東海発電所では燃料に天然ウランを用いる炉型が採用されたが、その後、燃料に濃縮ウラン、冷却水や中性子減速材に軽水(普通の水)を用いる軽水炉が大きく進歩。アメリカが濃縮ウランの供与に積極的となったこともあり、関西電力は軽水炉への関心を高めた。
軽水炉には、PWR(Pressurized Water Reactor=加圧水型)とBWR(Boiling Water Reactor=沸騰水型)があり、それぞれに特性の違いがある。PWRは、建設コストが高くなる一方、1次系と2次系が完全に分離されているため、2次系の管理が容易であるという特性がある。
関西電力は、PWRがBWRと比較して割高であるという点を克服できないか追及。粘り強い研究の結果、燃料の使用期間を長持ちさせる手法を考案。総コストの低減につなげ、1966年4月、PWRの採用を決定する。既存の技術に安住せず、より大きく社会に貢献できる道を求めて努力する。そんな関西電力の粘りの姿勢が貫かれたエピソードであった。
一方で、もう一つの重要課題である立地点(原子力発電所の建設地)の選択についても、広範かつ慎重な検討が進められた。1961年には、原子力委員会の長期計画に「関西電力の1号機が1969年10月までに運転開始」となることが盛り込まれ、1962年には、あらゆる条件に恵まれた福井県美浜町丹生地区での建設に向け、道が開かれた。
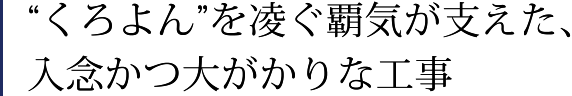
1966年8月、美浜発電所の造成工事が始まった。県道と発電所をつなぐ丹生大橋の建設もスタート。当時の社長・芦原義重に、「この事業に成功するためには、かつての“くろよん”の破砕帯で経験した苦難をはるかに上回る課題に必ず遭遇すると覚悟して、取り組むことが重要である」と言わしめた、新たな難事業の幕開けだった。
商業用原子力発電所の建設・運用は日本で初めてということもあり、特に環境対策や安全問題には徹底した対策を講じる必要があった。なかでも耐震性の確保は、最も重要な責務となる。
関西電力は発電所施設の耐震設計に注力し、災害発生の際にも機器設備の機能が十分維持されることを確認した。当然、原子力発電所の基礎部分の施工などは特に、念には念を入れた大がかりなものとなった。
やがて、原子炉格納容器やタービン建屋が堅牢な姿を現した。「万国博に原子の灯を」を合言葉とする全社の熱意の結晶だ。こうして、1969年4月には格納容器の外部遮蔽コンクリートが完成する。
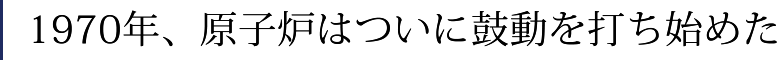
工事は順調に進み、1969年6月には心臓部にあたる原子炉容器が、7月には蒸気発生器が、8月には加圧器が据え付けられ、翌1970年1月の配管配線工事完了をもって1号機は完成した。発電所を建設している間にも急速に進歩した技術を反映し、発電の規模は当初の計画から7万kW増しとなる34万kW。建設から運転開始に要した日数は3年3か月だった。
もちろん、重視したのは耐震性だけではなかった。発電所から排出される気体については、タンクに回収して放射能を減衰させ、無害で排出していることに加え、排水についても、放射能除去の処理を行い基準値以下であることを確認したうえで排出している。また、地元の人々にもあらゆる機会で積極的に建設の進捗状況を報告。発電所建設地区一帯の環境を常時監視するシステムも整備した。若狭湾国定公園に位置する美浜町の風光との調和も大きなテーマだった。例えば、発電所に通ずる丹生大橋のたもとに群生する「根上がりの松」の景観は絶対に残したい。そこで、静岡県の三保の松原地帯の松の専門家にも助言を仰ぎ、古木の保護対策に万全を期した。
一方で、運転開始への準備も進められていた。関西電力は、早くから原子力発電における先進技術の吸収に努め、1957年以降は毎年2名以上の留学生を海外の原子力研究所や原子力発電所などに派遣。1967年12月からは、美浜発電所1号機の運転要員に指名した6名の社員を、導入する原子炉の製造元であるアメリカ・ピッツバーク市のウエスチングハウス社での1年間の実地訓練に送り込んでいる。吸収・蓄積された知識と経験に基づき、1号機が完成するとすぐに各種機器の構造試験、機能試験が繰り返された。そして、1970年7月4日、満を持した状態で原子燃料の装荷を開始。29日、臨界に到達。美浜発電所はついに鼓動を打ち始めた。

美浜発電所1号機の始動後間もない1970年8月8日午前11時過ぎ。静寂が中央制御室を包んだ。班長の指示のもと、呼吸を合わせて操作に集中するスタッフたち。見守る計器の針がふれ、全員が胸中で叫ぶ。「行くぞ、行くぞ、行くぞ。よしっ!…試送電成功。」その瞬間、作業を続ける全員の背中から無言の歓喜があふれ出た。響く電話の声。「ただ今原子の灯を送りました」「ただ今届きました」。午前11時21分、約1万kWの「原子の灯」は、無事、万国博会場に届き、お祭り広場の電光掲示板を通じて一般の来場者たちにも知らされた。
万国博の正式名称は日本万国博覧会。その開催は世界の注目を集め、大阪府千里丘陵の会場には約半年の会期中に6400万人を超える人々が押し寄せた。人類の進歩と調和をテーマとするこの祭典ほど、日本の商業用原子力発電の幕開けを飾るにふさわしい場はなかっただろう。
「万国博に原子の灯を」は、美浜発電所建設を進める関西電力の合言葉となった。その実現に向け、建設現場で汗にまみれてきた社員たちにとっては、万感胸に迫る送電の成功だった。この後も「原子の灯」は、万国博会場をはじめとした関西の電力需要を満たすうえで大きな役割を果たし続ける。
歴史年表の中では万国博の陰に隠れがちな日本初の原子力発電営業運転。しかしその裏には、原子力の平和利用という人類の夢の実現の一端を担う幸運に恵まれ、懸命に奮闘した関電社員たちの、熱い感謝と喜びが刻まれている。