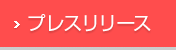プレスリリース
 2009
2009
2009年12月7日
関西電力株式会社
大飯発電所1号機プラント排気筒ガスモニタの一時的な僅かな指示値の上昇の原因と対策について
大飯発電所1号機(加圧水型軽水炉 定格電気出力117万5千キロワット、定格熱出力342万3千キロワット)は、定期検査中の10月12日および19日の、いずれも10時10分頃から約10分間、プラント排気筒ガスモニタ※1の指示値が僅かに上昇しました(最大値は両日とも18.1cps※2。通常値は14.5cps)。また、19日には、原子炉補助建屋内の空気を吸引して測定している放射線モニタ※3の指示値が同時刻に上昇しました。
10月19日までの調査で、モニタが上昇する同じ時間帯で、運転中の2号機の化学体積制御タンク※4の気相部の水素ガスを処理している気体廃棄物処理系統のガス分析装置の自動校正が動作していることが判明しました。
排気筒から放出された希ガスの放射能量は12日および19日の合計で約1.0×109Bqと評価し、保安規定に基づく放出管理目標値(3.9×1015Bq/年)に比べ十分低い値でした。また、発電所敷地内および周辺のモニタリングポストの指示値は平常と変わりなく、周辺環境等への影響はありませんでした。
[以上は平成21年10月19日 お知らせ済み]
また、同2号機は、定格熱出力一定運転中の8月31日、1次冷却材中のよう素(I−131)濃度と希ガス※5濃度が前回の測定値を上回ったため、燃料集合体に漏えい※6が発生した疑いがあるものと判断しました。その後、10月6日頃から希ガス濃度が上昇傾向にあったことから、漏えい燃料の特定調査を実施するため、10月21日に原子炉を停止しました。
なお、2号機は原子炉停止後、1次冷却材中の放射能を低減させた後、原子炉容器上部ふたを取り外し、12月4日から燃料集合体を取り出す作業を行い、12月7日からはシッピング検査※7を実施しています。
- ※1 運転に伴って発生する気体放射性廃棄物(希ガス)を監視するモニタ。大飯1号機ではプラント排気筒で原子炉格納容器および補助建屋からの排気を監視している。
- ※2 1秒間に測った放射線の数を表す単位。
- ※3 気体廃棄物処理系統の換気空調系ガスモニタ(通常は常時測定しているものではないが、10月12日以降、常時計測する設定に変更していたもの)。
- ※4 化学体積制御系の設備で、原子炉容器や配管内の1次冷却材の量を調整するためのタンク。
- ※5 ウランの核分裂反応で生成するキセノン等のガス。
- ※6 燃料ペレットを収納している燃料被覆管から漏えいがあると、燃料被覆管内のよう素や希ガスが1次冷却材中に放出される。このため、1次冷却材中のよう素や希ガス濃度の変化から、漏えいの有無を判断している。
- ※7 燃料集合体から漏れ出てくる気体および液体に含まれる核分裂生成物(キセノン-133、よう素-131等)の量を確認し、漏えい燃料集合体かどうか判断する検査。
- 1.調査結果
-
- (1)気体廃棄物処理系(1・2号機共用)の運転実績の調査
-
- ・大飯1・2号機では、運転中、1次系の化学体積制御タンクの気相部(水素ガス)を定期的に取り出し、ガス圧縮機および水素再結合装置を循環しながら、放射性気体廃棄物処理系のガス減衰タンクに圧縮し貯留しています。この際、水素ガスは水素再結合装置にて水にすることで貯留するガスの容積を小さくしています。
- ・大飯2号機では、8月31日、燃料漏えいの疑いが発生したことから、翌日から、1次冷却材中に含まれる放射性ガス(希ガス)濃度が上昇していくのを抑えるため、気相部の取り出しを連続して実施していました。
- ・水素再結合装置は、2系列(A、B)あり、通常は一系統を運転しており、9月1日からの処理ではB系を使用していました。
- ・水素再結合装置では、水素濃度に応じて酸素量を適切に調整する等のため、装置の入口側と出口側での水素濃度及び酸素濃度を分析(ガス分析装置)しています。
- ・この分析装置では、各濃度の検出計を定期的に自動校正※8する仕組みが備わっており、今回、プラント排気筒ガスモニタが上昇した際には、入口側の酸素濃度計で自動校正が行われていました。
- ※8 入口酸素濃度計は、タイマーにより168時間(7日)毎に約10分間、自動校正(計器のゼロ点調整とスパン調整)が行われるように設定されていた。
- (2)ガス分析装置の入口側酸素濃度計の調査
-
- ・酸素濃度計の自動校正は、以下の順序で弁等が自動操作されます。
 水素再結合装置につながる入口弁を閉じた後、窒素ガスを流して濃度計内に残留しているガスを廃棄物処理系(ガス圧縮機側)に排出します。
水素再結合装置につながる入口弁を閉じた後、窒素ガスを流して濃度計内に残留しているガスを廃棄物処理系(ガス圧縮機側)に排出します。 出口弁をガス圧縮機側から排気筒側(1号機)に切り替えて、校正用ガス(窒素、一定濃度の酸素)を流して自動校正を行います。
出口弁をガス圧縮機側から排気筒側(1号機)に切り替えて、校正用ガス(窒素、一定濃度の酸素)を流して自動校正を行います。
- ・これら一連の動作に関係する弁等について、校正作業中の圧力状態を模擬した漏えい試験を行ったところ、ガス圧縮機側出口弁でわずかな漏れが認められました。
- ・酸素濃度計の自動校正は、以下の順序で弁等が自動操作されます。
- (3)入口酸素濃度計のガス圧縮機側出口弁の調査
-
- ・当該弁は、弁体の自重とバネ力により、弁体先端のゴム製シート部を弁座に押しつけて閉止する構造となっています。
- ・通常当該弁は開となっていますが、自動校正中(排気筒側への切替時)には、弁は閉となります。この際、弁体で締め切られた下流側はガス圧縮機側の圧力は高く、弁体の上流側(排気筒側)は大気圧となり、この圧力差で弁体が持ち上げられる方向に働き、シート部の押しつけ力が弱まることがわかりました。
- ・ガス分析装置の弁は平成11年の定期検査で取替えを行い、その後は動作確認を行っていました。
- ・原因調査として実施した分解点検の結果では、バネや弁座等の構成部品に異常は認められませんでしたが、ゴム製シート部の弁座とのあたり位置にできる凹みが若干深く、幅広くなっていることや、ゴムが若干硬化していることを確認しました。
- ・A系の同じ弁について確認したところ、自動校正装置設置当初※9から弁閉止時に弁体を押し付ける方向に設置されていました。(弁の取り付け方向がB系とは逆)
- ※9 B系は昭和61年、A系は昭和62年に取替えられ、自動校正となった。
- 2.推定原因
-
- ・1号機プラント排気筒ガスモニタが上昇した原因は、燃料漏えいに伴い通常より高い濃度となっていた2号機の放射性ガス(希ガス)を処理していたB−水素再結合装置で、入口酸素濃度計の自動校正時に、ガス圧縮機側出口弁のシート部に漏れが発生し、放射性気体廃棄物処理系統内の高い濃度の希ガス※10が、1号機プラント排気筒から放出されたためと推定しました。
- ・出口弁のシート部の漏れは、当該弁が閉止した状態で、弁体を押し上げる圧力が作用するような方向になっていたためと推定しました。
- ※10 2号機の希ガス濃度は10月上旬から、それまでの値より約5倍(2260Bq/cm3 → 9700Bq/cm3)上昇していた。
- 3.対 策
-
- ・当該弁を新品に取り替えるとともに、その設置にあたっては、自動校正中にシート漏れが起きない向きに取り付けました。(B系のみ)
- ・濃度計(全4台)のプラント排気筒側への排出ラインは栓をして使用しないこととし、自動校正用ガスは全てガス圧縮機側に排出し、気体廃棄物処理系で処理することとしました。(A,B系とも)
なお、今回の調査の一環として、ガス分析装置の配管からの漏れを確認するため、より精度の高い漏えい検査(ヘリウムリークテスト)を行ったところ、配管継手部3箇所(入口酸素濃度計、入口水素濃度計、出口水素濃度計の各々1箇所ずつ)からごく僅かな漏れが認められたため、継手部の増し締めを行い漏えいは停止しました。また、自動校正動作の確認を行ったところ、濃度計内に残留した放射性ガスを廃棄物処理系に排出するための時間設定が短く、残った放射性ガスがわずかに排気筒側に排出される可能性があることがわかりました。
これらの影響については、漏れ量が極微量であることや、排気筒モニタの有意な変動がないことなどから、周辺環境への影響はないと評価しました。
なお、ガス分析装置においては、今後の定期検査時に従来から実施している窒素ガスによるリークテストに加え、ヘリウムガスによるリークテストを行うこととしました。また、今回の事象の対策として排気筒側への排出ラインを閉止することから、残った放射性ガスが排気筒に放出されることはありません。
今回の事象を受けて、B系の後に設置されたA−水素再結合装置のガス分析装置を確認したところ、自動校正中にシート部の漏れが起きないように弁の取り付け方向を配慮しており、B系の当該弁については、その配慮が反映されず、今回の事象に至るまで取り付け方向が改善されていませんでした。
このことを踏まえ、放射性ガスの放出にかかる系統設備について、設備設計に問題がないかを設計根拠や実際の設備動作等を書類及び現地調査により確認していきます。
以 上