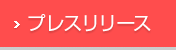プレスリリース
 2007
2007
2007年3月16日
関西電力株式会社
美浜発電所1号機余熱除去系統サンプリングラインの溶接事業者検査手続き漏れの原因と対策について
美浜発電所1号機(加圧水型軽水炉 定格電気出力34万キロワット、定格熱出力103万1千キロワット)は、平成18年11月1日より第22回定期検査中ですが、平成19年2月16日、今回の定期検査で実施した余熱除去系統※1サンプリングライン※2の溶接形状変更工事において、溶接事業者検査※3を実施していない箇所が2箇所あることが判明しました。
美浜発電所1号機では、前回定期検査に引き続き、今定期検査で大飯発電所3号機の事象の水平展開として133箇所(当該2箇所を除く)の溶接形状変更工事を行っています。
当社は、溶接事業者検査が電気事業法に基づく重要な手続きであるにも関わらず、手続き漏れが発生したことを重大な問題と捉え、2月19日に社内に「溶接事業者検査手続き問題対策検討会」を設置し、同検討会および社内のトラブル対策委員会において、原因の究明および再発防止対策の検討を行ってきました。
当該サンプリングラインについては、現在、溶接事業者検査を実施中であり、今後、監督官庁のご指導を賜りながら、適切に対応してまいります。
なお、当該部の配管取替作業は3月中旬頃に完了する見込みであり、その後、燃料装荷、原子炉容器組立ておよび必要な定期事業者検査を実施後、原子炉を起動し、調整運転を開始する予定です。
| ※1: | 余熱除去系統 |
| 原子炉を停止した後の炉内の燃料の余熱を除去する系統であり、事故時に原子炉を冷却する機能も有している系統。 | |
| ※2: | サンプリングライン |
| 配管内流体を分析するために試料採取装置へ導くための系統。 | |
| ※3: | 溶接事業者検査 |
| 電気事業法第52条に基づいて、溶接部の健全性を確認するために、事業者が溶接検査を実施するとともに、独立行政法人原子力安全基盤機構に溶接安全管理審査を申請し審査を受ける。 |
[平成19年2月16日 お知らせ済み]
当該工事は、平成17年3月に発生した大飯発電所3号機の加圧器気相部サンプリングラインからの1次冷却水漏えい事象の水平展開※4として、余熱除去系統サンプリングラインの第一弁の下流配管の溶接形状を変更するとともに、溶接時の作業性を考慮し、第一弁とその上流側配管をあわせて取り替えたものです。美浜発電所1号機では、前回定期検査に引き続き、今定期検査で大飯発電所3号機の事象の水平展開として133箇所(当該2箇所を除く)の溶接形状変更工事を行っています。
| ※4: | 漏えいの原因が初期の溶接不良であったことから、各発電所では至近定期検査で現場調査を実施し、5定期検査以内に類似箇所の溶接形状変更工事を実施することとした。 |
当社は、溶接事業者検査が電気事業法に基づく重要な手続きであるにも関わらず、手続き漏れが発生したことを重大な問題と捉え、2月19日に社内に「溶接事業者検査手続き問題対策検討会」を設置し、同検討会および社内のトラブル対策委員会において、原因の究明および再発防止対策の検討を行ってきました。
| (1)発見に至った経緯 | |||||||||||||||||||||||||
| サンプリングライン溶接形状変更工事について、次回定期検査の工事計画立案のため、メーカーが当該サンプリングラインの図面を確認していたところ、当該箇所で溶接事業者検査が未実施であることが判明しました。 | |||||||||||||||||||||||||
| (2)調査結果 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| (3)推定原因 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| (4)対 策 | |||||||||||||||||||||||||
| 本件を受けて、速やかに、原子力事業本部長から原子力関係の社員に対し、文書 で、法令遵守の再徹底について指示しました(2月20日実施済み)。 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
当該サンプリングラインについては、現在、溶接事業者検査を実施中であり、今後、監督官庁のご指導を賜りながら、適切に対応してまいります。
なお、当該部の配管取替作業は3月中旬頃に完了する見込みであり、その後、燃料装荷、原子炉容器組立ておよび必要な定期事業者検査を実施後、原子炉を起動し、調整運転を開始する予定です。
以 上