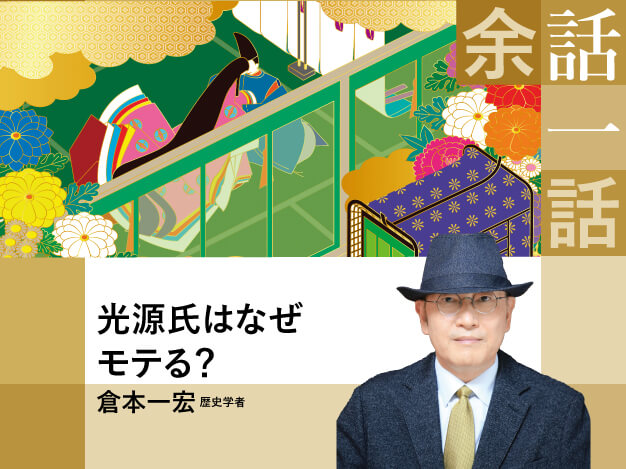エネルギー自給率向上、ウクライナ問題に伴う資源高、二酸化炭素(CO2)排出削減への対応に迫られています。この3つの課題に対し、一定の役割を果たすのが原子力発電です。安全性向上対策を着実に進める関西電力美浜発電所を、フリーキャスターの伊藤聡子さんが訪れました。

PRセンターを見学する場面
自給率、資源高、脱炭素
課題応える役割注目
日本のエネルギー自給率はわずか12%で、ほとんどを輸入に頼っています。東日本大震災以降、国内の原子力発電所が停止し、火力発電が大幅に増加。電力会社はLNGや石炭の追加調達を余儀なくされました。さらに昨年2月以降、ウクライナ情勢が緊迫化。欧州がロシアからの天然ガス輸入を削減し、代替としてLNG需要が増加したため、日本の調達環境が悪化しました。そこに円安の進行も重なり、燃料費の高騰が続いています。一方で地球温暖化の原因となるCO2排出量の削減も喫緊の課題です。
脱炭素の機運が高まり、同時にエネルギー安全保障の動きが強まる中、原子力発電の役割に注目が集まっています。政府は2030年の電源構成(エネルギーミックス)について、原子力発電比率を20~22%と定めましたが、その達成には安全性を確認した原子力発電所の運転再開が必要です。2月に閣議決定されたGX(グリーントランスフォーメーション)実現に向けた基本方針では「原子力規制委員会による安全審査に合格し、地元の理解を得た原子炉の再稼働を進める」と明記しています。
政府は20年10月に50年までのカーボンニュートラルを宣言。関電は21年2月にゼロカーボンビジョン、22年3月に具体策や目標を定めたロードマップを策定しました。発電によるCO2排出量は、25年度時点で13年度比の半減を目指します。そのために欠かせないのが原子力発電の安全・安定運転の継続です。ロードマップでは、グループ自らの原子力の取り組みとして、安全最優先を大前提に原子力の最大限の活用に向け、「運用高度化」「新増設・リプレース」「水素製造への活用」を重点項目に掲げました。

高畠 勇人 所長
原子力規制委員会の審査に合格し、40年超運転のプラントとして国内初の再稼働を果たしたのが美浜発電所3号機です。高畠勇人所長は、発電所を訪れた伊藤さんに原子力発電の役割を解説。発電に使うウラン燃料は、産油国のように偏在していないことや、運転開始後13カ月間、補充せず利用できる利点などを説明しました。
伊藤さんは「この数カ月、大事なエネルギーの根幹を海外に頼っていたと知り、危うさを痛感した。安定供給できる施設があることで、日本の成長も電気のある暮らしも維持できているのですね」と応えました。
廃止措置先駆者へ
安全対策重ね稼働
美浜発電所は3号機が1976年に営業運転を開始。東日本大震災後に定期検査入りし、その後は停止していましたが、安全性向上対策工事などを経て21年6月に再稼働を果たしました。1、2号機は15年4月に廃止。PWR(加圧水型軽水炉)の廃止措置でパイオニアを目指しています。
伊藤さんはまず、廃止措置中のプラントに足を運びました。1号機では原子炉格納容器の中に入り遮蔽壁の厚みなどを確認。2号機のタービンが解体・撤去された建屋では、作られた蒸気の流れについて高畠所長から「美浜発電所はPWRのプラントで、放射性物質を含まない二次冷却水を蒸気にしてタービンに送っています。BWR(沸騰水型軽水炉)では放射性物質で汚染されたタービンもPWRでは汚染されていないので、すでに構外に搬出済みです」と説明を受けました。こうしたものは可能な限り再利用する方針で、福井県では廃止措置がビジネスとして確立できないかという検討が「嶺南Eコースト計画推進会議」で進められています。伊藤さんは「貴重な資源もたくさん使われていると思いますから、うまくリサイクルされるといいですね」と期待を示しました。

廃止措置中のプラントも見て回った
稼働中の3号機については、新規制基準に対応した竜巻対策や、増大した基準地震動に耐えられる構台など安全性向上対策を見学。「思ったよりも大がかりですね」と驚いた様子で「地面を岩盤まで掘り返すなど想像を超えるスケールでした。これを完成させるモチベーションは相当なものだったのではないでしょうか」と作業員の苦労に思いを巡らせていました。
その後、中央制御室に設置された最新の操作・監視盤も視察。事故対策を検討・決定するための緊急時対策所では、必要な資機材や通信連絡設備を見て回りました。

事故対策を検討・決定するための緊急時対策所も視察
美浜発電所は、04年8月9日に発生した3号機の二次系配管破損事故の反省と教訓を心にとどめるため、毎月9日を「安全の日」に定めています。高畠所長は原子力利用について「安全が大前提で、それを確保するのが私たちの仕事」と強調。視察時には訓練中の作業員とも出くわし、伊藤さんは「訓練は年間を通じて計画されており、こうした積み重ねが安心材料になります」と話していました。
未来のために…現場の責任感
「原子力発電所の安全な解体に向けた模範」。視察を終えた伊藤さんは、廃止措置作業が進む1、2号機をこう表現しました。「責任も大きく、技術的にも大変だと思いますが、先導してもらいたい」。1、2号機は45年度の廃止措置完了を目指しています。
国内初の40年超のプラントとなった3号機の安全性向上対策工事については「安全性あっての原子力で、何も知らなければ漠然とした不安で揺れ動いてしまう」と指摘。具体的にどういった対策が取られているのか、積極的に発信していく必要性にも言及しました。
「現場から声が上がりやすい雰囲気作りも大事ですね」。視察の合間、高畠所長が現場作業員とフランクにコミュニケーションをしていた場面も印象的だったと伊藤さんは振り返りました。最後に「万が一に備えて訓練を続け、責任感を持って業務に当たっていることがわかりました。大変な仕事だと思いますが、日本の未来のためにがんばってください」とエールを送りました。

- 伊藤 聡子 いとう さとこ
1967年7月3日生まれ。大学在学中からキャスターとして報道番組などに出演。
地方創生や企業経営、エネルギー、地球温暖化などをテーマに幅広く活動している。
経済産業省総合資源エネルギー調査会など、国の委員会にも参加。事業創造大学院大学の客員教授を務める。
(3月17日付 電気新聞より転載)
![YOU’S[ユーズ]](/corporate/report/yous/images/header_logo.png)