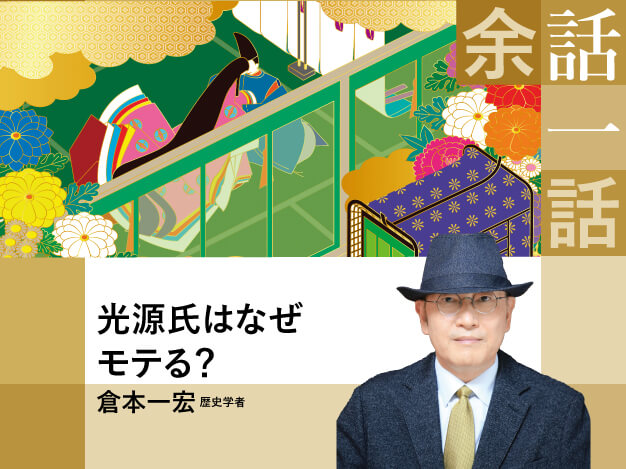脱炭素の機運が高まり、再生可能エネルギー拡大の流れが加速している。関西電力は2022年3月に策定した「ゼロカーボンロードマップ」で国内の再エネ開発に1兆円規模を投じる方針を示した。40年までに新規開発500万キロワット、累計開発量900万キロワット規模を目指す。柱となる洋上風力発電は、ローカル5Gを活用した点検画像伝送技術の実証に着手。脱炭素に向けた重要な基幹電源に位置付ける水力発電は監視業務の集約化を進めている。

成長見据え監視を集約化
ゼロカーボンビジョン達成に向けた重要な基幹電源が水力発電所だ。CO2排出を抑えるだけでなく、少資源国の日本にとって貴重な純国産エネルギーとなる。素早く起動・停止でき、時々刻々に変化する電力需要の対応に優れる。
関電は近畿、東海、北陸の3エリアで合計152カ所・出力824万8千キロワットの水力発電所を運用している。その遠隔監視・制御を担う総合水力制御所が2022年3月、大阪市に開所した。
これまでに東海、北陸エリアの72カ所の発電所を取り込み、遠隔監視をスタート。近畿エリアの一部も対象に加わる計画だ。
24年7月までに同エリアの滋賀、奈良、和歌山の各給電制御所が管轄する発電所なども集約し、全ての水力発電所が、大阪市の総合水力制御所での運用に切り替わる。
監視・制御業務を集約化し、運用の効率化や需給逼迫時などの供給力調整を一元化することで機動性も高まる。近年は電源の非化石価値なども求められており、水力発電を有効に活用しながら発電事業の成長につなげる。

22年3月に開所した総合水力制御所
洋上風車、
ドローン点検を高度化
ローカル5G(第5世代移動通信方式)とドローンを活用し、洋上風車のブレードの点検画像を伝送する技術の実証が進んでいる。現状のドローン点検は洋上風車を撮影した機体が帰還した後に記録媒体を回収。それを監視センターで解析している。状況によっては再飛行が必要なこともあり、作業効率面で課題があった。洋上風力発電での実用化を見据える関電は昨年6月、総務省が公募した実証事業に参画。成果を踏まえ、実際に導入した場合の費用対効果などを評価する。
洋上風力発電は、建設・運用・撤去を含むライフサイクルコストの3割以上を運転保守費用が占めると言われる。洋上風力の導入拡大によりメンテナンス需要の急増が予想されるため、設備損傷や異常を即時確認・解析できる効率的なシステムの確立を目指す。海底ケーブルを敷設し、洋上ウインドファーム内にローカル5G環境を整備できれば点検画像の撮影、分析が同時に進められるようになる。点検完了までの発電停止時間を最小化し、設備利用率を向上させる。
昨年12月に実施した実証事業には秋田ケーブルテレビを代表機関とする8者のコンソーシアムが参加。ユーラスエナジーホールディングスのユーラス秋田港ウインドファーム(総出力1万8千キロワット)で高精細画像をリアルタイム伝送できるか確かめた。
サービスとして成立するには収支計画だけでなく、海上での電波活用に関する規制緩和も必要だ。こうした課題の解決に向けて、コンソーシアムとの協力も強める。

洋上風車の点検画像伝送技術の実証
社員インタビュー①
脱属人化へデジタルが鍵

再生可能エネルギー事業本部
総合水力制御所 新宮諄
全水力発電所の年間発電計画の策定を担当している。発電実績や翌年度に計画されている点検などの作業を踏まえて供給量を計算。貯水池の年間発電計画では、電力需要が高まる夏や冬に向けて貯水し、梅雨時期など降雨が予想される場合には事前にダムの水位を下げる。貯水池からの放流は水系全体の供給力を左右するため、河川全体を意識した運用を心掛ける。
デジタル技術を活用した水力の運用にも挑む。需要や水量に応じてできているかを可視化。運用実績を確認できるような仕組みを構築し、ばらばらのデータの関連性を評価する取り組みを進めた。水力発電所の運用は、運転員の経験や判断が大きなウエートを占めてきた。一方、脱炭素にはより高度な運用が求められる。「脱属人化が必要で、さらなる高度な運用にはデジタル化が必須だ」と強調する。
入社7年目を迎えた。記憶に残るのは2018年、記録的な豪雨により浸水した発電所復旧作業だ。水力発電所の被害状況を確認するため第一陣として向かった際、現場に浸水状況を記録するテープを貼った。1時間後に現場を訪れるとテープが見当たらず晴天だったこともあり「はがれた」と認識したが、実際は水位が上昇して貼ったテープが水没していた。「災害は刻々と状況が変化する。思い込みの恐ろしさを知った」。この経験から、日々の業務でも先入観を持たずに多角的な視点で物事を見極め、自分が担う仕事の本質を理解するため問い続けることを忘れない。急速に変化するデジタルの世界に追従できるよう、社内でのDX(デジタルトランスフォーメーション)研修を積極的に受講。自身のアップデートも欠かさない。
社員インタビュー②
多彩な職歴、風力に生かす

再生可能エネルギー事業本部
技術グループ 藤原悠祐
洋上風力発電全般の技術分野を担当している。着床式洋上風車の開発に必要な地盤・風況調査や基礎設計がいまの中心的な業務だ。「その風車のレイアウトでどのくらいの発電量が見込めるか」。並べ方一つとっても収支に大きく関わってくる。FIP(フィード・イン・プレミアム)制度への移行を見据え、翌日の発電量予測モデルの構築も検討する。
海象条件は欧州より日本のほうが厳しい。特に多いと言われるのが冬季雷だ。
「日本海側には欧州と比較にならないほど落ちる。海外の知見ばかりを鵜呑みにはできない」。国内で運転を開始している洋上風力発電所は少なく、どう計画を練るかが課題だ。
建築技術者として2011年に入社。原子力発電所の設計審査、南海トラフ巨大地震に備えた防災計画策定、耐震技術アドバイザーとして日本原燃に出向など12年で8つの職場を経験。様々な企業や職種と議論を交わしてきた。
ローカル5Gを活用した実証にも参加。これまでは発注者として受注者と仕事をすることが多く、企業がそれぞれの強みを持ち寄り一つの目標に向かっていく仕事は初めてだった。「会社の文化の違いで意見が食い違うこともあるが、落としどころを見つけプロジェクトを前進させることは新鮮で楽しかった」
18年の台風21号襲来時は非常災害本部で事務局の担当者だった。いま手掛けている洋上風力も自然を扱う部分があるため「防災面の知識や地震に関する評価も必要になる」と話す。
(3月15日付 電気新聞より転載)
![YOU’S[ユーズ]](/corporate/report/yous/images/header_logo.png)