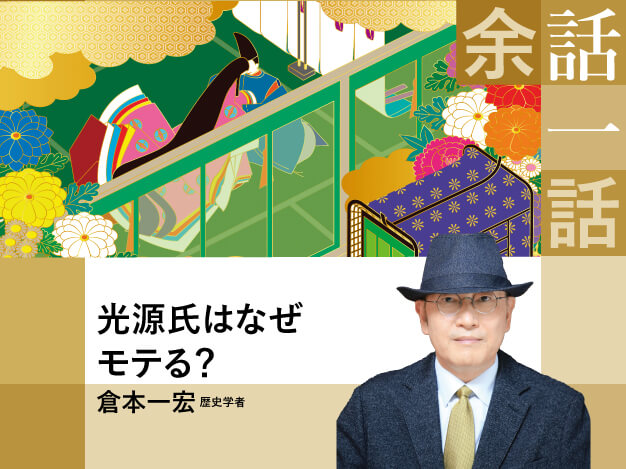脱炭素機運の高まりにより、水素社会実現に向けた動きが国内外で加速している。関西電力は昨年5月に水素事業戦略室(室長=桑野理執行役員・ソリューション本部副本部長)を設立。「戦略」「技術開発」の2グループ体制だったが、今年7月に国際グループを新設し、戦略グループが担っていた海外プロジェクトに関する機能を強化している。ゼロカーボンシリーズ特集の第2回は、同社の水素事業の位置付けや本格化する技術開発の動向を紹介する。
専門部署の体制拡充幅広く目配り、海外強化
関電は2021年2月に「ゼロカーボンビジョン2050」を策定。事業活動に伴う二酸化炭素(CO2)のゼロ排出を目指す取り組みの一つとして「水素社会への挑戦」を掲げた。サプライチェーン構築の準備を進めるため、事業可能性評価(FS)に参画しており、実証事業へ展開していく。
海外からの水素調達は25年頃から徐々に開始する計画。30年をめどに安価な水素を本格的に輸入できるようにし、ゼロカーボン燃料として火力発電所で活用する。また、水素を製造し、運輸・産業分野向けに販売するなど、事業拡大していく。
昨年5月に発足した水素事業戦略室は、水素ビジネスを効率的に進めるとともに、事業戦略の検討・立案や実証判断など関電の水素事業を一元的に手掛ける。発足当初は31人体制だが、水素社会の実現に向けた取り組みを加速させるため、積極的なキャリア採用を含めた要員増強などによる組織強化を図っており、現在は57人体制となっている。

戦略グループは事業戦略の策定・統括、渉外・広報対応、水素の普及開発に向けた対応を担う。技術開発グループは技術調査、水素の製造や発電分野に関する役割を担当。国際グループは海外で製造した水素を輸送するプロジェクトへの投資や国内の受け入れ量などを検討する。
関電は戦略室発足以前から様々なビジネスに参画してきた。04年には岩谷産業と共同で液化水素などの製造販売会社ハイドロエッジ(堺市)を設立。関電グループとして、液化水素の製造に関するノウハウを取得している。
水素バリューチェーン推進協議会や神戸・関西圏水素利活用協議会をはじめ外部の水素関連団体にも参画するなど国や様々な事業者と一体となり、水素事業を推進している。
水素社会を構築するため、短期的には幅広くFSや実証事業などに関与し、同社の強みである発電で需要を創出。安価な水素を海外から調達して販売し、収益を拡大していく方針だ。長期的には国内の再エネや原子力発電を活用した水素製造事業者を目指す。
NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)のグリーンイノベーション基金事業では、既設火力発電所での水素混焼・専焼に向けたプロジェクトが動き出した。23年度に設計を開始。25年度の実証運転開始を目指す。また、姫路第一発電所と姫路第二発電所をターゲットに、30年からの大規模な水素混焼発電開始を検討している。
水素サプライチェーン確立に向けた動きも本格化している。岩谷産業や川崎重工業、丸紅などとオーストラリアで製造した水素を液化し、日本に輸出するプロジェクトの事業化に向けた調査を昨年開始。31年以降には日量800トン規模の水素製造を想定する。
関電は政策支援の制度設計議論を注視しつつ、受け入れ拠点を姫路エリアとした水素サプライチェーンを構築するため、他社と協業しながらファーストムーバー(先行者)を目指す。
※ファーストムーバー(先行者)
ある市場において、他社に先駆けて投資や技術、製品・サービス提供を行い、事業基盤を作る企業。水素・アンモニア供給インフラの整備について、経済産業省はサプライチェーン早期立ち上げの後押しやリスクの高さの観点から、先行者を手厚く支援する制度設計を検討している。
NEDO事業を受託~製造から利活用を想定
関西電力は、水素の製造から利活用までを想定した事業可能性調査(FS)を兵庫県と熊本県で開始した。兵庫県では淡路島で、系統蓄電池と水素製造を組み合わせて島内で活用する、国内初の事業モデル構築を目指す。熊本県小国町では関電も出資する「わいた地熱発電所」(地熱、1995キロワット)周辺の未利用の地熱資源を活用し、再生可能エネルギー由来のグリーン水素を製造するモデル構築を検討する。
それぞれNEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)の委託先に採択された。調査期間は1年。事業化の可能性があると判断されれば実証試験に進む。
兵庫県の淡路島では再エネ由来の電力が豊富であるため、これらをより活用し、蓄電池への充電と水の電気分解による水素製造を行う運用モデルを検討する。蓄電池の容量は1万~2万キロワット時程度、水素製造量は毎時150~400ノルマル立方メートル程度の製造を見込む。製造した水素は燃料電池車(FCV)や商業店舗内の運搬機器、農業機械での利活用を想定する。30年代の事業化を目指す。

熊本県の小国町では未利用の地熱エネルギーを活用し、水素を製造する事業を検討する。今回、水電解で検討するSOEC(固体酸化物形水電解セル)は熱を利用することで、一般的な水電解方式であるアルカリ型や高分子型水電解よりも水素製造効率が向上する。このため、水電解装置へ地熱の熱を供給した高効率な水素製造という国内初の製造モデル構築を目指す。機器自体の高効率化に加え、ヒートポンプ技術なども組み合わせて地熱の利用率を高め、より水素製造効率を向上させたい考えだ。製造した水素は周辺地域の産業や災害時の電力供給などでの利活用を想定する。
いずれの事業も関電が代表事業者を務める。兵庫県の事業は淡路市、洲本市、南あわじ市で調査を進め、兵庫県や岩谷産業などが参画する。熊本県での事業は小国町周辺で行い、関電プラント(大阪市、北村仁一郎社長)が熱交換器や蒸気配管設計、東芝エネルギーシステムズは水素製造装置や地熱発電設備の設計、岩谷産業が水素貯蔵や輸送の設計を担う。
社員インタビュー①「採算性が鍵、価値創出を」

水素事業戦略室技術開発グループ 岩田英範
入社以来、水力部門を歩んできたが、自ら希望して昨年4月から水素事業に携わることになった。「水力からもう少し幅を広げ、新たな電力需要先でもある水素の経験を積むことで、自分にも会社にも大きな武器になる」。技術開発チームでは水素製造のプロジェクトを担当する。
社会のニーズを予測し、近い将来に採算性が成り立つモデルの構築を目指す。目下の課題は二酸化炭素(CO2)排出削減に対する価値が現時点では不十分な点だ。燃料を水素に転換することで機器の性能が向上するなどの利点は少ないため、CO2削減に対する価値が大きくならない限り、化石燃料と比較して採算性に劣る。
今年に入り、2件の水素の製造から利活用まで想定した事業可能性調査(FS)を提案し、採択が決まった。「FSではCO2削減だけでなく、新たな付加価値を創り出すことで事業の価値をより高めていきたい」と話す。
長く歩んだ水力部門では、工事設計や工程管理、現地検査などを手掛ける工事業務に携わってきた。
17~19年にはラオスのナムニアップ水力発電所の建設業務にも参加した。水素プロジェクトは複数の事業者が共同で進める必要があるため、各社の業務役割分担やスケジュールを決めるプロセスが重要になるが、「今までの経験がFSでの役割分担や工程の組み立てに生きるはず」と期待する。
社員インタビュー②「国際事業、目利き力磨き」

水素事業戦略室国際グループ 水野初季
水素サプライチェーン構築や上流事業への投資を加速するため、今年、国際グループが設置された。「まさに黎明(れいめい)期にある事業分野。各国の企業などと切磋琢磨しながら、できるだけ安く効率的に、よりCO2排出量の少ない水素を探し出して日本に持ってきたい」。海外製造・輸入プロジェクトの掘り起こしに力を入れる。
水素需要の拡大を見据え、世界中でプロジェクトの開発が進んでおり、「なるべく多くのプロジェクトに触れながら目利き力を高めたい」と話す。いま、メインで担当するオーストラリアは、ブルー水素の原料である化石燃料に加え、風力や太陽光など再生可能エネルギーの適地にも恵まれグリーン水素のポテンシャルも高い。
その土地の特性や政治の状況も踏まえ、現地のエネルギー企業やメーカーと知恵を出し合いながら開発を進める。
昨年、水素事業戦略室に配属になる前は、5年ほど国際事業本部を経験。再エネ普及のための国際協力プロジェクトやワークショップで小さな島国を巡った。事業開発では英国のトライトンノール洋上風力、フィンランドのピーパリンマキ陸上風力をはじめとした再エネ事業に多く携わり、投資参画などに関わる協議を進めた。「水素事業ではよりアーリーステージの話が多くなるが、これまでの国際事業の知見を生かしたい」と意気込む。
(9月20日付 電気新聞より転載)
![YOU’S[ユーズ]](/corporate/report/yous/images/header_logo.png)