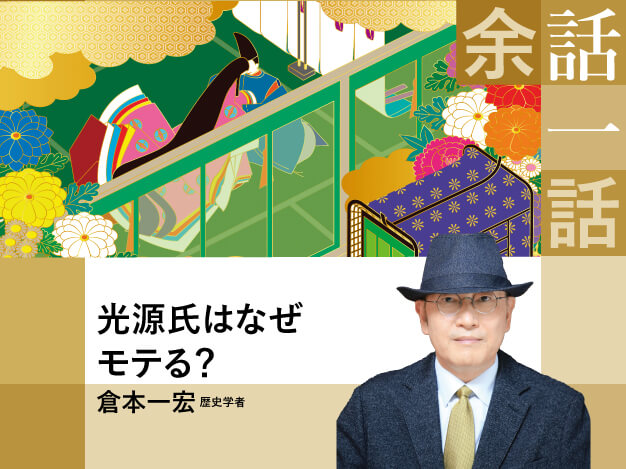発電利用だけでなく、産業、医療、科学など様々な分野で活用される原子力。次世代原子炉開発の現在地や原子力の科学、産業分野での活用など、関西地域の動きを追った。
三菱重工業|将来のエネルギー安定供給に向けて 次世代原子炉開発

革新軽水炉 SRZ-1200イメージ
2050年のゼロカーボン達成に加え、ウクライナ危機による燃料価格の高騰やエネルギーセキュリティの観点から、世界各国で原子力の重要性が見直されている。日本でも準国産エネルギーである原子力に対する社会の期待が高まり、活用に向けた動きが加速している。

地震、津波等自然災害への耐性を強化
こうしたなか、将来を見据えた次世代軽水炉の開発が進んでいる。神戸市にある三菱重工業原子力セグメントがその拠点だ。関西電力など電力4社と共同開発する120万kW級の革新軽水炉「SRZ-1200」は2030年代半ばの実用化を目指す。福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえ、「既設の加圧水型軽水炉(PWR)で強化したシビアアクシデント対策に加え、炉心損傷に備える対策もより高度に設計に織り込み、安全性、信頼性は革新的に進化している」と話すのは、原子力技術部次長の西谷順一さんだ。

多層、多様な手法でサイバー脅威から防御
SRZ-1200は地震、津波など自然災害への耐性やテロ、サイバー攻撃、航空機事故など外からの脅威に対するセキュリティを強化。加えて万が一の重大事故に備えて、溶融デブリを格納容器内で確実に保持・冷却するコアキャッチャを設置。さらに、放出される放射性物質の量を低減し、影響を発電所敷地内に留めるシステムの設計にも取り組む。さらなる再エネの拡大を見込んで、電力需要の細かい変化に合わせた出力調整機能も盛り込み、電力系統の安定化に貢献する。
このほか三菱重工業では、分散型小規模電源として30万kW級の小型モジュール炉、離島やへき地で使用するマイクロ炉、水素製造に適した高温ガス炉、原子燃料サイクルを担う高速炉などの開発も推進。いずれも2040年以降の実用化を目指している。
日本では2011年以降、原子力発電所の新増設計画が停止し、原子炉の製造に必要な高度な技術や部品などのサプライチェーンの維持が懸念されている。「一技術者として、原子力をエネルギー源として使っていくことは地球の将来に有益だと考えている。原子力技術を維持し、若い技術者を育てるためにも新しいプラントを早期に実現できるよう取り組んでいきたい」

写真提供:三菱重工業

- 西谷順一
三菱重工業原子力セグメント
原子力技術部次長
近畿大学|大学原子炉第1号で実践教育 近畿大学の原子力人材育成
原子力の活用には専門知識を持つ人材が欠かせない。人材育成の重要な担い手が、近畿大学原子力研究所だ。日本のエネルギー安定供給に向け、原子力の実践教育が必要と考えた初代総長・世耕弘一氏が原子炉の導入を決断。1961年に日本初の大学原子炉として運転を開始した。

近畿大学の教育用原子炉
近大原子炉は熱出力が1Wと小さいので、格納容器や圧力容器、冷却装置も必要ない。核分裂生成物の生成がわずかで、汚染や被曝の恐れが少ないため、炉心への接近や燃料操作が容易にできるのが特徴だ。「数式を解けば頭では理解できる。加えて実習を行うことで、数式どおりに動くかどうかリアルな体感を得て、研究の面白さを知る。工学分野は、実習で勘所を磨くことが何より大切」と、若林源一郎教授は強調する。

原子炉の運転を学ぶ海外の若手技術者・研究者
原子炉実習では、学生が原子炉の起動→臨界調整→出力変更→停止までの一連の操作を行い、基礎的な原子炉物理・放射線計測を体験する。全国14の大学・大学院および高専生に加え、アジア太平洋、アフリカを中心に海外からの研修生も受け入れている。取材当日、原子力研究所では国際原子力機関(IAEA)の協力による研修会が開かれており、アジア、アフリカの若手研究者・技術者10人が原子炉運転を体験していた。
全国の大学で原子力を学べる学部が減り、2011年の東京電力福島第一原子力発電所事故以降は学生の志望者数が減少している。「とはいえ、逆風のなかでも原子力に興味を持ち、学びたいという学生は存在し、意欲も高い。その受け皿を用意しておくことが重要だ。原子力利用は医療、宇宙、産業分野など裾野が広く、原子力発電所を持たないオーストラリア等でも科学インフラとして原子炉を持っており、理工学研究に生かしている。原子力先進国としてエキスパート育成に尽力していきたい」。原子力発電所の安全安定運転や新増設にも原子力人材は不可欠だが、現在原子炉を保有する大学は近畿大学と京都大学だけだ。近大原子炉が果たす役割はますます大きくなっている。

- 若林源一郎
近畿大学 原子力研究所教授
1970年生まれ。九州大学大学院工学研究科博士課程修了。専門は放射線工学。九州大学助教、近畿大学准教授を経て、2020年より現職。
![YOU’S[ユーズ]](/corporate/report/yous/images/header_logo.png)