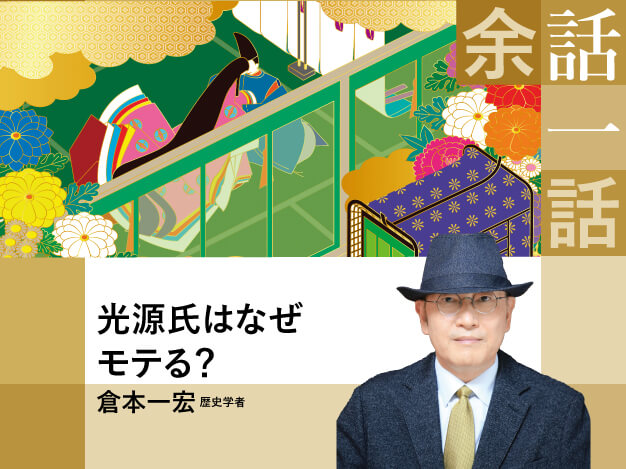IMDの「世界競争力ランキング」によると、日本の競争力は1992年の1位から2023年には過去最低の35位と下降の一途。日本の国際的プレゼンスの現状と行方、ありたい姿、課題と方策を、経済・エネルギー安全保障も視野に考えた──
経済力で押し切れないなら知恵・戦略で。
今の日本の国際的プレゼンスは悪くない
安田 今日のテーマは「国際競争力」です。村田さんは現時点の日本のプレゼンスをどうご覧になっていますか?
村田 私はさほど悪くないと思っています。人口減少やGDP減少など国力低下の流れは大きくは変えられませんが、例えばアメリカにとっての日本の必要性、先進国とグローバルサウスの仲介役などで日本の存在感が増していることは事実。減退している面と、強まっている面、両面があります。
安田 強まっているのは、日本政府が10年ほど前から主体的に動いた結果なのか、それとも世の中が変わったからか、どちらが大きいんでしょう。
村田 日本の国力低下への危機感で、過去10年、従来以上に日本が戦略的に動くようになりました。つまり体力がなくなるなら知力で行こうと。経済力で押し切れなくなった分、戦略的マインドを随分働かせるようになった。この間、トランプ政権の出現などアメリカの混乱、EU離脱といったイギリスの混乱など、先進民主主義国の規範とされてきた国々の混乱が大きかったため、相対的に日本の安定度が目立ったとも言えます。
競争力ランキング、日本はハード・インフラは強いが、
人と組織などソフト面は弱い
安田 競争力という点では、毎年スイスのビジネススクールIMDが、国際競争力ランキングとデジタル競争力ランキングを出しています。OECD諸国を中心に64の国と地域の中で、トータルと個別項目ごとに順位を付ける。競争力ランキングで日本は2023年過去最低の35位。調査が始まった1989年から4年間日本はトップでしたが、今やすっかり凋落しています。
デジタル競争力ランキングも全体順位が過去最低の32位で、個別項目の評価の高低に結構特色が出ています。高い項目で言うと、産業用ロボットとモバイルブロードバンドなどが2位。翻って低いのは、機会と脅威への対応が62位。デジタル技術/スキルは63位。ビッグデータの活用と分析、企業の俊敏性、そして国際経験は最下位です。つまりロボットや通信インフラといったハードウエア、インフラ面は世界でもトップクラスの一方、人と組織に代表されるソフト面はうまく機能していないのです。


IMD(国際経営開発研究所 International Institute for Management Development)
スイス・ローザンヌに拠点を置くビジネススクール。1989年から「世界競争力ランキング」、2017年から「世界デジタル競争力ランキング」を公表。
イタリアの魅力・ポルトガルの豊かさをモデルに
22世紀の日本像をイメージしてみる
安田 課題もありますが、現状、悪くはない国際的プレゼンスを示している日本は、今後何を強化し、どういう姿をめざせばいいでしょうか。
村田 戦後80年近く日本が積み重ねてきた国際的信頼は非常に厚い。日本は国も企業も派手なことはしないが、約束は守るし、しっかりした仕事をする。そういう国際的信頼を維持し続けることが大事です。
中国の台頭が続く国際環境下、アメリカの同盟国・日本がめざすべきは、東西冷戦期にイギリスがアメリカに果たしたような役割ではないか。1950年代マクミラン英首相のアイゼンハワー米大統領に対する言葉──「今の米英関係は、かつてのローマとギリシャの関係と同じ。ギリシャは没落したが、その知恵はローマ帝国に息づき繁栄に寄与している」と。そういう第2のイギリスのような役割を日本が果たせるかどうかが、世界にとって重要です。
安田 かつての経済大国、ものづくり大国から科学技術立国や観光立国、多様なビジョンが描かれてきましたが、今後はどう捉えればいいですか。
村田 自動車やIT、観光など、分類の発想ではダメ。日本は人口が今後どんどん減少し2100年に約6000万人。私は、22世紀初頭に日本が今のイタリアのような国として生き延びられれば、ほぼ成功ではないかと思うんです。
イタリアの人口は6000万人ほどで、GDPは世界10位。EUの中で独仏ほどの力はないが、イタリアの意向をEUは無視できない。魅力的なハイブランドを持ち、高級車など製造分野でも競争力があり、観光や食でも世界を惹きつける。日本もそういう準大国として22世紀を迎えられたら、そこそこ成功。そのためにどうするかを考えないといけない。
安田 なるほど。将来の日本を考えるにあたって、モデルとなるような国やビジョンを掲げるのは非常にわかりやすいですね。
僕は3年前に在外研究(サバティカル)でポルトガルのリスボンに1年半滞在したんです。ポルトガルはイタリア以上に小国で人口は約1000万人、大航海時代の栄光も500年以上が経ちすっかり忘れ去られています。でもとてもいい形で衰退していて、1人当たりGDPは西欧平均の半分ほどですが、年中太陽が輝いていて冬も暖かく、欧州やアメリカから観光客が大勢来る。食事もおいしく、それなりに楽しく豊かに暮らしている印象でした。
日本から海外を見ると、米中などの大国ばかりに目が行きがちですが、小国で暮らすと見方が変わりますよね。多くのヨーロッパ諸国は、人口や経済は小規模でも、歴史・文化・伝統は非常に豊かです。
大航海時代
15世紀半ばから17世紀半ばのヨーロッパによるアフリカ・アジア・アメリカ大陸への大規模航海の時代。先陣を切ったポルトガルは喜望峰到達をはじめ、ヴァスコ・ダ・ガマによるインド航路開拓、ブラジル発見など、「7つの海を制した」と言われるほど繁栄を極めた。1543年種子島への鉄砲伝来もこの時代。

世界を席巻する日本のソフトパワーの背景に
新規性を許容する土壌と競争がある
安田 文化についてポルトガル生活で実感したのは、日本のソフトパワーの強さです。ポルトガルはもともと親日国ですが、ドラゴンボールやポケモンといった日本の人気コンテンツを通じて、過去でなく今の日本に興味を持つ若者が増えています。日本のソフトパワーをどう見ていますか。
村田 私、下の名前が晃嗣で、昔、海外でコージだと言うと、いきなりマジンガーZと言われてね(笑)。マジンガーZの主人公が兜甲児だからですが、日本のアニメや漫画の魅力は世界に浸透。おそらく多くの人がコンテンツの面白さだけでなく、それを量産する日本社会の安定性や秩序感など包括して魅力を感じているのではないでしょうか。
安田 実は日本には新しいものを許容する土壌が結構あって、試行錯誤と競争があちこちで起きています。例えば音楽では、ボーカロイドという電子的な音声合成技術が世界に先駆け発展し、YOASOBIなどのアーティストが世界を席巻。数十年前に、YMOが世界にテクノミュージック旋風を起こした先例もあります。こうした強みを再現していくには、斬新で面白いものが同時多発的に出てくる環境をどう実現するかにかかっています。
バスケ、卓球、フィギュア、サッカーなどスポーツ分野の成功もヒントになりそうです。スポーツでは、個人のパフォーマンスが徹底的に可視化されるので健全な競争が生まれやすい。結果的に優れた日本のアスリートが世界中で活躍しています。企業内でも、社員の試行錯誤や競争が進めばもっと成果に繋がるはず。それができない組織は、今後厳しいでしょう。
同心円の関東と複数のブランドを持つ関西、
違いの存在・多元性が日本の強さに繋がる
村田 競争がシナジーを生む形になればいい。例えば関西、東京に対し関西の経済的地位が下がっているにもかかわらず、大阪と京都と神戸がバラバラ。京阪神それぞれ違う魅力で、シナジー効果を出すといいのですが。
安田 東京出身の僕から見ると、この違いが面白いです。世界での知名度は京都がずば抜けて高く、国際会議を開くとみんな来たがりますよ(笑)。関西圏で、外から人を集めたいときは京都、経済支援が必要であれば大阪、港町の雰囲気に浸るなら神戸、と使い分けられる。こうした複数ブランドがあるのが関西の強みなのに対して、関東は東京一極集中ですね。
村田 そうそう、同心円的な文化ですからね。関西が総合力を発揮できなければ、日本全体の地盤沈下を加速しかねない。東京に対するオルタナティブを文化的にも経済的にも追求できる地域があることは、日本の強みとなる。イタリアは、内側に多様な活力があって、死に絶えることなく、伸び縮みするイメージ。ローマも魅力的だけどミラノもフィレンツェもという多元性を持つ社会でなければ、生き延びていけない。
日本は大企業に牽引される経済だけでなく、1000年続く老舗企業から生まれたてのベンチャーまで元気な中小企業が多く、大企業が転んでも中小がしたたかに生き残って次の活力につなげていく。そんな強さがあります。
他国指標のランキングでは負の連鎖に陥る。
豊かさを適切に評価できる新たな指標をつくる
村田 ただ、気がかりなのは、ランキングに振り回されていないかということ。評価は大いに参考にしますが、常にランキングされる側でなく、我々の価値観や視点を入れてランキングをつくる力が日本にあるかどうか。
安田 確かに日本は、GDPでは残念な状態が続いていますが、訪日外国人の目にはとても衰退しているようには見えないでしょう。おそらく、GDPでは測れない社会的ストックとしての豊かさがあるからです。それを見える化する新しい指標をつくれば、世界に対して豊かさの見方を変えられるかもしれません。たとえば、治安や安全性はGDPでは測れません。むしろ、ひったくりに遭ってけがをして病院に行ったほうがGDPは増えます。
村田 裁判の訴訟もGDPに入りますからね。訴訟のない国のほうがいいが、アメリカのように訴訟が多い国のほうがGDPは高くなる。
戦後日本の自画像は世界第2位の経済大国。それが中国に抜かれ、先般ドイツに抜かれて4位、程なくインドに抜かれ、と既存ランキングで物を見ている限り、心理的に負の連鎖に飲み込まれる。GDPが下がっても、我々にはこんな豊かな資源があるという再発見を続けることが大事です。
安田 若い世代は、下がり続けるGDPなど暗い話ばかり聞かされ続けて、将来に良いイメージを抱けません。日本の多くの組織は、意思決定を行う経営層がミドルからシニアの男性中心です。多様性のない社会で、ずっと右肩下がりの日本が強調されると、若者の意欲が失われてしまいます。
村田 日本も世界もリーダーの世代交代がやがて各界で起きてきます。
今年の米大統領選挙は、81歳と77歳の競争。世界一の大国で、なぜ老人ばかりなのかと言われますが、次の2028年にはきっと世代交代が起こる。
米大統領の歴史を遡ると、アイゼンハワーからケネディへ27歳若返り、父ブッシュからクリントンへ22歳、今回の80代の次40代50代になれば、40歳ほど若返る。この世代交代にうまく乗れるかどうか。日本も、昭和のおじさんたちが去った後の世代交代にどう備えておくかは大事です。

変化する社会を支えるインフラ企業だからこそ、
安定・信頼と変革・革新の両立が大事
安田 最後に電力会社について言えば、ウクライナや中東情勢の不透明性が高まるなか、どうすれば安定的に電力を供給できるか。半導体など一瞬でも止まるとアウトですからね。ものづくりや暮らしやすさ等の国際競争力を考えたとき、電気の安定供給と低廉さは決定的に重要です。

村田 そうですね。ウクライナもガザの紛争も終わりが見えず、日本がいかに安全保障上脆弱な環境にいるかを見せつけられている。外交努力に加え、エネルギーや経済の安全保障として、いかに安定した基盤を確保するか。電力もガスも鉄道も、インフラ系の企業は、ローカルに密着しながら、グローバルな視点で状況を分析・発信することが極めて大事です。
安田 日本は停電がほとんどなく、安定供給に強みがある。安心して使えるインフラ、安心して暮らせる社会の実態も見える化されるべきですね。
村田 日本のアニメや漫画などソフトパワーあるいは時刻どおりに走る電車や、清潔、安全、健康も、根底にあるのはインフラの安定性。電気がいつ止まるかわからないところで高度な医療が施されるわけもない。日本外交が信頼されているように、インフラ企業も安定・信頼が強みですが、他方で変革やイノベーション。この2つの両立が今後の課題でしょうね。
安田 国も地域も企業も、必要なリストラクチャリングを進めるとともに、安定感や信頼感をしっかり維持していけば、決して未来は暗くありません。今日は改めてそれを確認できました。どうもありがとうございました。

- 村田 晃嗣 むらた こうじ
同志社大学法学部政治学科教授
1964年兵庫県生まれ。同志社大学法学部卒、神戸大学大学院法学研究科博士課程(国際関係論)修了。広島大学総合科学部助教授、同志社大学法学部助教授を経て2005年より教授。13-16年学長。専門は外交・安全保障政策論。18年より日本放送協会(NHK)経営委員。19-20年防衛省参与。著書『大統領とハリウッド』『トランプvsバイデン』など。
https://law.doshisha.ac.jp/law/teacher/politics/muratak/profile.html

- 安田 洋祐 やすだ ようすけ
大阪大学大学院経済学研究科教授
1980年東京都生まれ。東京大学経済学部卒、米プリンストン大学経済学部博士課程修了(Ph.D.)。政策研究大学院大学などを経て2022年より現職。専門はゲーム理論とマーケットデザイン。20年経済学をビジネスに活用する(株)エコノミクスデザインを共同創業。編著『学校選択制のデザイン』、共著『そのビジネス課題、最新の経済学で「すでに解決」しています。』など。
https://yagena.github.io/jp/
![YOU’S[ユーズ]](/corporate/report/yous/images/header_logo.png)