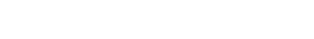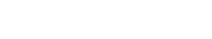

1950年代、敗戦を乗り越えた日本は、産業再興へと邁進していた。やがて始まる大量生産大量消費の時代。
たくましい経済成長を続けるも、電力不足という課題に直面する。
豊かさを生み出す原動力であり、便利で快適なくらしの象徴である、電気。
その潤沢な供給は、是が非でも実現させなければならない。使命を担った関西電力は、社運を賭した。
人跡未踏・厳冬の地で繰り広げられたのは、強い信念なくしてはとても貫徹できない究極の難工事だった。
全社員が固唾をのんだ現場の苦闘。一人ひとりが、電力供給への熱い想いを試され続けた。
こうして、「関電スピリッツ」はそれと意識されることなく全社員の心中に育まれ、しっかりと根を下ろした。
以来連綿と引き継がれ、試練にさらされれば自然発生的に全社規模で立ち上がる「関電スピリッツ」。
ここではまず、そのルーツとなった“くろよん”の話をしよう。

家電製品のある便利なくらし。その歴史は、意外なほど新しい。今はどこの家庭にもある冷蔵庫、洗濯機、トースターなどが登場し、電気元年と名づけられたのは、つい半世紀余り前、1953年のことだ。本格的な普及はまだ先で、このころ家庭の冷蔵庫といえば、氷屋が配達する氷を入れて冷やす、小さな食品庫に過ぎなかった。戦中の不便なくらしに耐えてきた人々は、家電製品の登場に明るい新時代の到来をはっきりと実感したことだろう。家電製品はみるみる普及し、50年代半ば以降の高度経済成長をしっかりと支えていく。こうして、家庭では照明以外にほとんど使われることのなかった電気が、打って変わって大きく利用されるようになっていった。
一方、つくれば売れたこの時代、産業界もかつてない活況を呈していた。鉄鋼業、非鉄金属製造業、化学工業など、膨大な電力を消費する産業が、増産に継ぐ増産を重ねていく。
戦後の復興期から高度経済成長時代にかけて、関西圏の電力供給を担う関西電力にとっては、新たな発電所を建設して電気を増産することが、長年にわたる課題であった。

日本に電力会社が誕生した当初、発電の主流は水力発電だった。特に日本は、気象も地理も水力発電に適していたことから、水力発電所が多く建設された。だが、渇水期には発電量が落ちてしまうことから、水力発電を補助する役割として、火力発電が用いられた。これを「水主火従」と言う。電力需要が高まりを見せた1950年代には、火力発電技術が飛躍的に高まり、それまでよりも高効率で大容量の発電が行えるようになった。その特質を活かすべく、主流を水力発電から火力発電へと転換した「火主水従」が目指されるようになった。発電の主流を水力から火力へと移し、断続的な稼働でもロスなく発電できる水力発電に、需要に合わせた発電量の調整を任せようというのである。水力発電は「主」から「従」にまわることになるが、需要そのものが急速に拡大しているだけに、調整に必要な電力も半端な量ではない。大規模なダムが求められていた。
1955年秋、関西電力は、この「火主水従」時代の到来に先駆け、社運を賭しての挑戦となる“くろよん”の建設を決断した。“くろよん”とは、黒部川第四発電所。1951年の電気事業再編によって関西電力が発足するはるか以前から調査や立案がなされながら、あまりの難事業ゆえに先送りされてきた、大規模な水力発電所だ。
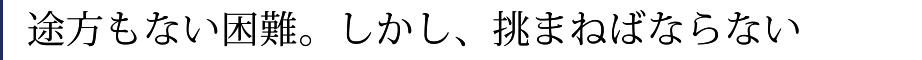
覗き込めば目がくらむ。深い谷のはるかな底。岩をかむ激流がまるで糸のように細く小さく目に映る、それが黒部の峡谷。“くろよん”はそんな、足を踏み入れることさえ難しい地に建設が予定されていた。それも、堤の高さ186m、堤最上部の端から端まで492m、計画上の貯水量1億6000万m³という、当時日本最大、世界でも第4位のドーム型アーチ式ダムを築き、580mもの落差を活用。地下に発電所を設置して、25万8000kWを出力しようというのである。
今後の電力供給には、大きなダムが欠かせない。われわれの前に黒部に勝る適地がないのであれば、どうあっても“くろよん”の建設に着手しなければならない。そんな一途な想いが決断を支えていた。リスクが低下するのを待っていては、たとえ10年たっても動き出せないだろう。それでは電力安定供給の使命が果たせない。「存在するリスクをいかにして克服するかという点に、経営者としての手腕が掛かっているのではないだろうか」。当時の社長、太田垣士郎の述懐には、決断の重みがにじみ出る。

工事の難航はマスコミにも取り上げられ、関西電力の経営が窮地に陥りかねないとも噂された。しかし、社長・太田垣は、どっしりと構えて揺るがない。もともと、リスクを認識したうえで着手した事業だ。現場をねぎらいこそすれ、決して急かそうとはしなかった。
また、「鉛筆1本、紙1枚を節約してでも、“くろよん”の支援を」という雰囲気が社内に広がり、「“くろよん”に手を貸そう」運動が全社で展開されていった。「社会の要請を受け秘境で闘っているのは自分たちの仲間であり、彼らと自分たちは、支援の心でつながっているのだ」。その自覚は、関西電力社員の大きな誇りともなった。
この状況下で、関西電力は良質の資金調達にも挑戦した。なかでも特筆すべきは世界銀行借款の成功である。建設現場が破砕帯(※1)との格闘を続けている間も、日本政府を通じて世界銀行に働きかけ、後に日本初となるインパクト・ローン(※2)成立を勝ち取り、3700万ドル(133億2000万円)の融資にこぎ着けている。その額は“くろよん”建設資金の約4分の1をまかなうに足る大きさだった。
それぞれがそれぞれの持ち場で、しっかりと“くろよん”を支えていた。
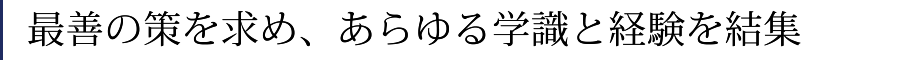
破砕帯突破は、“くろよん”建設関係者たちの悲願となった。トンネル内部の支えを大きく強化して崩落を防ぎながら、前後左右に枝分かれしていく水抜き用のトンネルを何本も掘り進んだ。また、地質調査と水抜きのためのボーリングを重ね、発見された水脈に向けセメントと化学薬液を注入して固めるハイドロック法も根気よく繰り返した。打てる手はすべて打つんだという太田垣の方針に従い、大きな鋼鉄の筒で安全な作業空間を確保するシールド工法を実施するための高性能な機械も発注された。
さらに、地質学者、丹那トンネルや関門海底トンネル貫通などに携わった実績を持つ旧国鉄のOBや現役技術者、海外の技師などを招いて、あらゆる学識と経験の結集が図られた。大きな変革の中で、安定的な電力供給を待つ関西の人々のことを思うと、一刻たりとも無為に時を過ごすことはできなかった。
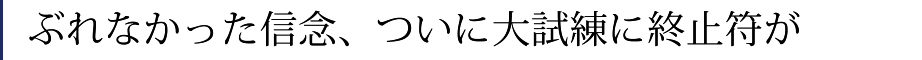
経営者としての責任を一身に担う太田垣の頭には、“前進”の二文字しかなかったのだろう。破砕帯との遭遇に恐れをなして後退し、未知数の別ルートに再びゼロから挑もうとする意見にははっきりと異を唱えた。直面する困難から目を背けると成功は遠のくばかりだ。決してぶれないその信念は、建設現場の雑念をも消していく。たとえ今は目に見える効果がなくても、破砕帯からの水はいつか必ず止まる。そう信じることが、日々の作業の原動力となった。
表面的には徒労のように見えながら、地道な作業は着実に地中の様相を変えていた。9月の半ばから末にかけて湧水がみるみる激減。なおも水抜きやボーリングを続行しながらではあるが、途絶えていたトンネルの掘削を再開することができた。トンネル掘削は着実に前進し、ついに12月2日、悩みに悩まされた破砕帯の突破が確認される。はじけるように、歓喜の渦が巻き起こった。測ってみれば坑口から1762m。破砕帯に遭遇した5月1日以来、「わずか70m足らずの掘削に7か月もかけた大試練」は、全社の結束を固めて終結した。

その後、掘削は順調に進み、翌1958年2月25日、貫通にこぎ着けた。厚い山塊は、ついに関西電力の熱意に貫かれたのだ。これを弾みに“くろよん”工事はいよいよ本格的なダム建設へと突き進む。終盤の山場、昼夜兼行のコンクリート打設が続く1959年9月26日には、吹き荒れた伊勢湾台風のためにセメント輸送の動脈を切断されるという危機にも見舞われたが、関西電力は即座に社内外に呼び掛け可能な限りの輸送手段を確保するなど、結束して事に当たり、計画通りの工事進行を支援した。
1960年10月には、ダムの完成に先駆けて貯水を開始。3か月後に一部発電が始まり、徐々に出力を増加して、1962年8月、全面運転が実現した。ダムの竣工式は、1963年6月5日。7年の労苦が、黒部を豊かな電力の源に変えた。
この間、関西電力の社員は、ダム建設業務に直接携わっていない者も、想像を超えた難工事を見守り続けた。“くろよん”の建設を通して電力安定供給の難しさと重要性を、自らの胸に問い直さなかった関西電力社員はいないだろう。この経験は、後世まで脈々と受け継がれる関西電力の「関電スピリッツ」の礎となったのである。